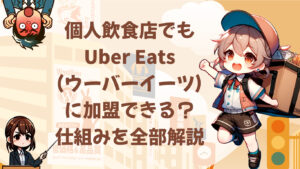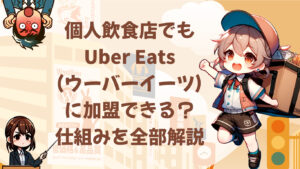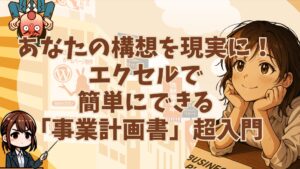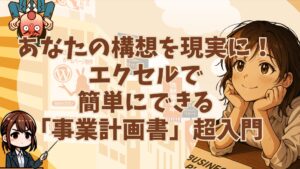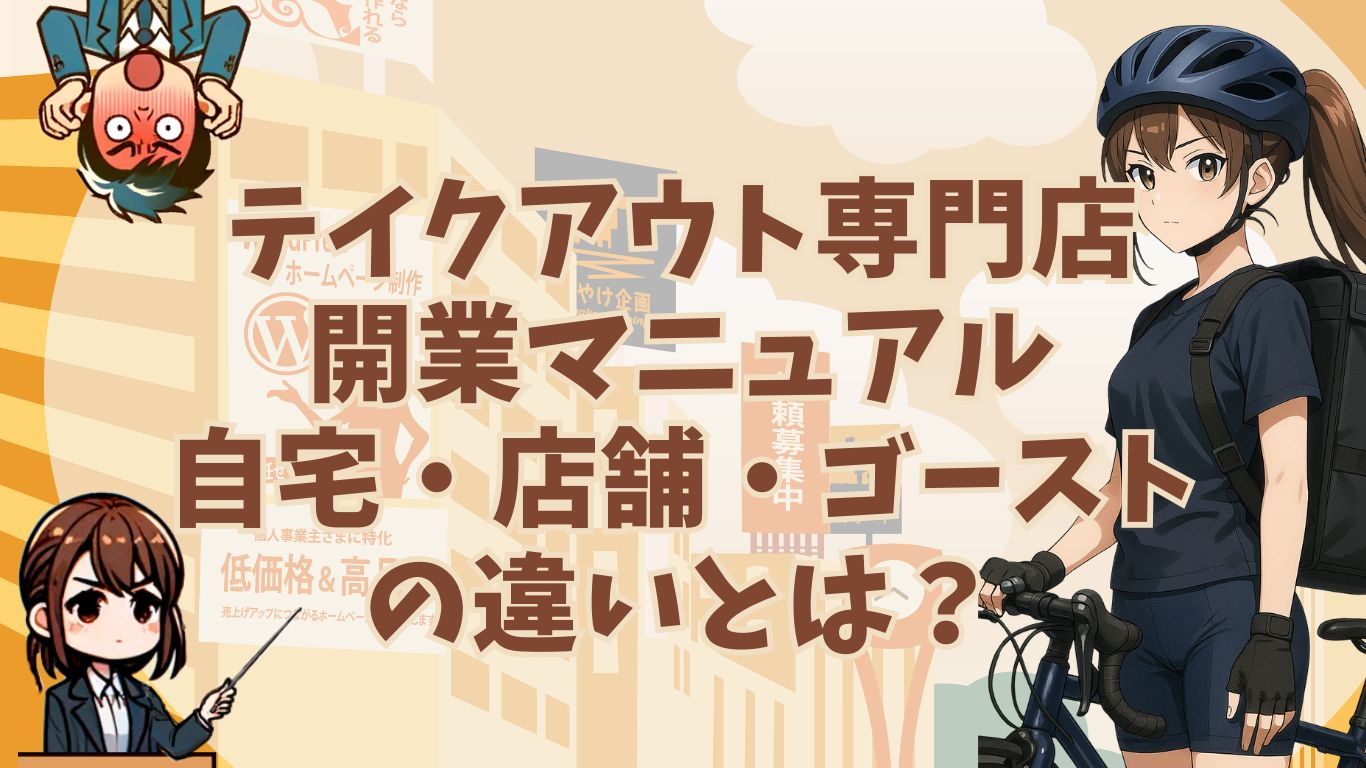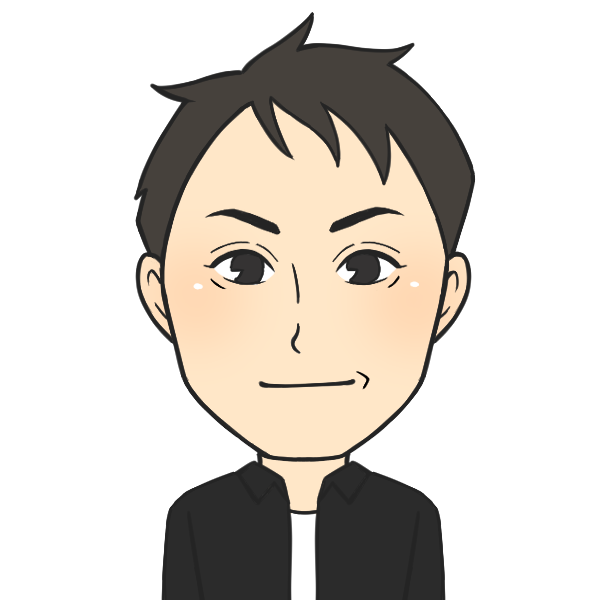甲斐承太郎
甲斐承太郎なんか、最近テイクアウト専門店とかって流行ってるみたいね。
なんかキッチンのスペースだけで開業できるから、すごく安く開業できるって聞いたよ!
でも、テイクアウトだけでちゃんと儲かるのかな?



確かに最近はテイクアウト専門店の人気が高まってます。
とくに個人で小さく始めるお店としては、すごく合理的なんだ。
店内スペースや接客スタッフが必要ないぶん、
・初期費用が抑えられて
・ワンオペでまわせる
・小さく始めて、大きく育てることもできる
つまり、これから開業を考えている人にとっては、「ちょうどいい規模感」のビジネスなんだよ。
- 自分に合ったテイクアウト専門店の開業スタイルがわかる
- 必要な許可や資格、設備の条件が明確になる
- テイクアウト専門店で成功するための実践的なヒントが得られる



テイクアウト専門店は、小資本で済むため、未経験者や副業での開業にも適しています。
運営コストが低く抑えられ、売上を得やすい構造である点が評価されています。
テイクアウト専門店とは?中食ビジネスの基本





ところでさ、「テイクアウト専門店」って普通の飲食店とどう違うの?
イートインがないだけで、やることは同じなんじゃない?



いい質問です。
テイクアウト専門店は「中食(なかしょく)」って言われるジャンルに分類されるのです。
最近は「固定費をかけずに飲食店を始めたい」という人にすごく注目されてます。
- 内食(うちしょく):家で料理する
- 外食(がいしょく):お店で食べる
- 中食(なかしょく):お店で買って、家や外で食べる
- お客様が店内に滞在しない(席が不要)
- 配膳・接客スタッフが不要(ワンオペに最適)
- 回転率や滞在時間に左右されない
- 小スペース・低家賃でも開業できる
- Uber Eatsなど宅配導入とも相性がいい



なお、法律上は「飲食店営業」に分類されるため、通常の飲食店と同じく営業許可が必要です。
詳細は後述の許可解説セクションで整理されます。
テイクアウト専門店の開業スタイル一覧



実際にテイクアウト専門店って、どういうスタイルで始められるの?
なんか自宅とかキッチンカーとか、いろいろあるみたいだけど…



今はテイクアウト専門店にもいろんな形があるんですね。
それぞれにメリット・注意点があるから、自分のスタイルに合った形を選ぶのがポイントです。
代表的なスタイルを4つ紹介するよ。
自宅キッチンで始める


- 自宅の一部を調理場として使うスタイル
- 保健所の設備基準をクリアすれば開業可能
- 家賃ゼロ、通勤ゼロで開業できる
- 調理スペースと生活スペースの完全分離が必要
副業・育児と両立したい人、固定費を最小限に抑えたい人
小型テナントで開業する


- 小さなテナントを借りて、厨房だけの店舗を運営
- 飲食スペースなしのため内装費が少ない
- 開業資金はやや必要だが、プロ感と安心感あり
本格的に飲食店を始めたい人、駅チカや人通りの多い立地で開業したい人
ゴーストキッチン(シェア型)


- 飲食スペースのない、デリバリー専門の厨房を間借り
- 店舗費用を抑えつつ、Uber Eatsなどで販売
- ブランド力とネット集客がカギになる
ネット集客に自信がある人、実店舗を持たずに始めたい人



「自宅開業の場合は、特に保健所の基準が厳しいため、事前に設備要件を確認して改装工事が前提になります。
一方、「ゴーストキッチン」は設備を共有するぶん、調理内容や営業条件に制限が出ることもあります。



ゴーストキッチンは、「まずは少資本で試してみたい人」「デリバリーで勝負したい人」にとって有力な選択肢です。
ただし、店舗の存在感がない=目に見えない存在になるため、集客はSNSや口コミ、配達アプリでの評価が重要になります。
継続的に売上を上げるには、写真・メニュー構成・価格設計・レビュー管理まで含めて“見せ方の戦略”が必要です。
売れる商品アイデアと傾向



ところでさ、テイクアウト専門店ってどんな商品が売れてるの?
ただ持ち帰りできればなんでもいいのかな?



いやいや、やっぱり「売れる商品」にはいくつか共通点があるんですよ。
とくにテイクアウト向きの商品には、次のような特徴があります。
- 冷めても美味しい・品質が落ちにくい
- 包装しやすく、持ち運びしやすい
- 食べるタイミングを選ばない(ランチ・夕食・夜食など)
- 見た目にインパクトがある(SNS映え)
- 他店と差別化できるコンセプトがある
| 商品ジャンル | 特徴 | 向いているスタイル |
|---|---|---|
| おにぎり・弁当 | 食事系・ボリューム重視 | 自宅・テナント |
| サンドイッチ・バーガー系 | 包装しやすく見た目も良い | テナント |
| スープ・惣菜 | 主婦層や健康志向に人気 | 自宅・ゴーストキッチン |
| 焼き菓子・マフィンなど | 保存性が高く手軽 | 自宅・ゴーストキッチン |
| アジア系(カレー・ガパオ) | 個性とコストの両立がしやすい | テナント |



原価率を意識した商品設計が重要です。
たとえば、米やパンを主軸にした商品は、コストを抑えつつ満足度を高める構成に適しています。
また、衛生管理のしやすさも、調理工程を考える上でのポイントになります。
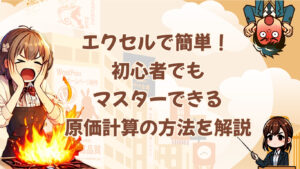
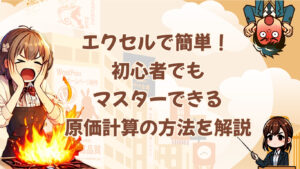
テイクアウト専門店に必要な許可は?



そういえば、テイクアウト専門店でも営業許可って必要なんだよね?
なんとなく「お店で食べるわけじゃないから大丈夫」とか思っちゃいそうだけど…。



前述しましたが、基本的には「飲食店営業許可」が必要です。
テイクアウトだけの営業でも、調理して提供するなら保健所の許可が必須なんだ。
- その場で調理して提供するスタイルなら、イートインがなくても飲食店営業許可が必要
- 自宅・ゴーストキッチンでも同様に、調理するなら許可が必要
必要な許可の種類と判断表
| 店舗スタイル | 調理の有無 | 必要な許可・届出 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 自宅営業 | あり | 飲食店営業許可+設備対応 | 調理場と生活空間の分離が必要 |
| パン・菓子を製造販売 | あり | 菓子製造業許可 | 甘味系・ベーカリー系 |
| 加工なし販売 | なし | 食品販売業許可または営業届出 | 包装済商品の販売など |
| 惣菜店 (弁当など) | あり | 飲食店営業許可 or そうざい製造業許可 | 提供スタイルを総合的に判断して 保健所により対応が変わる |
| ゴーストキッチン | あり | 飲食店営業許可(借用拠点) | シェア施設の設備に依存 |



惣菜関係は加熱や盛り付けなど、ちょっとした加工でも「調理」と見なされるケースが多いから、判断に迷ったら早めに保健所に相談するのがおすすめです。
- 各施設に1名必要(個人営業でも自分が取得する)
- 1日講習で取得可能(都道府県ごとに実施)
- 営業許可の申請時には、資格証の写しを提出
- 調理場と居住空間を完全に分ける必要あり
- 自宅キッチンのリフォームが必要なケースも
- シェアキッチンでは「営業許可の譲渡」ができないため、必ず自分名義で手続きをすること
テイクアウト専門店のメリット・デメリット





でもさ、店内で食べてもらう飲食店と違って、テイクアウト専門店ってどんな良いことがあるの?
逆にデメリットとかもあるのかな?



やっぱりどんなスタイルにも一長一短があります。
特に「テイクアウト専門店」は、うまくハマると利益率も高くなるけど、注意点もあるから確認しておきましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 初期費用が安い → テーブルや内装工事が不要。物件も小規模でOK。 | 回転率がない → 滞在時間を使った売上アップが見込めない。 |
| ワンオペが可能 → 接客が少なく、仕込み~販売まで1人でも回しやすい。 | その場での顧客体験が少ない → 店内の雰囲気や接客でリピーター化しにくい。 |
| 客席トラブルがない → 飲酒や長時間滞在などの問題が少なく、衛生管理に集中できる。 | 場所選びがより重要 → 通行量・立地がモロに売上に直結。 |
| コロナ以降のニーズに合致 → 「持ち帰り」「非接触」で需要が安定。 | 衛生管理の基準が緩くはならない → 「食べる場所がない=手抜きOK」ではなく、保健所の基準は通常の飲食店と同様。 |
| デリバリーとの相性が良い → Uber Eatsや出前館などと組みやすい。 | 雨や天候の影響を受けやすい(特にキッチンカー) → 集客が不安定になる日もある。 |



テイクアウト専門店は省スペース・省人員化が最大の武器ですが、集客は立地や導線、SNS戦略に強く依存します。
また、リピーター獲得には商品力とパッケージ、店名やロゴといったブランド設計も欠かせません。
テイクアウト専門店の開業手順



実際の開業方法は、「どこで」「どのスタイルで」営業するかによって変わります。
以下は、基本の共通ステップと、それぞれの営業形態に合わせた補足ポイントです。
まずは「どんな商品を」「誰に」「どうやって」提供するかを明確にします。
- 例:出勤前のビジネスマンに、朝限定のおにぎりセットを販売
- 例:近所の主婦層に、無添加の手作りお惣菜を夕方に販売
- 例:SNSで若年層にリーチする韓国チキン専門ゴーストキッチン
どの方法で売るかによって、必要な設備や許可が変わります。
| 店頭販売 | お客が直接来店し、持ち帰る | 惣菜屋・弁当屋 |
| 予約受取 | 事前予約→決まった時間に受け取り | おにぎり屋、焼き菓子店 |
| 配達(デリバリー) | 自社or外部配達サービスで届ける | ゴーストキッチン |
| ネット注文&発送 | EC型・冷凍弁当や焼き菓子の全国発送など | オンライン専門スイーツ店 |
以下のように、販売スタイルに応じて必要な許可が異なります。
| 許可の種類 | 適用ケース |
|---|---|
| 飲食店営業許可 | その場で調理・容器に盛り販売する場合 |
| 菓子製造業許可 | 焼き菓子などを袋詰めして販売する場合 |
| そうざい製造業許可 | 煮物・揚げ物等を製造・包装して販売 |
| 営業届出(簡易業態) | 洗浄・加熱なし、包装済商品の販売など |
自宅で開業する場合の補足
- 営業可能な間取りや設備が必要(別キッチンや専用区画など)
- 自治体によって用途地域制限あり。事前に保健所に確認必須
テナント・物件の場合の補足
- 設備要件(手洗い、換気、区画)を満たす内装が必要
- 消防法や建築基準法にも配慮(飲食OKな物件か確認)
ゴーストキッチンの場合の補足
- キッチン設備がすでに整っている施設を借りるため、
→「飲食店営業許可を包括取得」済みのケースもある - 登録すれば即営業OKのセットプランあり(KitchenBASEなど)
- 食品衛生責任者(必須):1日講習で取得可能(調理師免許があれば不要)
- 防火管理者(必要なら):一定規模の物件の場合は必要
- (自宅や小規模テイクアウトのみで不要な場合も)
- 店舗看板・メニュー表示
- SNSアカウント・地図登録(Googleマップ、Instagramなど)
- デリバリー連携(Uber Eats、出前館など)
- 自前のホームページや予約サイト(3do1などの活用が◎)
- 仕入れや包装資材の準備(保存容器、ラベルなど)
- 営業許可証の交付
- 検便・水質検査などが求められることも(自治体差あり)
補足:設備・保健所チェックの例
| 専用の手洗い場 | 客用トイレとは別に、厨房内に設置必須 |
| シンクの数 | 洗浄用・すすぎ用・手洗い用に区別 |
| 冷蔵・冷凍機器 | 温度管理・記録ができる体制が求められる |
| 加熱・冷却設備 | 電子レンジや加熱器の種類も要件になる |
| 包装・ラベル表示 | 名称・内容量・原材料・消費期限などが必要 |
成功するための考え方|失敗しない7つのポイント





やっぱり、せっかく開業するなら「ちゃんと成功させたい」よね。
テイクアウト専門店を始めるとき、気をつけるポイントってあるの?



もちろんあります。
開業の失敗は「最初の設計ミス」が原因なことが多いんです。
そこで、テイクアウト専門店で失敗を避けるための7つのポイントを紹介しよう。
- 立地と導線を徹底リサーチする
- → テイクアウトは「ついで買い」「通勤導線」で売上が決まる。
- 商品力は“冷めてもウマい”を基準にする
- → 味・食感・見た目が冷めても魅力的か?
- 原価率とFL(食材+人件費)を最初に設計する
- → FL合計は60%以内が目安。利益が出ない商品は売らない。
- SNSやLINEを前提とした広報設計をする
- → オープン前から情報発信。友達登録やフォローで集客の仕組みを作る。
- 保健所との相談は早めにする
- → 自宅やシェアキッチンは特に、営業許可の取得に時間がかかるケースも。
- 最初からデリバリーも想定しておく
- → Uber Eatsや出前館に加盟するなら、包装・価格・導線の設計が重要。
- Uber Eatsの加盟方法についてはコチラ
- “やらないこと”も決めておく
- → メニュー数を絞る、深夜営業はしないなど、自分のリソースに合った経営を。



テイクアウト専門店は「商品」と「オペレーション設計」が命です。
設備や立地よりも、「何を、誰に、どう届けるか」の設計次第で成否が分かれます。
また、個人経営なら“シンプルで強い1品”に絞るのが効率的です。
ゴーストキッチンという選択肢もある



そういえば最近「ゴーストキッチン」って言葉をよく聞くけど、あれって何?
なんか店舗がないお店ってイメージなんだけど…



ゴーストキッチンっていうのは、店舗を持たずに調理専用の場所だけを借りて、テイクアウトやデリバリーに特化した営業をするスタイルなのです。
物件の取得費や人件費を抑えられるから、個人開業にも注目されているんですよ。



自宅や店舗で営業許可を取得して開業するのが「テイクアウト専門店」の王道。
一方で「ゴーストキッチン」は調理だけに特化し、店舗を持たずにデリバリーで勝負する新しい形です。
- 店内飲食スペースがない
→ 完全にテイクアウト/デリバリー専用の厨房 - シェアキッチン型や単独契約型がある
→ 必要な設備がそろっていて、即営業可能なことも - 住所の貸し出し、営業許可の一括取得サポートあり
→ 初心者向けのセットプランを用意する業者も
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 家賃・初期費用 | 家賃が安い/短期契約も可能 | 利用時間や設備に制限があることも |
| 設備 | 業務用設備が整っており、すぐに営業可能 | 共有施設の場合、他店とトラブルのリスクも |
| 集客 | 立地の影響を受けにくく、どこでも開業できる | 集客はSNSやデリバリーアプリに依存 |
| 営業形態 | 店頭販売なしでOK、デリバリーに特化できる | 飲食スペースがないためブランドの認知が弱くなりがち |
| 多店舗展開 | 複数ブランドの同時運営も可能(バーチャルレストラン) | オペレーションが複雑になり、管理が難しい |



ゴーストキッチンは、デリバリープラットフォームを活用して低リスクに開業したい人向けです。
一方で、SNSや口コミ、デリバリーサイト上での露出強化がないと、集客に苦戦することもあります。
とくに、他店と差別化できる商品力とブランド設計が必要不可欠です。
- 丼もの、カレー、唐揚げ、パスタなど単品系・ワンプレート系
- 調理工程がシンプルで、時間の読める料理
- 冷めても美味しい or 保温がしやすい商品
- ブランド展開がしやすいネーミングやパッケージがある業態
テイクアウト専門店開業でよくある質問



開業前に「これ大丈夫かな?」って不安になるポイントは共通しています。
ここで、よくある質問をまとめました。



食品営業許可の種類と判断はややこしい部分もあるため、開業エリアの保健所に事前相談するのが最も確実です。
また、地域によって運用ルールに差があるため、ネット情報だけで判断しないようにしましょう。
まとめ|まずは小さく始めて、自由な働き方を目指そう



ここまで、「テイクアウト専門店を開業する方法」について、スタイルごとの特徴、許可、メリット・デメリット、成功のポイントなどを解説してきました。
テイクアウトは、飲食店のなかでも最も省スペース・低コストで始められる選択肢のひとつ。だからこそ、脱サラや副業で「自分のお店」を始めたい人にとって、とても現実的な第一歩になるんだ。



低資本でリスクを抑えながら始められるため、初期段階のテスト販売にも向いています。
飲食店の経験がない人でも、正しい許可と設備を整えれば営業可能です。
重要なのは、スタイルの選択・売れる商品・集客導線の3点を、事前にしっかり設計することです。



ボクみたいなお金のない個人でもスタートできるのが魅力的だね。
まずは副業からはじめて大きくしていくのもアリかもね!
ちょっと計画を立ててみよう!!