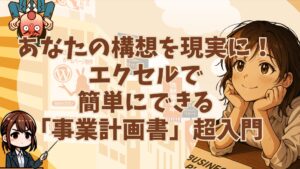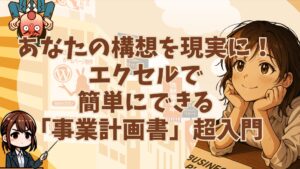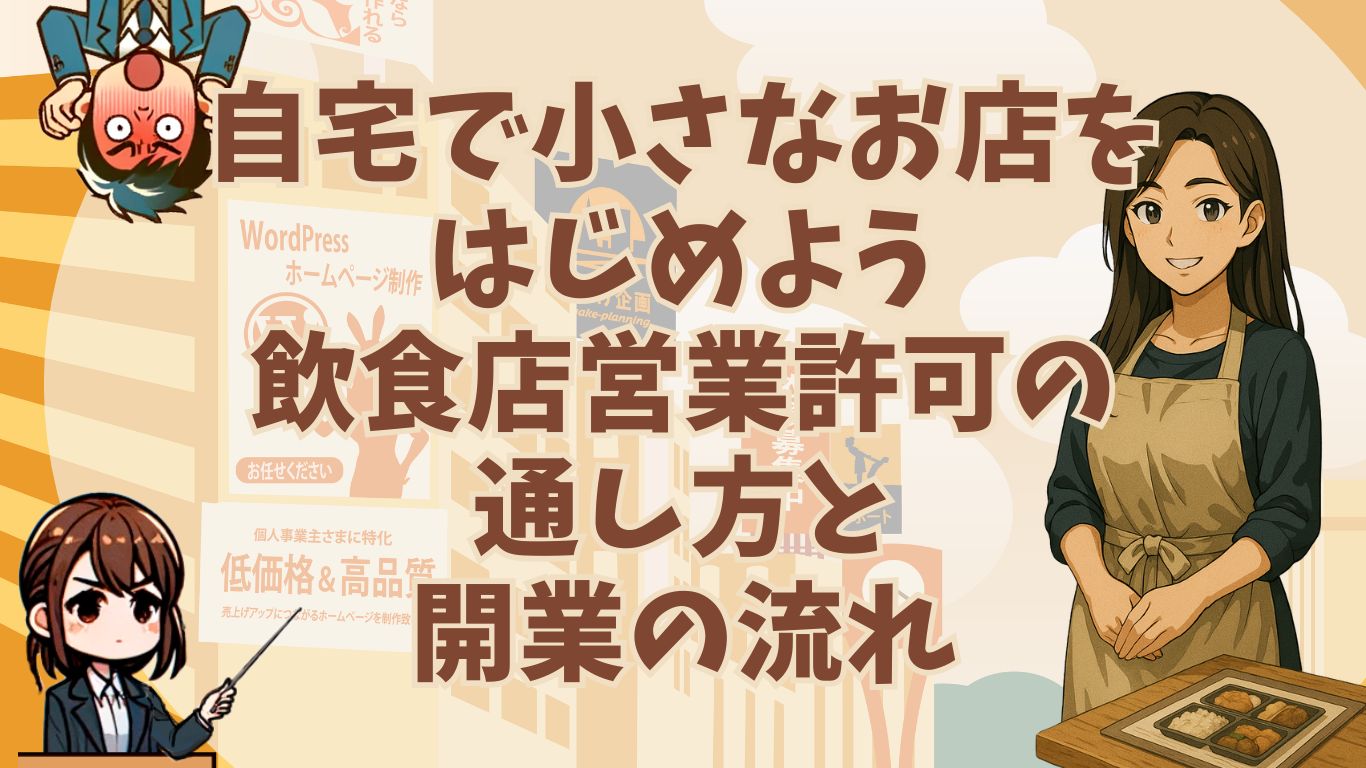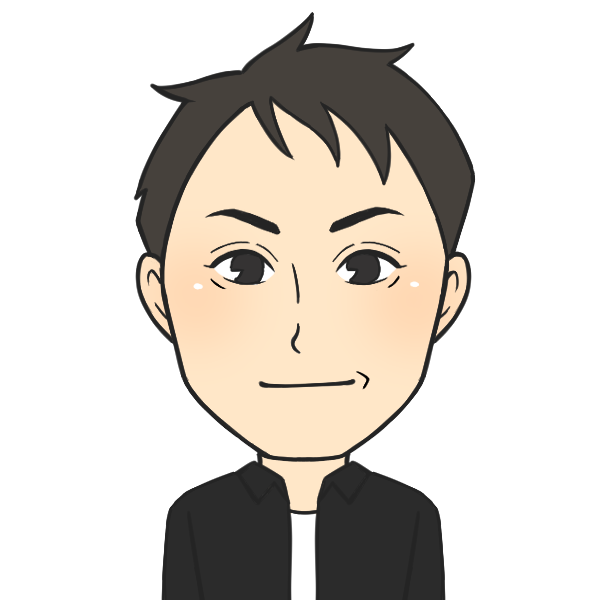甲斐承太郎
甲斐承太郎店舗物件を借りるだけで何百万…だったら、もう実家の一角をお店にしちゃえばいいんじゃない?
自宅で開業すれば初期費用も抑えられるし、家賃もゼロだし…でも、やっぱりリスクとかデメリットもあるのかな?



たしかに、最近は「物件を借りずに自宅で小さく始める飲食店」が増えています。
お金の面では大きなメリットがある一方で、法律・設備・ご近所との関係など、思った以上にハードルも高いのが現実です。
- 自宅を飲食店にするための「法律・許可・届け出」
- 自宅開業に向いている飲食店の種類と特徴
- 必要な設備と費用、開業までのステップ
- 自宅で開業する際の注意点と失敗リスク



結論から言うと、正しい手順で許可を取れば、自宅でも飲食店の営業は可能です。
ただし、家庭用キッチンをそのまま使うことは違法になります。
まずは用途地域と保健所の基準を確認することから始めてください。
第1章:自宅で飲食店は開ける?違法じゃないの?





で、ぶっちゃけ…うちの実家とか自宅をそのままお店にするのって、違法なの?



結論から言うと、「営業許可」を取れば自宅でも開業は可能です。
ただし、すべての自宅がOKとは限りません。
自宅の立地や設備によっては許可が下りないこともあります。
まずは、以下の2つを確認してください。
自宅開業でチェックすべき2つのポイント
| チェック項目 | 内容 | NGの例 |
|---|---|---|
| ① 用途地域 | その場所が「店舗営業」OKか? | 第一種低層住居専用地域などは制限が多い |
| ② 保健所の許可 | キッチンなどが基準を満たしているか? | 家庭用キッチンのままでは不可 |



自宅のキッチンやリビングをそのまま使うのは違法です。
飲食店営業許可を得るには、用途地域の条件クリアと、キッチンの設備改修が必要です。
日本では、都市計画法に基づいて「この地域ではこういう建物が建てられる」というルールが決まっています。
このルールを「用途地域」といいます。
代表的な用途地域と飲食店の可否(簡略表)
| 用途地域 | 飲食店開業の可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | ✕ (原則不可) | 店舗用途は厳しく制限される |
| 第2種低層住居専用地域 | △(要確認) | 小規模店舗なら条件付きで可 |
| 第1種住居地域 | ○ | 小規模飲食店は可能 |
| 準住居・商業地域 | ◎ | 飲食店に適したエリア |



用途地域は市町村の都市計画課やWebマップで確認できます。
計画が固まる前に必ずチェックしてください。
- 自宅でコーヒーや軽食を出すカフェ
- スープやお弁当を手作りして販売する
- 惣菜を量り売りで提供する
飲食店営業許可が必要な業態の例
| 業態 | 許可が必要? | 理由 |
|---|---|---|
| カフェ | 必要 | 調理+提供のため |
| スープ専門店 | 必要 | 加熱・盛り付けあり |
| 惣菜屋 | 必要 | 食材加工がある |
| パン・お菓子販売 | 菓子製造業の許可が必要 | 調理・包装があるため |
| 市販品のみ販売 | 不要(届出のみ) | 加工しない場合に限る |



つまりこういうことです。



自宅での飲食店開業は、用途地域と保健所の許可の2つをクリアすれば可能です。
違法なのは「許可を取らずに始めること」。
まずは自宅の住所が営業OKの地域かを確認し、キッチンを改装できるかを考えるところから始めましょう。
第2章:自宅を飲食店にするには?許可取得までの流れ



なるほど、用途地域も許可も必要なのはわかったけど…実際、どうやって進めればいいの?
何から手をつければいいのかサッパリ!



ご安心を。
以下の手順にそって一つずつ進めれば、自宅での飲食店開業に近づいていけますよ!
自宅飲食店を開業するためのステップ早見表
| ステップ | 内容 | 誰に確認・相談? |
|---|---|---|
| ① 用途地域の確認 | その土地が飲食店営業に適しているか | 市役所(都市計画課) |
| ② 管理規約・契約書の確認 | マンションなどの場合、営業OKか | 管理会社・大家 |
| ③ 保健所に事前相談 | 許可が必要か、必要な設備は? | 所轄の保健所 |
| ④ キッチンの改装計画 | 手洗い・二槽シンクなどの設置 | 内装業者/施工店 |
| ⑤ 営業許可の申請 | 書類提出+施設検査 | 保健所 |
| ⑥ 許可証の交付 | 営業開始へ! | 保健所 |



この中でも、最初にやるべきことは用途地域と保健所への相談です。
「改装してから相談」では手遅れになることもあります。
キッチン設備の要件(保健所基準)
| 設備項目 | 要件例 |
|---|---|
| シンク | 二槽式が基本(調理と洗浄で分ける) |
| 手洗い設備 | ボタン式・非接触が望ましい |
| 床・壁 | 水拭き清掃がしやすい素材・構造 |
| ゴミ箱 | 蓋つき・清掃しやすいもの |
| 冷蔵庫 | 温度計つき、区分管理できる構造 |
| 更衣スペース | 従業員数に応じて必要 |
| トイレ | 調理場と適切な距離、衛生的配置 |
| 換気 | 調理場の換気が十分であること |



「家庭用キッチンのまま」では許可が下りません。
保健所の施設基準に合わせた改装が必要です。
施工前に必ず図面を持参して相談しましょう。
許可取得の流れ
▶ その場所でお店を開いていいかを調べる
- 市役所(都市計画課)で「用途地域図」を確認。
- 第一種低層住居専用地域などは要注意!
▶ どんな許可が必要か?設備は足りてるか?をチェック
- 飲食店営業・菓子製造業など該当業種を確認。
- キッチン改装予定があれば簡単な図面を見せて相談。
▶ 保健所の基準に合わせた設備の整備
- 二槽シンク、手洗い、換気扇、防虫網など必要。
- 必要に応じて上下分離・縦割りなど生活空間の分離も検討。
▶ 計画が固まったら正式に申請へ
- 営業許可申請書、施設図面、身分証明書などを提出。
- 申請手数料(例:札幌市なら16,000円)が必要。
▶ 設備が基準を満たしているか、現地でチェック
- 厨房の広さや衛生状態、動線などを確認されます。
- 不備があれば改善後に再検査。
▶ 条件をクリアすれば、営業が許可される
- 許可証を店内に掲示するのが義務。
- 必要に応じて食品衛生責任者講習の受講も(1日・1万円程度)。
▶ SNSやチラシで告知、近所の人から徐々にファンづくり
- 知り合いに試食会を開いたり、インスタで発信も効果的!
- 最初は無理せず「週3営業」などのベビーステップが◎



よーし、なんか道筋が見えてきたぞ!
まずは保健所に相談して、実家のキッチンでどこまでやれるか確認してみよう!



自宅で飲食店を始めるには、「許可が取れるか」を確認してから改装を始めるのが鉄則です。
必要なのは、大がかりな投資ではなく、順番を間違えない計画力です。
第3章:マンションと一戸建て、それぞれの開業ポイント



ぼくんち、賃貸のマンションなんだけど、ここでお弁当屋さんとかできるのかな?
大家にバレたら怒られそう…。



マンションと一戸建てでは、開業に向いているかどうかが大きく変わります。
それぞれの特徴と注意点を整理してみましょう。
マンションで開業する場合のポイント
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 管理規約 | 商用利用が禁止されていないか必ず確認 |
| 大家の許可 | 賃貸なら口頭ではなく書面で許可を得る |
| 原状回復 | 改装が必要なら、退去時の復元義務がある |
| 住民トラブル | 匂いや騒音、出入りが増えることへの配慮が必要 |
| 設備の制約 | キッチン設備の工事がしづらく、配管工事も困難 |



賃貸マンションでの開業は基本的にハードルが高く、保健所も慎重に審査します。
開業可能な例は「1階のテナント兼住居」など、特殊なケースが多いです。
分譲マンションだからといって自由に使えるわけではありません。
管理規約や理事会の承認が必要なことが多く、開業には住民との合意形成が不可欠です。
一戸建てで開業する場合のポイント
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 用途地域 | 商業・準住居地域ならハードルが低い |
| 店舗スペースの分離 | 生活空間と明確に分ける構造が望ましい |
| 改装の自由度 | 自分の所有物件なら比較的自由に工事できる |
| 駐車スペース | 来客用の駐車スペースもあれば安心 |
| 近隣配慮 | 匂いや騒音、ゴミなどの対策を最初に考える |



住宅を改装して店舗と住まいを分ける方法は、主にこの2つです。
| 【上下分離型】 | 【縦割り型】 |
|---|---|
| 1階が店舗、2階が住居という構成 | 建物を前後で分け、通りに面した部分を店舗にする |
| 建築的に明確に区切られるため、許可も取りやすい | 専用玄関・導線が取りやすく、視覚的にもお店らしい雰囲気が作れる |
| 注意点: 生活音が下に響く/生活感が客から見える可能性あり | 注意点: 構造によっては改装費用がかさむ |



マンションは開業ハードルが高く、原則おすすめしません。
自宅での飲食店を目指すなら、一戸建ての上下分離・縦割り型での計画が現実的です。
とくに地方都市や郊外では、駐車スペースと住宅街の立地を活かした開業戦略が有効です。
第4章:自宅飲食店のリアルな開業資金





物件を借りないなら安くすむって聞いたけど、ぶっちゃけいくらあれば始められるの?



たしかに、物件取得費や家賃が不要になるぶん、自宅開業は費用を大きく抑えることができます。
ただし、改装や設備にはある程度の初期投資が必要です。
ここでは、10坪のカフェを自宅で開業する場合をモデルに、費用の目安を出してみましょう。
10坪の自宅カフェ開業モデル|費用シミュレーション
| 費用項目 | 金額目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 外装工事費 | 10万円 | 看板・外壁・玄関など簡易リフォーム |
| 内装工事費 | 250万円 | カウンター・壁床仕上げ・照明・防音対策 |
| 厨房設備費 | 200万円 | 業務用コンロ・冷蔵庫・換気扇・二槽シンクなど |
| 什器・備品費 | 120万円 | テーブル・椅子・食器・POSレジなど |
| 運転資金(3ヶ月分) | 156万円 | 仕入れ、人件費(ワンオペなら不要)、光熱費など |



節約できるポイントは「家賃」と「敷金・礼金」ですが、改装や厨房機器には100万円単位の支出が想定されます。
自宅が既に店舗として使える状態に近いなら、500万円以下でも開業可能な場合があります。
費用を抑えるコツ
| 方法 | 効果 |
|---|---|
| 中古の厨房機器を活用 | 最大50%以上のコストダウン |
| 自分でDIYできる範囲はやる | 壁紙や家具などで節約可能 |
| 小規模営業でスタート | 週末だけ営業→徐々に拡大 |
| 飲食業向け補助金を活用 | 最大100万円支給される制度も(※地域による) |



やっぱゼロでは始められないけど、店舗を借りるより断然安いし、やってみる価値はありそう!
もし補助金とか使えたら、もっとラクになるよね。



自宅飲食店の開業費用は、「家賃0円」という最大の強みがあります。
ただし、改装や設備は必須投資と考えて、最低でも300〜500万円の予算を確保しておくのが現実的です。
業態や開業スタイルによっては、補助金や中古品活用でさらに抑えることも可能です。
第5章:自宅開業に向いている飲食業態ランキングBEST5



いろいろな業態があるけど、実際どんなお店が自宅で始めやすいの?
ぜんぶやってみたいけど…ムリなくスタートできるのがいいな。



いい質問です!
ここでは、自宅開業に向いている飲食業態をランキング形式で5つ紹介します。
第1位:カフェ


- 許可 :飲食店営業許可
- 特徴 :調理はシンプルでもOK。スイーツやドリンク中心でも成立
- 向いてる人: 接客が好き・SNSで集客したい人
- メリット: 開業事例が豊富で参考にしやすい/設備投資が比較的少ない
💡 近所の主婦やママ友との交流の場に!
外観や内装の工夫で「地域に愛されるお店」に育てることも可能。
第2位:テイクアウト専門店(弁当・パン・ドリンクなど)


- 許可 :飲食店営業・菓子製造業・惣菜製造業(メニューによる)
- 特徴: 客席が不要なので省スペースでOK/駐車場があると便利
- 向いてる人: 短時間営業をしたい人/副業や子育て中の人にも最適
- メリット :初期投資が抑えられ、混雑トラブルも起きにくい
💡 ゴーストキッチン形式にも対応可能!
「UberEats」や「出前館」との連携でエリア外集客も◎
第3位:お弁当屋さん


- 許可 :飲食店営業またはそうざい製造業
- 特徴 :仕出し弁当、日替わり弁当などバリエーション豊富
- 向いてる人 :調理が得意で、時間管理が得意な人
- メリット :高齢者向けや企業向けなど、需要の幅が広い
💡 高齢化が進む地域では固定客がつきやすい!
栄養バランスやボリューム感を工夫するとリピート率UP。
第4位:惣菜屋さん(オカズの量り売り)


- 許可 :そうざい製造業許可
- 特徴: 単身者・共働き家庭に向けた「1品追加」の需要が強い
- 向いてる人: 家庭料理の腕に自信がある人/大量調理が苦でない人
- メリット :店舗面積が狭くても成立/スープや副菜の応用も効く
💡 和食・中華・健康志向などテーマ特化が強い!
「おふくろの味」を売りにしたブランドづくりも◎
第5位:スープ専門店
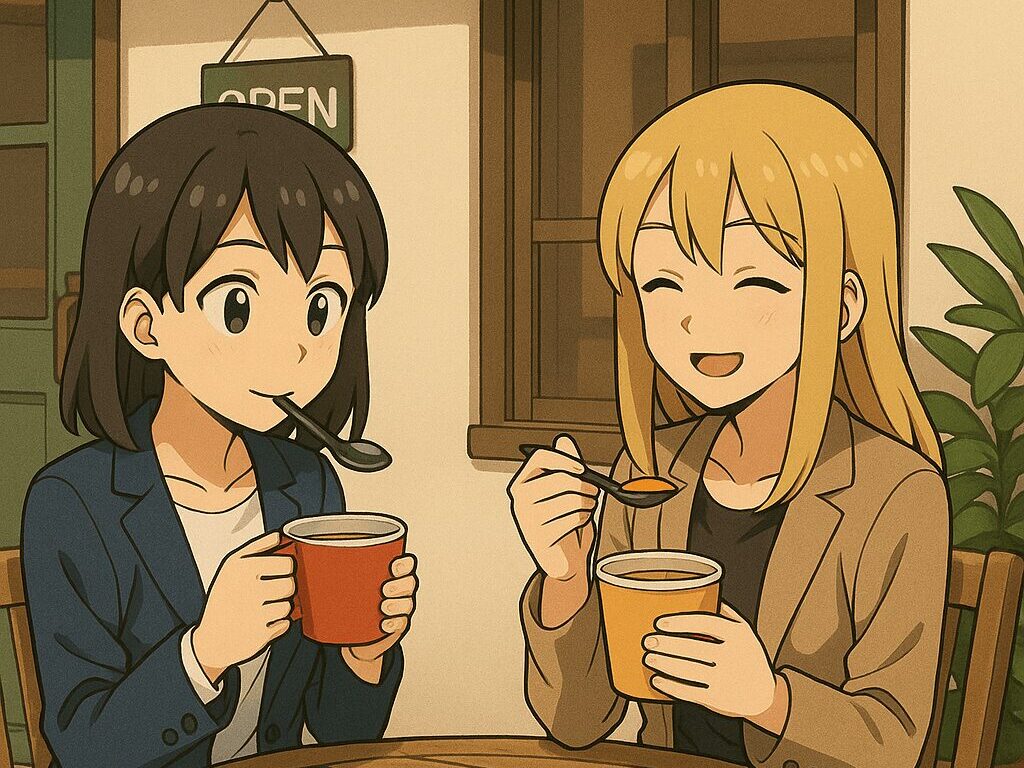
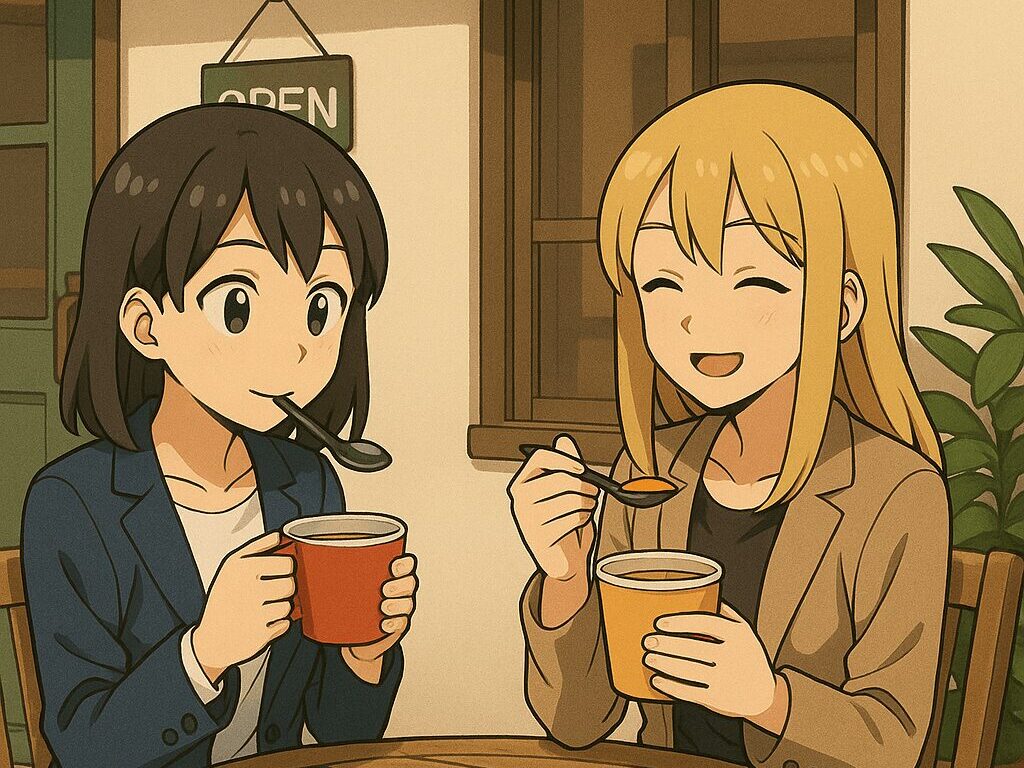
- 許可 :飲食店営業許可またはそうざい製造業
- 特徴 :一汁一菜に近いコンセプト/女性客に人気の業態
- 向いてる人: 野菜や健康食にこだわりたい人/差別化したい人
- メリット :少ない調理工程でも味の変化が出しやすい/冷凍展開も可能
💡 冷製スープや豆乳・ヴィーガン対応で差別化しやすい!



自宅開業に向いているのは、「小規模・短時間・低リスク」で始められる業態です。
初心者はまずカフェやテイクアウトからスタートし、徐々に展開を広げていくのが現実的。
許可の種類や改装コストも業態によって異なるため、やりたいことと資金のバランスを見ながら選びましょう。
第6章:自宅開業で失敗しないための注意点



ここまで読んできたけど…やっぱりちょっと不安もあるよね。
トラブルとか、途中でうまくいかなくなるとか…。



その感覚は正しいです!
自宅で飲食店を始める前に、リスクを知っておくことは成功への第一歩です。
ここでは「よくある失敗パターン」と「それを防ぐポイント」を解説していきます。
よくあるトラブルとその対策
① 近隣トラブル(匂い・騒音・路上駐車など)
| 換気扇からの匂いが広がる | フィルター設置や排気方向の工夫 |
|---|---|
| 調理音・BGMが響く | 営業スペースの防音処理・時間配慮 |
| お客様の車が迷惑になる | 来店手段を事前に案内/駐車場の確保を |
② 衛生管理が甘くて許可取り消しに
| 調理場が清掃されていない | 毎営業後のルーティン清掃を習慣化 |
|---|---|
| ゴミが適切に処理されない | 分別・保管ルールを明確にする |
| 食材管理が曖昧 | 期限・温度管理を徹底する(冷蔵庫に温度計必須) |
③ セキュリティと生活空間の問題
| お客さんが家の奥まで見えてしまう | カーテン・仕切り・入口を分けるなどの工夫 |
|---|---|
| 家族の生活音が聞こえてしまう | 営業時間と生活導線をきっちり分ける |
④ 集客できない/SNS疲れになる
| 知人だけで回している | 地域チラシ・地図アプリ登録・SNS運用の分散化 |
|---|---|
| 投稿がしんどくなってきた | Canvaでテンプレ化/自動投稿ツールの活用 |
| 売上が波に左右される | テイクアウト・冷凍販売・イベント出店で柱を増やす |



自宅開業のリスクは「生活と商売の境界」があいまいになることです。
設備や許可はクリアしていても、近隣配慮・衛生管理・メンタルの継続性が欠けると、営業は続けられません。
「小さく始めて、慣れてから広げる」姿勢が、自宅ビジネス成功の鉄則です。
第7章:自宅で飲食店を開業するのに必要な資格・手続き



許可のことは分かってきたけど、資格とか、書類の提出とかって何が必要なんだ?
なんか忘れてると怖いよね…。



そう、その感覚が大切なのです。
営業許可だけじゃなく、最低限の資格や行政への届出もセットで進めないと、開業できません。
以下の表に、自宅で飲食店を開業する際に必要なものをまとめました。
自宅飲食店に必要な資格・手続きリスト
| 分類 | 内容 | 詳細・注意点 |
|---|---|---|
| 食品衛生責任者 | 必須資格。 1名以上設置が義務 | 調理師・栄養士なら代用可/未取得なら講習で取得(1日・1万円前後) |
| 防火管理者 (必要な場合) | 延床300㎡以上 or ガス設備が大きい場合 | 自宅規模なら不要なことが多いが、火気の使用によっては推奨 |
| 飲食店営業許可 | 保健所で申請 | 必要設備を満たす必要あり。 営業開始10日前までに申請 |
| 開業届(個人事業の開始) | 税務署に提出 | 開業後1ヶ月以内。 提出しないと青色申告や屋号が使えない |
| 青色申告承認申請書 | 帳簿管理が楽&節税できる | 開業届とセットで出すとお得。最大65万円控除 |
- 「資格がなくても開業できる」と勘違いしがち → 食品衛生責任者は必須
- 「開業届はあとでいいや」が税務的に大損になる → 青色申告が使えなくなる
- 「フリーランスだから税金関係は後回し」→ 後から大変になるので最初に整える



資格は「あとから」ではなく「申請前に」取る必要があります。
特に食品衛生責任者の講習は予約制のため、早めの行動が重要です。
また、個人事業の開始届や青色申告書を出すことで、節税や事業継続に有利になります。
第8章:開業までのスケジュール|6ヶ月前からやるべきこと



なるほど…。じゃあ、いつ何をすればいいのかが気になるな。
思い立ったらすぐ始められるもんじゃないよね?



そうなんです。実際は「やることが多くてバタバタ」する人が多いので、開業までのスケジュール感を持つことがとても重要です。
以下に、「6ヶ月前から開業当日まで」の流れを一覧にまとめました。
自宅開業までの流れ(モデルスケジュール)
| 時期 | やること | 補足 |
|---|---|---|
| 半年前 (6ヶ月前) | コンセプト決定・業態選定/家族の同意 | 専用キッチンが必要かも検討 |
| 5ヶ月前 | 近隣調整・間取り確認/用途地域の調査 | 図面を保健所に相談するのも◎ |
| 4ヶ月前 | 保健所に事前相談/設備リストの確認 | 改装が必要なら早めに見積り |
| 3ヶ月前 | 食品衛生責任者の講習申込 | 地域により開催頻度が異なる |
| 2ヶ月前 | 改装開始・営業許可申請 | 同時に開業届も税務署へ提出 |
| 1ヶ月前 | 内装・厨房完成→検査/チラシ・SNS告知 | プレオープン準備もこの時期 |
| 開業直前 | 営業許可交付→営業開始 | 帳簿・レジ・釣り銭など準 備万端に |



許可申請だけでなく、改装や設備購入にも時間がかかるため、
実際には半年ほどの準備期間を見込んでおくのが理想です。
まとめ:自宅飲食店は「低リスク×高ハードル」でも夢は叶



自宅開業は「手軽そうに見えて、実はかなり戦略的な準備が必要」な選択肢ということなんです。
自宅を使って飲食店を開業するという選択肢は、物件取得費や家賃がかからない分、初期費用を大きく抑えられる魅力的な方法です。
しかしその反面、用途地域の制限や、営業許可を取得するための設備基準、近隣との関係や衛生管理など、乗り越えるべきハードルも多く存在します。



自宅での飲食店開業は、法令・設備・地域との調和が取れていれば実現可能です。
ただし、感覚や勢いだけで始めると必ず詰みます。
許可の条件、改装の要件、必要な届出を順序立てて確認し、開業プラン全体を言語化(=事業計画化)することが成功への鍵です。



なるほど~。
とりあえず家でできるかはわかってきたけど…
じゃあ実際「どれくらい売れたら成り立つのか」とか「どれだけ原価がかかるのか」とか…数字の面もちゃんと考えなきゃだよね!