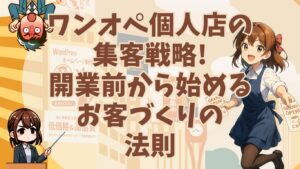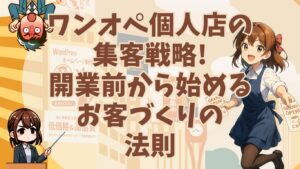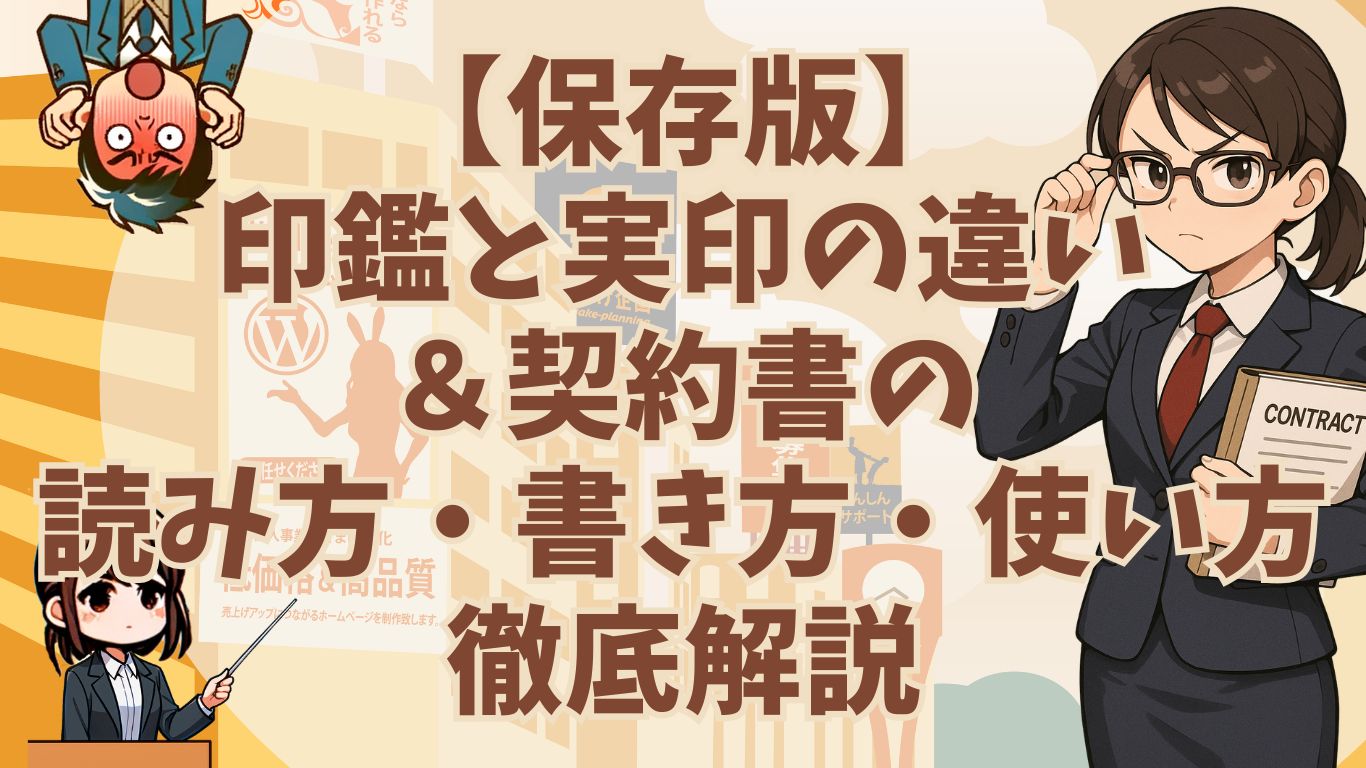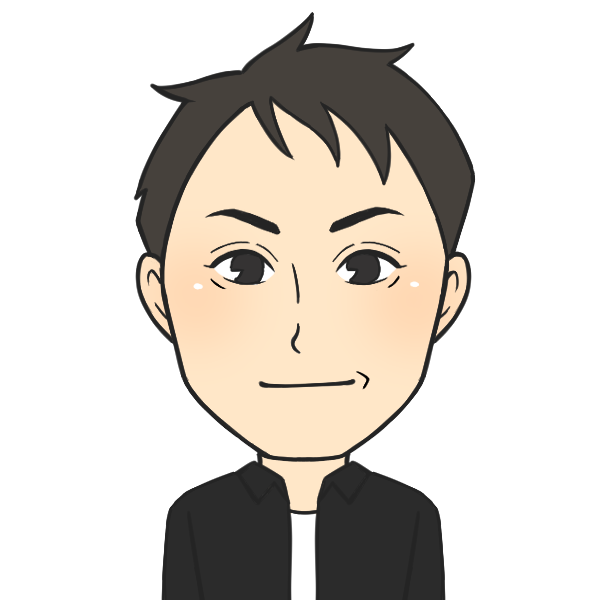甲斐承太郎
甲斐承太郎なんか、いろんな契約書を見せられて「ここにハンコ押してください」って言われるから、いつも何となく押してるんだけど…これって大丈夫なの?



契約書って、ただの紙じゃありません。
たとえば「家を借りる」「店舗を借りる」「取引先と仕入れ契約を結ぶ」──全部、将来のトラブルを防ぐための“約束の記録”なんです。
でもその中身を理解していないまま印鑑を押すと、自分に不利な内容に同意してしまうことも。
- 契約書の仕組みと構成が“流れで理解できる”
- 契約トラブルを防ぐための“読むべきポイント”がつかめる
- 行政書士を味方につける意味がわかる



契約書と印鑑は「取引の安全」を守る道具。
仕組みを理解していれば、怖くありません。
第0章 契約書ってそもそもなに?なんのために?





契約って、ハンコを押して契約書を交わして初めて成立するんだよね?
書類があれば安心って聞いたけど…。



実は、契約は口頭でも成立します。
たとえば「この机、1万円で買います」「いいですよ」――これだけで契約成立です。
でも、口頭契約には決定的な弱点があります。
それは、約束の内容を証明できないことです。
- 「税込み?」「納期は?」で言った言わないになる
- 時間が経つと記憶が曖昧になる
- 第三者(税務署・金融機関)に説明できない
契約書の役割
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 証拠 | 「何を・いくらで・いつまでに」やるかを形に残す |
| 抑止 | お互いが約束を破りにくくなる心理的ブレーキ |
| 信頼 | 書面を交わすことで、安心感が生まれる |



契約書は“契約を成立させる紙”ではなく、
成立した約束を証拠にする紙です。



たとえば飲食店を開業するなら、
物件の賃貸借、内装工事、仕入れ、リース、雇用など、
数十万円〜数百万円の契約が次々に登場します。
ここで契約書を作るのは、相手を疑うためではありません。
後で揉めないための保険。
信頼関係を長く続けるための確認書なんです。



一言でまとめると
第1章 印鑑とハンコの違いとは





この見出し…印鑑とハンコって、同じものじゃないの?



いい質問ですね。
実は「印鑑」とは、押したあとに残る“印影”のことなんです。
たとえば――
あなたが実印のハンコで押した跡(=朱肉の跡)。
その“印影”を法的に登録・証明したものが「印鑑」になります。
| 用語 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 印章 | ハンコそのもの(モノ) | ハンコ屋さんで作るもの |
| 印影 | 押した跡(形) | 宅急便の「ハンコください」 |
| 印鑑 | 役所に登録された印影 | 実印として登録された印影 |



「ハンコください」は印影を求める言葉。
「ハンコ作りたい」は印章を指します。
同じ“ハンコ”でも、文脈で指すものが違うんです。



なるほど!じゃあ“実印”って、その印影を役所で登録したハンコってこと?



その通りです。
実印とは、市区町村に登録された印章で、印鑑証明が取れるハンコのことです。
つまり「本人が確かに押した」と法的に証明できる唯一の印章です。



うわ…そんなに責任が重いのか。
じゃあ、事業を始めるときって、どんなハンコを用意すればいいの?



いい質問です。
個人として使うハンコと、事業者として使うハンコは別です。
| 名称 | 用途 | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 個人向け ハンコ | 実印 | 契約・届出など重要書類 | 市区町村に登録して使う |
| 銀行印 | 口座開設・金融取引 | 銀行に届け出て使用 | |
| 認印 | 日常の確認用 | 普段使い。安価でOK | |
| 事業者向け ハンコ | 代表者印(丸印) | 契約書・役所提出書類 | 丸形(直径18mm前後) |
| 会社印(角印) | 請求書・領収書など社外書類 | 四角形 | |
| 割印 | 書類の綴じ合わせ | 縦長が多い |
第2章 契約書の種類



契約書といっても携帯電話の契約書もあるし、車を買う契約書もあったな~…
飲食店を始めるときって、どんな契約書を使うの?



まずは契約書について理解を深めましょう。
契約書には大きく分けて「典型契約」と「非典型契約」の2種類があります。
| 典型契約 | 非典型契約 |
|---|---|
| 民法で定義あり | 民法で定義なし |
| ルールがすでに法律で決まっている契約 | 自由に内容を決めてよい契約 |



飲食店経営で関わるのは、実は両方。
次の表を見るとイメージがつかみやすいです。
| 契約書の種類 | 内容 | 契約区分 | 例 |
|---|---|---|---|
| 賃貸借契約書 | 店舗物件を借りる | 典型契約 | 家主とテナント間の賃貸借 |
| 工事請負契約書 | 内装・改装などの依頼 | 典型契約 | 内装業者・設備業者との契約 |
| 売買契約書 | モノの売買 | 典型契約 | 厨房機器、中古什器の購入など |
| 仕入取引契約書 | 材料の継続的な取引 | 非典型契約 | 酒屋・八百屋との取引 |
| 業務委託契約書 | 外部業者に作業を依頼 | 非典型契約 | デザイン・清掃・配送など |
| 雇用契約書 | スタッフ雇用 | 典型契約 | アルバイト契約など |



特に飲食店の開業では、次の3つは必ず確認が必要です。
どれも「あとで揉めやすいポイント」です。
- 賃貸借契約:退去条件と原状回復の範囲
- 工事請負契約:支払い時期と追加費用の扱い
- 仕入契約:価格改定や返品ルールの有無



まとめます。
契約書には法律で決まった型のあるもの(典型)と、自由に作るもの(非典型)がある。
自由な契約ほど、内容を丁寧に書く必要があります。
第3章 契約書の読み方





契約書って、ページ数が多くて読む気がしない…。
どこに何が書いてあるか、まったくわからないんだけど?



契約書は長くても、ほとんどがこの15のパーツでできています。
構造さえわかれば、一気に読みやすくなります。
- 収入印紙
- 契約書の表題
- 前文
- 目的に関する条項
- 権利・義務に関する条項
- 解除に関する条項
- 損害賠償に関する条項
- 誠実協議条項
- 費用負担条項
- 存続条項
- 合意管轄に関する条項
- 後文
- 契約書の作成年月日
- 署名・捺印
- 契印・割印
①収入印紙



印紙ってなんか切手みたいなやつ?
なんか会社の領収書に「200円の印紙貼っておいて」って言われたことあるけど…。



まさにそれです。
収入印紙とは、国に納める税金(印紙税)を“切手のような形”で払うしくみなんです。
印紙税法で定められた“課税文書”を作成したときに貼り付ける必要があります。
印紙税がかかる書類は、全部で20種類あります。
そのうち、日常で最も身近なのが――
第17号文書:「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 商品・サービスなどの売上代金を受け取った証拠として発行する書類 |
| 代表例 | 領収書、レシート、検収書、納品完了書など |
| 課税対象金額 | 5万円を超える受取書から印紙が必要 |
| 印紙税額 (令和5年度以降) | 5万円超〜100万円以下:200円/以降、金額に応じて増加 |
| 印紙の貼り方 | 左上や余白に貼り、押印または割印をして消印する |
| 目的 | 国への税金の納付+金銭授受の証拠を法的に有効化する |



つまり「売上代金を受け取りました」と証明する書類が、課税対象になるわけです。
お店の領収書に200円の印紙を貼るのは、まさにこの第17号文書にあたるからなんです。
- 5万円以下の領収書には印紙不要
- クレジットカード決済・電子領収書は「電子文書」とみなされるため、印紙不要
- 手書き領収書で5万円を超える場合のみ、印紙を貼る



この印紙代って一体誰が払うの?



それは文書の作成者です。
5万円以上の商品を売った場合に受取書=領収書は売主が発行するので売主が印紙代を負担します。
もちろん、共同で作成した場合「連帯」して支払う必要があります。



印紙を貼らなかった場合はどうなるの?



「過怠税(かたいぜい)」を支払わなければなります。
印紙税額の3倍払いのペナルティになります。
②契約書の表題



契約書のタイトル(表題)は、実は“書類の性格”を表しています。
そして、契約書の形式には「差入式」と「連署式」の2種類があります。
どちらの形式かによって、文書の名前や扱いが変わるんですよ。
| 差入式(さしいれしき) | 連署式(れんしょしき) |
|---|---|
| 契約当事者の一方だけが署名・押印し、相手に差し出す形式。 | 契約当事者の双方が署名・押印し、それぞれが同内容の原本を持つ形式。 |
| 片方が「この条件で責任を負います」と約束する場面。 | 双方が合意した内容を記録しておく場面。 |
| 例:納品業者が「この内容で確かに受けました」と出す請書など。 | 例:物件の仮契約、取引条件の取り決めなど。 |
代表的な契約関連文書とその内容
| 文書名 | 形式 | 主な内容・目的 | 使用される場面 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 念書 (ねんしょ) | 差入式 | 一方が相手に対して「今後こうします」と約束する文書。片側だけが署名。 | 例:店舗の退去時に「設備を原状回復して返します」と差し入れる。 | 自分側の責任や義務を明確にしたいとき。証拠として効力あり。 |
| 請書 (うけしょ) | 差入式 | 相手からの注文・依頼を正式に受けたことを証明する文書。 | 例:内装業者が「発注内容を確かにお引き受けします」と返す。 | 注文書とセットで使う。商取引でよく使われる。 |
| 覚書 (おぼえがき) | 連署式 | 双方が合意した内容を簡潔に記録した文書。 | 例:物件の内見後、「契約前に仮押さえする条件」を覚書でまとめる。 | 契約前後の細かな合意事項を補足する。簡易な契約書として機能。 |
| 合意書 (ごういしょ) | 連署式 | 双方の合意が成立したことを正式に記録する文書。 | 例:店舗工事の追加費用について双方が再度同意する。 | 契約の変更・追加事項の確認に使われる。 |
| 確認書 (かくにんしょ) | 連署式 | 既に話し合い済みの内容を「確認した事実」として残す文書。 | 例:納期・支払日などを再確認した内容を文書化。 | 合意の再確認や、認識ズレの防止に効果的。 |



差入式ってのはチェックマーク入れないと進めないネット通販あるあるのヤツだな!



おおむね正解です。



具体例として
第3条(売買価格)
本件商品の売買価格は、甲乙協議のうえで、別途、個別契約において定めるものとする。
として、別途「覚書」を用意する場合などがあります。
③前文
○○株式会社(以下「甲」という)と△△株式会社(以下「乙」という)とは、甲の製造する商品の売買に関し、次のとおり契約を締結する。



甲乙って、どっちがどっち? “甲乙つけがたい”ってこと?



はは、それは名言ですね。
でも契約書では単なる区別です。
そして、上下関係ではなく、便宜上の呼び分けです。
| 呼び名 | 意味 | 例(飲食店) |
|---|---|---|
| 甲 | 契約を申し込む・依頼する側 | 店主(依頼者) |
| 乙 | 契約を受ける・請け負う側 | 内装業者・仕入先 |
④目的に関する条項
第1条(目 的)
乙は甲より次の製品(以下「本件商品」という)を購入し、これを乙の顧客に販売するものとする。
1.○○○○○2.△△△△△
第2条(個別契約の成立)
1. 甲乙間の本件商品に関する個々の売買契約(以下「個別契約」という) は、乙の申込に対し甲が承諾したときに甲乙間に成立するものとする。
2. 前項の申込と承諾は、それぞれ注文書および請書をもって行い、甲が請書を発送した時点で個別契約が成立するものとする。
3. 甲が、前項の注文書が到達後、○日以内に異議を申し出ない場合は、乙の注文書の内容を承諾したものとみなす。
4. 甲および乙は、個別契約において、甲乙協議のうえ、本契約と異なる定めをすることができるものとし、その場合には個別契約が本契約に優先するものとする。第3条(売買価格)
本件商品の売買価格は、甲乙協議のうえで、別途、個別契約において定めるものとする。第4条(納品・検査方法)
- 乙は、本件商品引渡後○日以内にこれを検査し、本件商品の数量及び品質等に問題があった場合には、甲に申し出るものとする。
2. 甲は、前項の申し出があった場合、甲の判断により、代替品や不足品の納入、修理、過剰納品の引取り等の適切な対応を行うものとする。



第一条には、だいたい「契約の目的」が書かれています。
つまり「この契約は何のために結ぶのか」。
ここを読むと、契約全体の方向性がつかめます。
⑤権利・義務に関する条項
第XX条 (本商品の引渡し等)
1 甲は、 ○○年○月○日までに、乙に対し、本商品を引き渡すものとする。なお、本商品引渡に伴う費用は甲の負担とする。
2 本商品の所有権は、前項の引渡しをもって、甲から乙に移転するものとする。



ここが一番大事。
「この契約によって、相手に何を要求でき、自分は何をしなければならないのか」が書かれています。
- 支払期日
- 利息
- 弁済方法(振込・手渡しなど)



曖昧なままサインするとトラブルのもと。
読み飛ばさないでくださいね。
⑥解除に関する条項
第XX条(契約解除)
1. 甲または乙は、相手方が前条1項2号ないし9号の一に該当したときは何らの通知催告を要せず、直ちに本契約および個別契約の全部または一部を解除することができるものとする。
2. 相手方が本契約または個別契約の条項に違反し、相当の期間を定めて履行を催告したにもかかわらず、当該期間内に履行しないときも前項と同様とする。
3. 前二項に基づいて本契約が解除されたときは、帰責事由の存する当事者は他の当事者に対し、本契約の解除により他の当事者が被った損害を賠償するものとする。



契約を「なかったことにする」ための条件です。
たとえば「お弁当10食を5月31日までに納品できなければ契約を解除できる」といった明確な取り決めを事前に書いておけば、
催告(=相手に改めて通知する手続き)を省ける場合もあります。
⑦損害賠償に関する条項
第XX条(損害賠償)
甲または乙が本契約または個別契約の条項に違反し、他の当事者に損害を与えたときは、違反した当事者は、損害を被った当事者に対し、その損害を賠賞するものとする。



“損害賠償”って言葉いろんなところでいろんな人が言うよね。
肩がぶつかっただけで損害賠償って払わないとダメなの?



いい質問ですね。
実は「損害賠償」とは、相手に損害(=損したこと)を与えたときに、その分をお金で補うことをいいます。
ただし、なんでもかんでも「損害賠償!」というわけではありません。
法律上は3つの条件が揃ったときに初めて、損害賠償の責任が生まれます。
損害賠償が成立する3つの条件
| 条件 | 内容 | 例(飲食店の場合) |
|---|---|---|
| ① 損害が発生した | 相手に何らかの損が生じた | 店舗工事で設備を壊した |
| ② 違法または契約違反があった | 約束や法令を破った | 契約どおりの納期を守らなかった |
| ③ 因果関係がある | その損害が自分の行為によって起きた | 工事のミスで営業開始が遅れた |



契約書の中では、この損害賠償をあらかじめ「どの範囲まで・いくらまで」と決めておくことができます。
たとえば──
「契約違反があった場合、契約金額の10%を損害賠償金として支払う」
というような条項です。これを損害賠償予定条項といいます。
⑧誠実協議条項
第XX条(協議事項)
本契約に定めがない事項が生じたときや、本契約条項の解釈に疑義が生じたときは、相互に誠意をもって協議・解決する。



これは“トラブル時の最後の砦”。
書いてある内容が決まっていない場合は「誠意をもって話し合いましょう」と示す条項です。
一見飾りのようでも、紛争防止に役立ちます。
その他の条項
第XX条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、調印の日より○年間とし、期間満了○カ月前までに、いずれの当事者からも書面による別段の申出がないときは、さらに○年間延長されるものとし、以後も同様とする。
2. 本契約が終結または解除のときに、すでに成立した個別契約があるときは、本契約は、当該個別契約の履行が完了するまで、当該個別契約の履行の目的のために、なお効力を有するものとする。第XX条(協議)
本契約に定めなき事頃または解釈に疑義を生じた事項については、甲乙協議のうえ解決するものとする。第XX条(効力の存続)
甲乙は、本契約が期間満了または契約解除等により終了した場合であっても、本契約終了日から起算して○年間は、第10条(製造物責任)、第11条(第三者の知的財産権の侵害)、第12条(保証)及び第15条(秘密保持)の義務を負担するものとする。第XX条(裁判管轄)
甲乙は、本契約および個別契約に関して裁判上の紛争が生じたときには、甲の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。以上、本契約の成立を証するため、本書二通を作成し、署名捺印の上、各自一通を保有する。
令和○○年○月○日
(甲) 住所 北海道札幌市○○区○○条○丁目○番地
会社名 ○○株式会社
氏名 ○○ ○○ 印
(乙) 住所 東京都○○区△△町△丁目△番地
会社名 △△株式会社
氏名 △△ △△ 印
| 条項 | 内容 | チェックポイント |
|---|---|---|
| ⑨ 費用負担条項 | 契約書作成費や印紙代、交通費などをどちらが負担するか | 小さい金額でも明確に |
| ⑩ 存続条項 | 契約終了後も有効な項目(守秘義務など) | 「契約後も守る約束」があるか確認 |
| ⑪ 合意管轄条項 | トラブル時にどこの裁判所で争うか | 「相手の地元裁判所」になっていないか注意 |
| ⑫ 後文 | 契約書の通数・保管方法 | 原本は双方で1通ずつ持つ |
| ⑬ 作成年月日 | 契約が成立した日付 | サイン日と同じか確認 |
| ⑭ 署名・捺印 | 契約当事者のサイン | 印鑑の種類に注意(認印でOKか、実印か) |
| ⑮ 契印・割印 | 書類が複数枚ある場合に押す印 | 契約書が差し替えられないようにする |



こうしてみると、契約書は“約束の流れを順番に書いた紙”だと分かります。
難しく感じるのは、形式に圧倒されるから。
仕組みが見えれば、もう怖くありません。



この文言もよく見るね。



これは“もし裁判になったらどこの裁判所で争うか”を決めておく条項です。
これを合意管轄条項(ごういかんかつじょうこう)といいます。
実は、契約書って多くの場合、作った側が有利になるように作られています。
そのため、裁判の場所(管轄裁判所)も相手の会社の所在地に設定されていることが多いんです。



つまり、契約書を相手任せにすると、不利な条件をそのまま受け入れてしまう危険があるんです。
「内容は相手が作ってくれたから安心」ではなく、自分に不利な点がないか必ず確認することが大切です。
補足として、行政書士などの専門家にリーガルチェックを依頼すれば、
このような見落としがちな不利条項を事前に指摘してもらえます。
第5章 契約の約束を破ったらどうなる?





もし契約書の約束を守れなかったら、どうなるの?
たとえば支払いが遅れたり、納期が間に合わなかったり…。



それは法律的には「債務不履行(さいむふりこう)」といいます。
つまり“約束を守らなかった状態”のことですね。
民法では、債務不履行は3つのパターンに分かれます。
債務不履行の3つのタイプ
| 種類 | 意味 | 例(飲食店のケース) |
|---|---|---|
| 履行遅滞 | 約束を果たすのが遅れた | 厨房機器の納品が遅れた、家賃の支払いが遅れた |
| 履行不能 | そもそも実行できなくなった | 火災で商品が納品できなくなった |
| 不完全履行 | 内容が不十分だった | 注文数よりも少ない食材が届いた |



債務不履行になると、相手方(もう一方の当事者)は次の3つの手段を取ることができます。
相手方が取れる3つの対応
| 手段 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 履行の請求 | 「約束どおりにやってください」と要求できる | 支払い・納品などを催促できる |
| 契約の解除 | 契約そのものをなかったことにできる | 条件を満たせば一方的に解除可能 |
| 損害賠償の請求 | 不履行によって発生した損害をお金で補う | 修理費・再仕入れ・営業損失など |



契約を解除しただけでは損害は回復しません。
たとえば工事を途中で放棄された場合、
契約解除+損害賠償請求(再工事費用の補償など)をセットで行うこともあります。



つまり、契約書は「トラブルが起きたときの地図」でもあるんです。
解除や賠償の条項を確認しておけば、
万一の時にどう動くかを事前に決めておけるということですね。
第6章 契約書の作り方



契約書って、自分で作ってもいいの?
ネットのテンプレートをコピペすれば大丈夫?



もちろん、自分で作っても問題ありません。
契約書には「この形式でなければ無効」という決まりはないんです。
ただし――テンプレートをそのまま使うのは危険です。
契約の内容に合っていないと、逆にトラブルの原因になります。
契約書を作るときの3ステップ
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 内容を整理する | 何を・誰と・いくらで・いつまでに、を明確に | 契約の目的と責任の範囲を先に紙に書き出す |
| ② テンプレートを選ぶ | できるだけ業種に近いものを選ぶ | 例:工事請負契約/賃貸借契約/業務委託契約など |
| ③ 内容を修正する | 自分の取引条件に合わせてカスタマイズ | 支払い時期・解約条件・損害賠償の範囲などを実態に合わせる |
よくある失敗例
| 失敗パターン | 何が問題? | 対策 |
|---|---|---|
| ネットの雛形をそのまま使う | 実際の取引内容とズレている | 必ず金額・納期・責任範囲を修正する |
| 相手のひな形に全部従う | 不利な条件が含まれている場合あり | 解除・支払い・損害賠償の条項をチェック |
| サインを急かされる | 内容を理解しないまま押印 | 一晩置いて冷静に読み返す習慣をつける |



開業したての頃は、相手の提示した契約書をそのまま受け取ってしまいがちです。
でも、契約書は交渉のスタート地点。
不利な内容なら修正を提案してOKです。
第7章 契約書と印鑑を味方にする心得



契約書やハンコの大切さはわかったけど、
やっぱりいざ契約ってなると、自信がないなぁ…。
「これで本当に大丈夫なのかな」って不安になる。



それはごく自然なことです。
契約は“信頼”と“責任”の証ですから、慎重になるのは正しい姿勢ですよ。
そして――そういう時こそ、専門家を味方につけるタイミングです。
契約を安全に進めるための心得
| 心得 | 内容 | 行動のヒント |
|---|---|---|
| 1. 署名・押印は理解してから | 「急いでサイン」は一番危険。 | わからない文言は必ず確認する。即サインしない。 |
| 2. 契約内容は“中身”を重視 | 体裁より「何を」「どう守るか」。 | テンプレートの言葉に惑わされない。 |
| 3. 書面で残す習慣を持つ | 口約束は誤解のもと。 | メールや覚書でもOK。必ず記録を残す。 |
| 4. 不安を感じたら専門家に相談 | 自力判断に限界を感じたらすぐ相談。 | 行政書士や弁護士に早めにアドバイスをもらう。 |



契約の現場では、行政書士があなたの“防波堤”になります。
契約書の作成やリーガルチェックだけでなく、
契約の席に同席して、相手方に不利な契約を結ばないようサポートすることもできます。
不利な条項を見抜いたり、修正案をその場で提案したり──
それが行政書士の得意分野です。
あなたが事業に集中できるよう、法律の部分を支えるのが私たちの役割です。



契約や印鑑は“敵”ではなく、正しく使えばあなたを守る“盾”。
自信がないときは無理せず、行政書士を味方にしてください。
一緒に契約の場を乗り切れば、その経験があなた自身の力になります。



遠藤さん!
俺の金~!俺の~~!!
あ~!!
まとめ



こうして見てきましたが、結局のところ契約書って「難しい法律文書」じゃないんですよね。
要は、自分と相手の約束を紙に残した確認書なんです。
形式よりも中身。
「誰と・何を・いくらで・いつまでに・守れなかったらどうするか」
この5つが書かれていれば、それが立派な契約書です。



そして、その証として押すのが印鑑。
実印や認印といったハンコは“責任の印”。
理解して押すハンコこそ、あなたの信頼を守ってくれます。



よし、契約の基本はつかめた!
次は「どうやってお客さんと信頼を築いていくか」だね。
開店前から始められる集客のコツ──
次の記事『ワンオペ個人店の集客戦略!開業前から始めるお客づくりの法則』へ続きます。