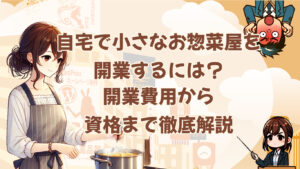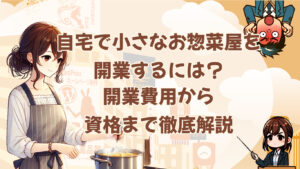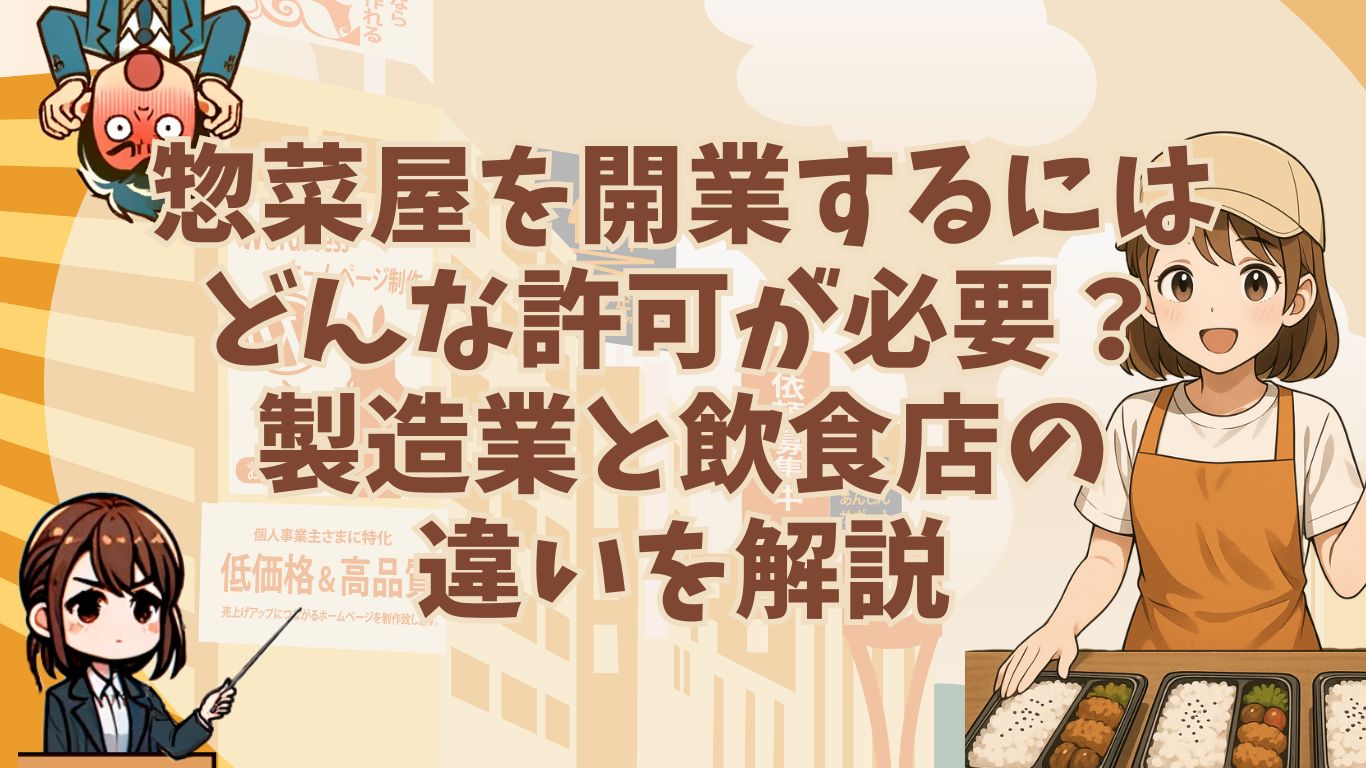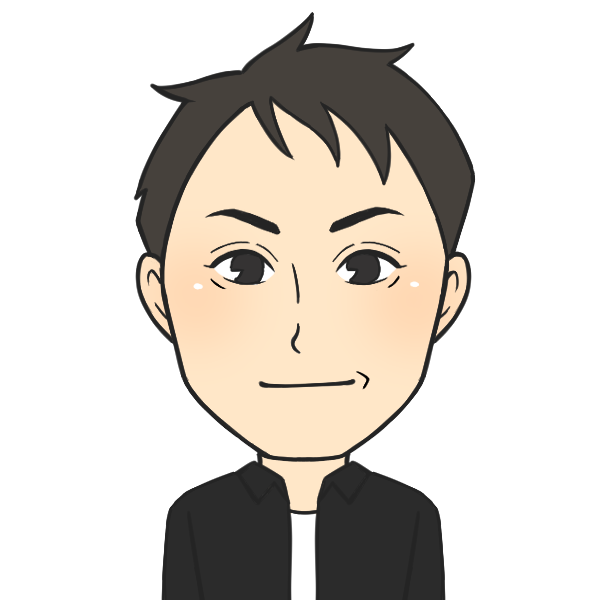甲斐承太郎
甲斐承太郎最近、駅前とか商店街でお惣菜屋さんをよく見かけるんだよね。
テイクアウトできて便利だし、ちょっと憧れちゃうなぁ。
僕もいつか、自分で小さな惣菜屋を開いてみたい!
でも……始めるにはやっぱり「そうざい製造業許可」ってやつが必要なのかな?



うん、それはいいところに目をつけたね。
最近は共働き家庭の増加で、手軽に買えるお惣菜のニーズが急増してます。
開業アイデアとしてはとても有望です。
ただし、「惣菜屋=製造業許可が必須」とは限りません。
重要なのは、どこでどうやって提供するか。
まずは、その違いをきちんと整理していきましょう。
- 惣菜屋を始めるために必要な営業許可の種類と違いがわかる
- そうざい製造業許可取得に必要な手順・設備・費用の具体的なイメージが持てる
- 売れる惣菜屋を作るための販売戦略と営業スタイルがわかる



惣菜屋を始めるには、
その場で盛り付けて渡すだけ → 飲食店営業許可で可
パック詰めして販売・配送 → そうざい製造業許可が必要
つまり、「提供の仕方」によって必要な許可が変わるのです。
第1章|そもそも「そうざい製造業許可」とは?





でもさ、「惣菜屋」って言っても、なんか漠然としてて……
そうざい製造業許可って、いったい何が対象になるの?
唐揚げとかポテトサラダとかも惣菜ってことでいいのかな?



「そうざい製造業許可」とは、
食品衛生法に基づく“製造業許可”のひとつで、
煮物・焼き物・揚げ物・和え物・サラダ・弁当など、
いわゆる“総菜類”を製造・包装・販売するために必要な営業許可なんだ。
- 唐揚げ・焼き魚・煮物などのおかず類
- ポテトサラダやマカロニサラダなどの非加熱副菜
- 弁当・おにぎり・サンドイッチ
- ショーケースで冷蔵・包装して売る形式のテイクアウト総菜



あっ、じゃあ例えば「お弁当屋さん」も該当する?



はい、それも「そうざい製造業」に含まれます。
ただし、お弁当をその場で作って、すぐ手渡しするだけなら、
飲食店営業許可でも対応可能なケースもあります。
- 製造してパック詰めして置いておく → 製造業許可が必要
- 注文受けてすぐに盛り付けて手渡す → 飲食店営業許可でOKなことも
補足:こんな業態も「そうざい製造業」になる
| 業態 | 許可が必要な可能性 |
|---|---|
| 真空パックで販売する惣菜セット | 必要(製造+包装) |
| 通販で常温発送するレトルト惣菜 | 必要(長期保存対応) |
| 移動販売車で惣菜を販売 | 販売方法と保管に応じて、そうざい製造業許可が必要になることも |
第2章|飲食店営業とそうざい製造業の違いとは?



うーん……
結局「飲食店営業許可」と「そうざい製造業許可」って、どう違うの?
どっちが必要か、どう判断すればいいのかイマイチわかんないな。



それはね、「その場で食べさせるか」「後で食べさせるか」が分かれ目です。
つまり、“喫食タイミング”と“提供方法”が判断基準になるんだよ。



わかりやすくまとめると、こうなります
許可の違いを比べてみよう
| 比較項目 | 飲食店営業許可 | そうざい製造業許可 |
|---|---|---|
| 主な対象 | その場で調理・盛り付けし、店内または持ち帰りで提供 | 加熱・味付け・包装し、冷蔵ショーケース等で販売 |
| 提供方法 | すぐに渡して喫食させる(弁当・イートイン) | 製造後にパック詰めして保存・販売 |
| 喫食タイミング | 原則、すぐに食べる前提 | いつ食べるかわからない(時間経過あり) |
| 設備基準 | 比較的緩やか(厨房+接客スペース) | より厳格(製造室の区画・温度管理などが必要) |
| 食中毒リスク対策 | 調理後すぐの提供前提=比較的低リスク | 時間経過・保存前提=高リスク=厳しい衛生管理 |



なるほど、そうか!
「すぐ食べるか、後で食べるか」っていう考え方はめっちゃ分かりやすい!



その通り。
だから同じ「唐揚げ」でも――
・その場で揚げてすぐに手渡す
→ 飲食店営業許可
・揚げた唐揚げをパック詰めして冷蔵ショーケースに並べる
→ そうざい製造業許可
というように、同じメニューでも提供方法次第で許可が変わります。



さらに注意しておきたいのは、「テイクアウト」や「EC販売」「マルシェ販売」の場合です。
包装して持ち帰らせる形態は製造業扱いになることが多いから、飲食店営業だけでは足りないケースもあります。
- 店頭で調理し、その場で盛り付けて提供するだけの惣菜屋
- 注文を受けてその場でお弁当を詰めて渡すだけの持ち帰り専門店(保健所判断による)
補足:飲食店のテイクアウト販売について





でもさ……
たとえば普通の飲食店でさ、出前とかテイクアウトやってるところあるじゃん?
あれって、「製造業」にはならないの??



なりません。
2021年の食品衛生法改正で明確になった通り、
飲食店営業許可を持っていれば、調理したものをテイクアウトや配達(出前)で提供することもOKです。



ただし条件があります。
あくまで「その場で調理して、そのまま渡す・届ける」形式であること。
パック詰めして長期保存や流通を前提とした製造販売になると、
それはそうざい製造業許可が必要になる可能性がある。
ポイント整理:飲食店のテイクアウト・出前はOK!
| 提供形態 | 必要な許可 | 説明 |
|---|---|---|
| 店内で調理 → パック詰めしてすぐ渡す (弁当) | 飲食店営業許可でOK | すぐに喫食される前提なので許可内で対応可 |
| 店内で調理 → 自店で配達 (出前・ウーバー) | 飲食店営業許可でOK | 出前・配達も許可の範囲内 |
| 製造 → 冷蔵・冷凍してストック → マルシェ販売 | 製造業許可が必要 | 保存・外販は製造扱いになる |



つまり、“その場で作ってすぐ出す”が飲食店の範囲。
保存・包装して時間を置くような形式は製造業の範囲になるんです。
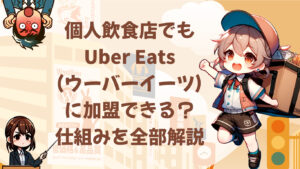
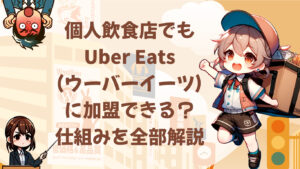
第3章|惣菜屋開業に必要な許可と資格は?



じゃあさ、実際に惣菜屋を開業するには、
どんな許可と資格を持っていればいいの?
調理師免許とかも必要なのかな?



結論から言えば、国家資格(調理師免許)は不要です。
ただし、営業許可を取るには最低限「食品衛生責任者」の資格が必要になります。
惣菜屋に必要な「2つの必須要件」
| 必要なもの | 内容と取得方法 |
|---|---|
| 営業許可 | → 主に「そうざい製造業許可」または「飲食店営業許可」(どちらか/両方) |
| 食品衛生責任者資格 | → 調理師免許がなくても、1日の講習で取得可(各都道府県で定期開催・費用1万円前後) |



ちなみに、調理師・栄養士・製菓衛生師などの有資格者であれば、
講習を受けずに食品衛生責任者になれる場合もあるよ。
でも、ほとんどの人は講習受講で問題なし!
その他、開業前に必要な手続き
| 手続き内容 | 補足 |
|---|---|
| 保健所への営業許可申請 | 設備・レイアウトが整ってから申請する |
| 開業届(税務署) | 個人事業主としての届出(開業時) |
| 消費税関連の届出(売上次第) | インボイス制度への対応なども要検討 |
| 食品表示法の確認 | 原材料やアレルゲン表示が必要な場合あり |



なるほど〜、
資格っていっても国家資格じゃなくて、ちゃんとルールに沿えば誰でも始められるってことか!



そう、それが惣菜屋の魅力のひとつでもある。
ただし、自己流では通用しない業界でもあるから、きちんとルールを押さえてスタートするのが重要だよ。
第4章|そうざい製造業許可の取り方と流れ





じゃあさ、いざ惣菜屋を始めるぞ!って決めたら、
そうざい製造業許可ってどうやって取るの?
いきなり申請しに保健所行けばいいの?



おっと、ちょっと待ってくださいね。
いきなり申請しに行くのはNG。
まずは、保健所への事前相談から始めるのが基本中の基本になります。
惣菜製造業許可を取る6ステップ
営業地を管轄する保健所へ連絡し、業種と物件の適合を確認
基準に合った厨房・製造スペース・設備を用意(区画・2槽シンク等)
資格がなければ各都道府県の講習を受けて取得(1日でOK)
平面図・申請書・設備表などを保健所の指示に従って準備
書類提出後に施設の実地検査が行われる(立ち会いあり)
問題なければ1〜2週間程度で許可証が発行され営業可能に!



とくに重要なのはSTEP1とSTEP2。
勝手に設備を整えてから申請すると、「ここ作り直してください」って言われるリスクが高い。



つまり、「図面ができる前」に保健所に相談するのが正解です。
電話でもOK。
図面を持って窓口に行くのもOKです。
- 営業許可申請書(保健所指定様式)
- 施設の平面図(手書きでもOK)
- 食品衛生責任者の資格証明書
- 営業所の使用権限を示す書類(賃貸契約書など)
- その他、保健所が指定する書類



なるほど……
まずは“相談がスタートライン”ってわけだね!
自己流で始めなくて良かった〜。



開業って、夢や情熱が先行しがちだけど、
こういう現実的なステップをきちんと踏むことが成功の近道なんだ。
第5章|そうざい製造業許可に必要な設備と施設基準



設備ってさ、どのくらい整えなきゃダメなの?
家庭のキッチンじゃさすがに無理だよね?



その通りです。
「そうざい製造業」は製造業扱いなので、
家庭用の調理場とはまったく別物と考えてください。



保健所の審査で最も見られるのが、“食品に菌が付かないための構造”なんだ。
たとえば、水回りや動線、洗浄スペースなどがちゃんと区分けされているかどうかが重要になる。
そうざい製造業の施設基準まとめ(札幌市の公式資料に準拠)
| 区分 | 基準内容(札幌市の施設基準に準拠) |
|---|---|
| 調理室(製造室) | 独立した部屋。 出入口・窓には防虫網・防鼠構造。壁・床は清掃しやすく耐水性あるもの。 |
| 作業台・設備 | 作業台は清掃・消毒が容易な材質(例:ステンレス)。器具も衛生的に保管。 |
| 洗浄設備(シンク) | 二槽式以上の流し(洗い・すすぎ分離)または一槽+消毒槽。 排水が衛生的に処理できること。 |
| 手洗い設備 | 調理従事者専用の手洗い設備が必要。 消毒用せっけん・ペーパータオルを備える。 |
| 冷蔵・冷凍設備 | 原材料・製品を適切に保管できる容量の冷蔵庫。 温度管理ができること。温度計付きが望ましい。 |
| 換気・照明 | 湿気や臭気がこもらないよう換気扇などを設置。 作業に支障のない照度(例:100ルクス以上) |
| 更衣室・トイレ | 更衣室またはロッカーを設置。 トイレは調理室と隔離し、手洗い場も併設が望ましい。 |
| 害虫・ねずみ防止措置 | 出入口に防虫網、排水口に防虫トラップ、照明に防虫灯の使用推奨。 |
| 衛生管理 | 使用後の器具・ふきん類は洗浄・消毒を実施。 記録を残すなど、HACCPに基づいた管理が望ましい。 |



うわっ、思ったより本格的だ……
これ、やっぱり居抜き物件とかを使う方が楽なのかな?



そうですね。
飲食店や仕出し屋の元テナント物件(保健所の実績あり)を活用できると、改装コストを抑えられるうえ、許可取得のハードルも下がります。
🧠 補足:イートイン併設や複合型にする場合は要注意!



要するに、惣菜を売るなら「工場的なつくり」も求められるということです。
衛生と保存を重視した設備が、製造業のポイントになります。
第6章|許可取得にかかる費用とランニングコスト





ところで……
設備もいろいろ必要そうだけど、実際にいくらくらいかかるの?
開業費用ってやっぱり高いのかな?



「製造業許可」は飲食店より設備基準が厳しい分、初期費用もやや高めになる傾向があります。
惣菜製造業の初期費用の目安(10坪前後のモデルケース)
| 項目 | 目安金額(例) | 備考 |
|---|---|---|
| 保健所への許可申請料 | 約18,000円 | 札幌市の例(地域により差あり) |
| 食品衛生責任者講習費 | 約10,000円 | 1日講習で取得可能 |
第7章|売れる惣菜屋をつくる!営業スタイルと販売戦略



ところで……
ちゃんと許可とって惣菜屋さんのお店つくっても、売れなかったら意味ないじゃん?
実際、どんな売り方があるの?



いいところに気づきましたね。
惣菜屋は売り方・スタイルの工夫で、利益率も固定客も大きく変わってきます。
惣菜屋の代表的な営業スタイルと特徴
| スタイル | 特徴とポイント |
|---|---|
| テイクアウト専門店 | 駅近・住宅街で展開しやすい。主婦層・働く世代がメインターゲット。 夕方以降の時間帯に集中しやすい。 |
| 移動販売(キッチンカー型) | イベント・スーパー前などで柔軟に展開。 仕込み場(許可施設)+販売車両の組み合わせが基本。 |
| 商業施設内の惣菜売場 | ショッピングモールや直売所内。家族連れ・高齢者層への訴求が有効。 |
| ネット販売・デリバリー | 常温〜冷蔵品を梱包し、オンライン注文を受付。 ラベル表示・クール便対応・製造体制の強化が必要。 |



なんか……めちゃくちゃ可能性あるじゃん!
しかも、イートインなしならワンオペでもいけそうだよね?



はい。
特に「夕方メインのテイクアウト」+「昼は仕込み時間」という流れは、個人・家族経営との相性も良いです。
- 曜日限定メニュー:金曜は「カレー」、水曜は「おでん」など習慣化させる
- LINEやインスタで新作や売れ筋を発信
- ポイントカードや割引券で来店促進
- 手書きPOP・レシピカードで親しみやすさを演出



今の惣菜屋は、「味の勝負」だけじゃない。
“どこで・誰に・どう届けるか”のマーケティング次第で成功確率がグッと変わります。
第8章|複合型そうざい製造業と漬物製造業|新設された許可とは?



そうざいって「漬物」も含まれるの?
前に「漬物屋さんの許可が必要になる」ってニュース見た気がするんだけど…



そう、あれは2021年(令和3年)に大きく変わった食品衛生法改正の話です。
この法改正では、次のような再編がありました
食品衛生法の改正ポイント(要約)
| 食中毒リスクの見直し | 食品ごとのリスクを科学的に評価し、制度を整理 |
|---|---|
| 新設された許可業種 | 漬物製造業/水産食品製造業/液卵製造業 など |
| 届出に移行した業種 | リスクが低い業種(乳類販売・氷販売など)は届出扱いへ |
| 一施設一許可の原則 | 工程や原材料が近い業種は「統合して1つの許可」で取得可能に |



これまで漬物の製造には許可が不要でしたが、食品衛生法の改正により「漬物製造業」が新設され、
今では漬物屋さんも許可を取得しなければならなくなったんです。
その猶予期間が終了したタイミングで、ニュースにも取り上げられましたね。



そうざい製造業からさらに漬物も新設されたの!?
もう、作るものによって、アレやコレやたくさん許可を取らないとダメなの?
面倒くさいな~…



同じく改正の中で、「一施設一許可」の原則が打ち出され、
それに伴い新たに登場したのが「複合型そうざい製造業」です。
複合型そうざい製造業とは?



惣菜店で「唐揚げ」「浅漬け」「炊き込みご飯」などを一つの厨房で作って売る場合、
以前はそれぞれ個別に許可を取る必要がありました。
でも、法改正でできた「複合型そうざい製造業」なら── 1つの許可で、複数のそうざい品目を一括して製造・販売できるのです。
複合型そうざい製造業の特徴まとめ
| 対象 | 惣菜のうち、異なる分類(煮物・焼き物・漬物など)を製造する業態 |
|---|---|
| 目的 | 一施設で多品目を扱う事業者の負担軽減/現実に即した制度設計 |
| メリット | 許可の一元化で手続きがラク/キッチンや設備を効率活用できる |
| 注意点 | 幅広い品目に対応するため、施設基準・衛生管理は高水準が求められる |



なるほどね!
わざわざ、あれやこれやたくさん許可を取らずに済むようになったんだね!
まとめ



今回は惣菜屋さんを始める方法についてお話しました。
惣菜を継続的に製造・包装・販売するには「そうざい製造業許可」が必要になります。
飲食店営業許可と違って、製造後すぐに食べるわけではないため、衛生管理がより厳格です。



開業には設備基準や保健所とのやりとりが多く、「事前相談」がとても重要です。
ただし、販売形態や施設条件によっては複合許可が必要な場合もあります。
まずは保健所へ事前相談し、あなたの理想の営業スタイルに合った許可を確認しましょう。



さあ、どうやって惣菜屋さんをはじめようかな!?
みんなも下記から選んで挑戦してみてね!