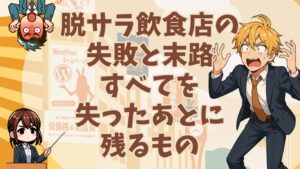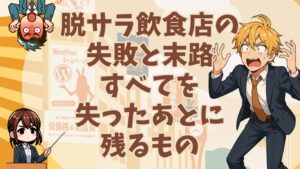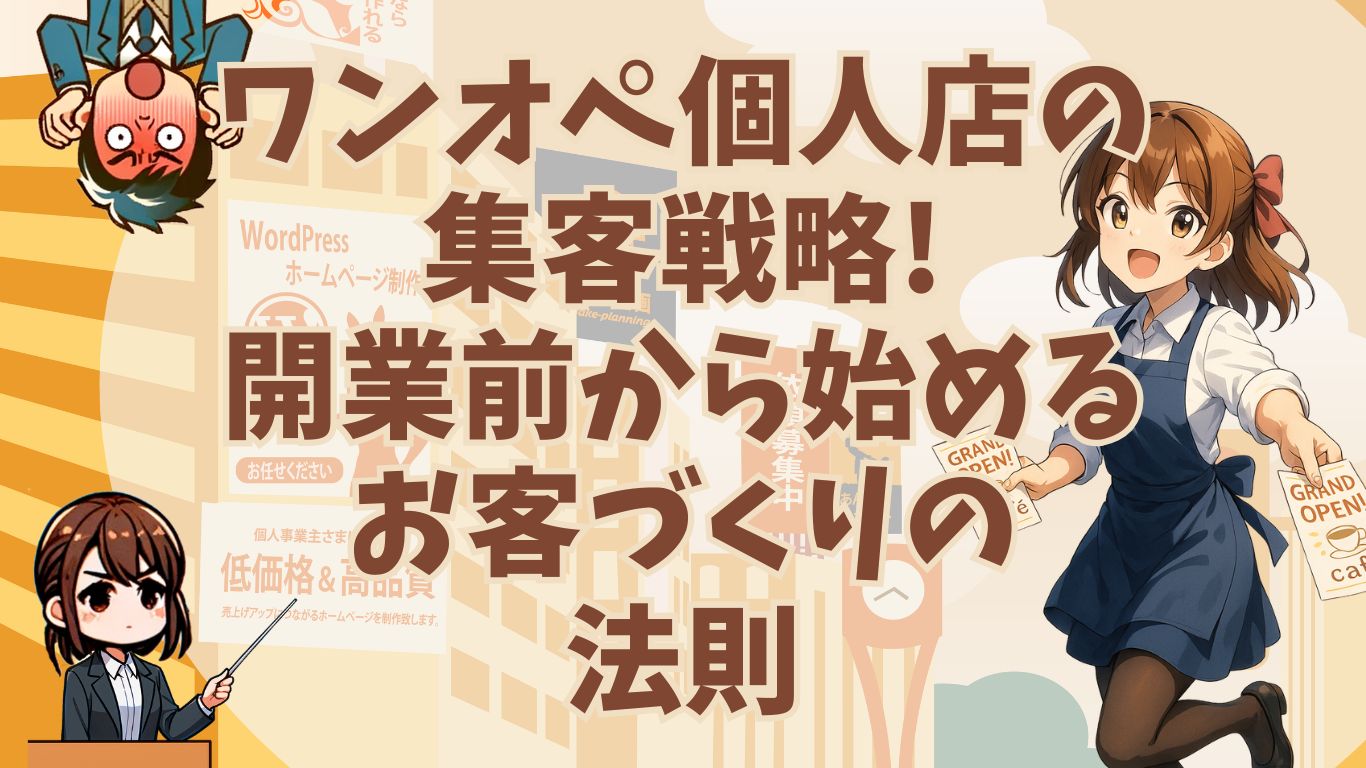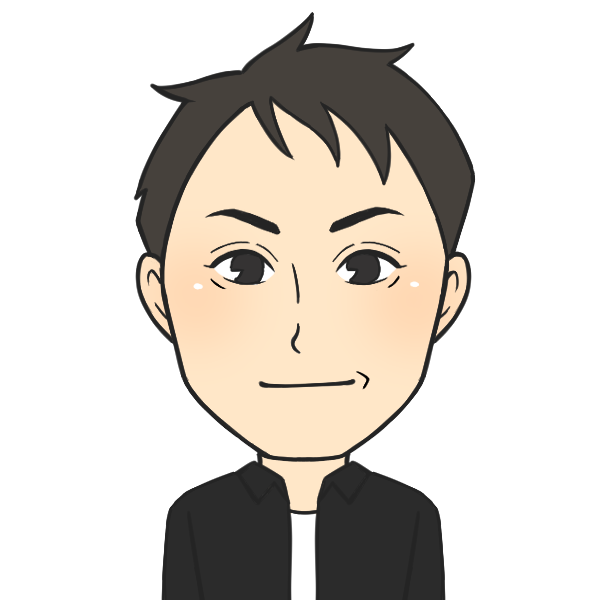甲斐承太郎
甲斐承太郎さあ、ついに店舗も完成間近。許可も無事に通ったし、これでひと安心だよね?
あとは開業までお客さんを待つだけ!!



そう思いたくなる気持ち、よくわかります。
でも現実は──“開けたらお客さんが来る”時代はもう終わりました。
お店を作ることはスタート地点。
そこから先に必要なのは、「お客さんを作る力」です。
集客とは「仕組み」であり、「運任せにしない努力」の積み重ねなんです。
- 開業前から始める集客の正しい順序がわかる
- SNS・地域・口コミをつなぐ導線設計の考え方がわかる
- オープン初日から満席をつくる実践ノウハウがわかる



良い店が生き残るのではなく、“知ってもらえる店”が生き残る。
宣伝とは派手さではなく、存在を継続的に伝える設計である。
あなたがこの章で学ぶべきは、広告テクニックではなく、
「どうすれば人の記憶に残るか」という商売の本質。
第1章|SNSをはじめよう ― 開業までの道のりがコンテンツになる





お店も形になってきたし、そろそろ宣伝を始めた方がいいのかな?
でもまだ完成してないし、看板もメニュー表も無い…
こんな中途半端な状態でSNSを始めても、意味あるの?



むしろ今がいちばん価値のあるタイミングです。
お店が完成してから投稿を始める人は多いですが、
フォロワーがゼロの状態から“オープンしました!”と告知しても、
誰の目にも届きません。



人は“完成品”よりも、“できていく過程”に惹かれるものです。
あなたが悩み、決断し、準備を進めるその姿こそが物語になります。
開業までの苦労や工夫を共有することで、
「応援したい」「オープンしたら行ってみたい」という“ファン予備軍”が生まれる。
SNSとは、宣伝ではなくお店の成長記録を通じて信頼を築くツール
開業準備は、すでに集客の一部である。
店ができてから発信するのでは遅い。
“準備のストーリー”を発信することで、
まだ見ぬお客が、あなたの最初のフォロワーになる。
補足:フロー型とストック型を組み合わせよう



SNSにも性格があります。
一瞬で広がる“フロー型”と、検索で積み上がる“ストック型”です。
集客とは、SNSの発信から地域のつながり、リピーターづくりまでを一本の導線として設計すること。
開業とは人を集める技術ではなく、人との関係を育てる技術です。
| タイプ | 媒体例 | 特徴 | 目的 |
|---|---|---|---|
| フロー型 | Instagram・X(旧Twitter)・Threads・TikTok | 拡散力が高く即効性がある | 開業前の話題づくり・ファン形成 |
| ストック型 | ブログ・YouTube | 検索で蓄積され長期的に読まれる | 開業ノウハウ・信頼構築・SEO効果 |



準備は戦略であり、集客は構造です。
SNSは勢い、ブログは信頼。
どちらか片方では集客は続きません。
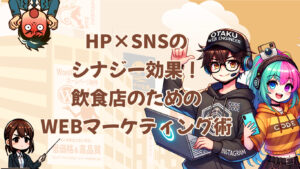
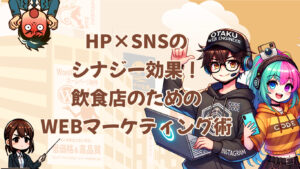
おまけ:インスタやTikTokで“参考になる投稿”を見つけよう



SNSで発信する前に、まず“上手な発信者”を観察しましょう。
開業準備中の人、個人カフェ、ワンオペ居酒屋など、あなたと近い立場の発信者は教材そのものです。
うまくいっている投稿には必ず理由があります。
構図、照明、音、テンポ、テロップ──これらを観察しながら、自分の発信に取り入れてみましょう。
- Instagramなら:「#開業準備」「#店舗DIY」「#カフェオープン準備」「#一人飲食店」などで検索
- TikTokなら:「開業準備 vlog」「店舗改装」「居酒屋オープン」などの短尺動画をチェック
- ThreadsやXなら:開業までの日常や悩みを綴るアカウントをフォローして“共感の文脈”を学ぶ


第2章|地域に届かせる ― チラシとMEOで現地集客を固める





いえい!SNSのフォロワーさんから、「ぜひ開店したら行ってみたい!」ってコメントをもらえた!
……って、あれ?この人、沖縄の人だ……。



それは嬉しいことですが、残念ながら飛行機では常連になってもらえませんね。
インターネットを活用した集客も大切ですが、
お店には“商圏(しょうけん)”――つまり実際に通える距離の範囲という現実があります。
だから、地域に根ざした集客も同じくらい大切なのです。



SNSは「全国に知ってもらう」力が強い一方で、
チラシやGoogleマップ(MEO)は「近所の人に来てもらう」ための仕組み。
どちらが欠けても、安定した売上にはつながりません。



なるほど。SNSで話題を作って、チラシやマップで実際に“足を運んでもらう”。
ネットと地元、両方のバランスが大事なんだね。



その通りです。では、地域でお店を“見つけてもらう方法”を具体的に見ていきましょう。
1.チラシは「オープン2週間前」が黄金タイミング



チラシは、開業直前に使う“最後の一撃”です。
早すぎても忘れられ、遅すぎても来られない。
理想は、オープンの2週間前に第一波、1週間前に第二波。



内容は、「何をやる店なのか」「いつオープンするのか」「地図と駐車場の案内」。
そして“行く理由”をひとつ添えましょう。
たとえば「オープン記念ドリンク1杯無料」など、行動を促す小さなきっかけです。
| 店舗規模 | 目安配布枚数 | 配布エリアの目安 |
|---|---|---|
| 10坪前後の個人店 | 2,000〜3,000枚 | 店舗から半径500〜800m |
| 郊外型(駐車場あり) | 5,000〜10,000枚 | 車移動圏内(2〜3km) |



なるほど、地元密着ってそういうことか。
SNSで「チラシ配布しました!」って報告するのもいいかもね。



ええ、それも立派な戦略です。
チラシをまくだけでなく、SNSでその様子を投稿すれば、
「地元でも本格的に動き出したんだ」と伝わります。
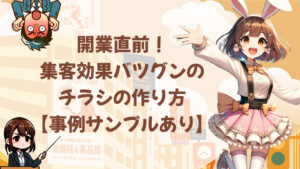
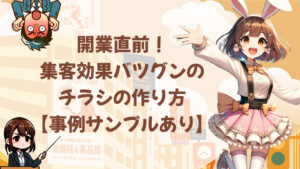
2.MEO対策は「開業前登録+口コミ育成」で差がつく



Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)は、
無料で使える“地域検索の主戦場”です。
「〇〇市 ランチ」「〇〇町 カフェ」で検索する人の目に、
あなたの店を表示させるのがMEO(Map Engine Optimization)。



開業前でも「準備中」ステータスで登録が可能です。
住所・営業時間・写真を整え、店舗の雰囲気を先に公開しておきましょう。
オープン当日には、すでに地図上に“居場所”ができています。



開業後は、友人や常連にお願いして最初の口コミをもらう。
その数件が、次に来る人の信頼になります。



口コミって、自分から頼んでもいいんだね。
“最初の数件”があるだけで安心感が全然違うもんな。



ええ、口コミは「信頼の入口」です。
お願いするのは営業ではなく“感謝の共有”なんです。


3. ホームページを持つことで「ストック型の集客」が完成する



チラシやMEOは即効性がありますが、効果が続くのは一時的です。
本当に強い集客は、自分のホームページを持つことで生まれます。
- ストック型メディアとしての長期的な検索効果
- オンライン予約システムを内蔵できる柔軟性



予約を“ゴール”に設計すると、
人があなたの店を見つけてから来店に至るまでの導線――
つまりAIDMA(アイドマ)理論が明確に組み立てられます。





この流れを意識すれば、
あなたのホームページは「見るだけ」ではなく「来店を生む仕組み」に変わります。



なるほど、SNSは拡散の入口で、ホームページは“行動の出口”って感じだね。



まさにその通りです。
“自分の公式サイト”を中心にすべての情報をつなぐ。
それが安定した集客の形です。



SNSで知ってもらい、チラシで足を動かし、MEOで検索に残す。
そしてホームページで予約という行動に変える。
これが、現代の“地域密着+デジタル連動型”集客の完成形だ。
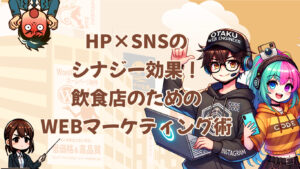
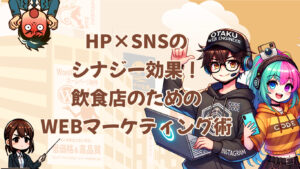
第3章|売上拡張編 ― 店舗の外にもお客をつくる





最近SNSで、うちの動画を見た人から「通販とかやってないんですか?」ってコメントが来たよ。
でも通販とかデリバリーって、個人店にはハードル高くない?
人も少ないし、そんなに手を広げたら回らなくなりそうだよ。



確かに全部を一度にやるのは難しいです。
でも、“お店の外にも売上をつくる”という発想は、
これからの時代に欠かせない視点です。



ポイントは「ワンオペでもできる範囲で、収益の柱を増やす」こと。
店舗営業だけに依存すると、天候・感染症・景気変動などに左右されます。
しかし、デリバリーや通販を一部取り入れるだけで、
リスクを分散しながら売上を安定させられます。



なるほど、“やらない”じゃなくて“できる形でやる”ってことか。
1.個人飲食店でもできるUber Eats加盟



Uber Eats(ウーバーイーツ)は、いまや個人店の重要な販路です。
加盟には「飲食店営業許可」があれば基本的に問題ありません。
登録手順はシンプルです。
- Uber Eats公式サイトで申し込み
- 店舗情報・メニューを登録
- 許可証を提出し審査を通過
- 専用アプリで注文受付を開始



初期費用は無料、導入まで平均2〜3週間ほど。
手数料は売上の約35%前後が目安です。



35%!?けっこう持ってかれるね……。



確かに大きく見えますが、
固定費ゼロで新規顧客を獲得できる“広告費”と考えれば悪くありません。
昼営業だけの店なら、夜だけデリバリー稼働という方法もあります。
厨房が空いている時間を活用するのがコツです。
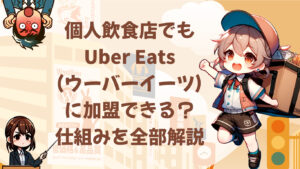
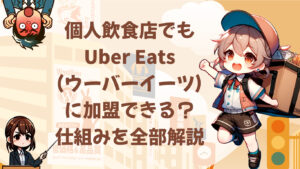
2.テイクアウト×デリバリーのハイブリッド運用



Uber Eatsを導入すると、
同時に「テイクアウト対応」も整備できます。
専用アプリで「持ち帰り注文」だけ受け付ける設定も可能ですし、
お店の公式LINEやホームページにテイクアウト注文フォームを設けてもOKです。
- 受け取り時間をずらして混雑を防げる
- 現金対応を減らせる
- SNSで「テイクアウト始めました!」と発信できる



つまり、デリバリー=遠くの顧客、テイクアウト=近くの顧客。
この2本を組み合わせれば、営業の幅がぐっと広がります。



そうか、どっちも“厨房の延長線上”なんだね。
別ビジネスって思ってたけど、意外とシンプルだ。
3.BASEで「製造業許可×通販」の新しい稼ぎ方



もし「菓子製造業許可」や「惣菜製造業許可」を持っているなら、
BASEなどのECサイトを使って自社商品を販売できます。



たとえば、店で人気のスイーツやソースを瓶詰めにして、
「自宅で味わえるシリーズ」として通販化する。
この発想で、仕込みの延長がストック型の売上に変わります。
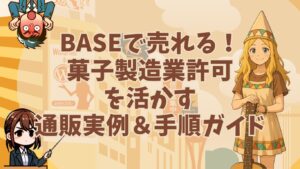
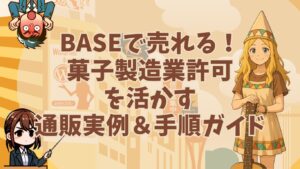



なるほど、店での売上と別のルートでファンを増やせるわけか。



ええ。お客さんが旅行帰りや引っ越し後でも、
通販を通じて“つながり続ける関係”が作れます。
4.店外収益を支える仕組みづくり



店外販売を始めると、どうしても注文対応や在庫管理が気になります。
そこはシステム化とデータ連携で乗り越えましょう。
- POSレジを使えばデリバリー売上も自動集計
- 会計ソフト(マネーフォワード等)と連携すれば確定申告が簡単
- ホームページ内に予約・注文ボタンを設置して顧客動線を統一



この仕組みを整えるだけで、
「お店を広げずに売上を伸ばす」ことが可能になります。
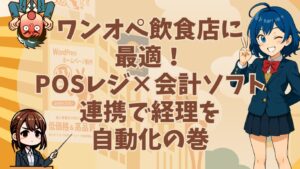
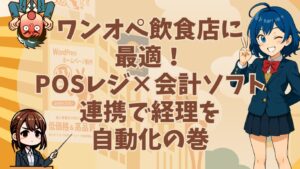



店舗の外に売上を持つとは、リスクを分散しながら関係を広げること。
Uber Eatsで新規を呼び、テイクアウトで常連を増やし、
BASEで遠方のファンとつながる。
ワンオペでも「動ける仕組み」を作れば、
お客は店の外でもあなたを見つけてくれる。
第4章|リピーター編 ― お店を“応援される存在”に変える



一回来て終わりの人が常連になってもらうにはどうすればいいの?
味には満足してもらってると思うけど、
どうしたら「また来たい!」って思ってもらえるんだろう?



とても良い感覚ですね。
リピーターづくりの第一歩は、
「一度来たお客さんに、もう一度理由を作ること」。



お客さんの行動をよく見ると、
“偶然見つけた人”が“常連”になるまでには段階があります。
この段階を設計してあげると、お店は「覚えられる店」に変わるんです。
1.LINE公式アカウントで“覚えてもらう仕組み”をつくる



LINEは無料で使える“再来店ツール”です。
名刺の代わりにQRコードを貼っておくだけで、
お客さんが登録すれば次から直接メッセージを送れます。



ポイントカードやクーポン機能を組み合わせれば、
「また行こうかな」という心理を後押しできます。
| 機能 | 目的 | 効果 |
|---|---|---|
| メッセージ配信 | 新メニュー・臨時休業のお知らせ | “思い出してもらう” |
| クーポン | 再来店を促す | “もう一度行く理由”を作る |
| ショップカード | 来店ごとのスタンプ | “常連化”を可視化 |



あー、確かに店員さんに「LINE登録してくれたら特典あります」ってよく言われるし、うさんくさいユーチューバーもライン登録したらスゴイ物無料で差し上げてます。ってよく言うよね。



その一言で、お店とお客さんの関係が“一度きり”から“続く”に変わります。
広告を打たなくても、リピーターが安定すれば固定収益が見えてくるんです。
→ 関連リンク:【LINE公式アカウント活用術|個人店でもできる再来店戦略】※準備中
2.口コミとレビューで“信頼を育てる”



リピーターは「体験の満足」だけでなく、
他の人がどう思っているかでも判断します。
Google口コミや食べログなどで、
あなたの店が“誰かに推薦されている”状態を作ることが重要です。
- 来店後に「よかったらGoogleに感想を書いてください」と伝える
- 口コミには必ず返信する
- 悪い評価にも丁寧に対応する
これだけで印象がまったく変わります。



たしかに、口コミを見て店を選ぶ人がほとんどだよね。
返信までしてくれる店って、ちょっと好感度上がるもんな。



ええ、返信は“信頼を育てる会話”です。
無言より、対話のあるお店が選ばれます。
顧客データを“おもてなし”に活かす



POSレジや会計ソフトを導入しているなら、
顧客データを活用して“記憶に残る接客”ができます。
- 来店回数の多いお客さんには誕生日クーポンを
- しばらく来ていない人には限定メッセージを
- 好きなメニューを把握して次に提案する



これはデータというより“記憶の補助ツール”です。
小さな気配りが、常連化を自然に進めてくれます。
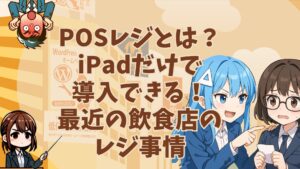
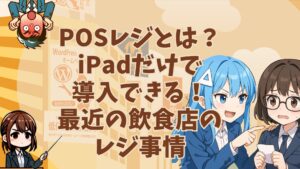



リピーターを増やすとは、お客を追いかけることではなく、覚えてもらう仕組みを作ること。
LINEでつながり、口コミで信頼を積み重ね、
データで“一人ひとりに合った接客”を実現する。
そうすれば、お店は“偶然見つけた場所”から“帰ってくる場所”になります。
第5章|開業準備の最終仕上げ ― レセプションで開店前に走り出す





やっとここまで来た……!
工事も終わって、メニューも決まった。
SNSのフォロワーさんたちにも「もうすぐオープンです!」って発信したし、
あとはオープン日を待つだけだよね?



その気持ち、よくわかります。
でも、実は“最後の一仕事”が残っています。
それが――レセプション(プレオープン)です。
レセプションとは? ― ゲネプロ(公開リハーサル)



レセプションとは、
開店前にお世話になった人や関係者、友人などを招いて行う“お披露目のリハーサル”です。
演劇で言うならゲネプロ(総リハーサル)。
営業を試しながら、同時に宣伝効果を得ることが目的です。
| 目的 | 内容 | 得られる効果 |
|---|---|---|
| 動線の確認 | 提供スピード、会計導線、厨房の混雑をチェック | オープン当日のトラブルを防ぐ |
| 顧客体験の検証 | 味・量・雰囲気・音・接客などの印象を確認 | 改善点を明確にできる |
| 宣伝効果 | SNS投稿・口コミの誘発 | オープン前に話題を作れる |
| 感謝と関係づくり | お世話になった人へのお礼の場 | 信頼関係の強化・口コミ種まき |
レセプションの2タイプと開催のコツ



レセプションには主に2つのスタイルがあります。
| クローズド型(招待制) | オープン型(一般公開プレオープン) |
|---|---|
| 家族・友人・取引先などを中心に行う形式。 準備段階での動線確認に向いています。 | SNSや店頭で「○日限定プレオープン」を告知。 特典付きでテスト営業を兼ねる方法。 |



どちらの場合も、“完璧を目指さない”ことが大切です。
レセプションは失敗するための場。
小さなミスや混乱こそ、翌日の本番での強さになります。



なるほど、リハーサルで失敗しておけば本番が怖くないってわけか。



実際にやってみると、厨房の配置や注文の流れ、レジの操作など、
図面だけではわからない改善点が必ず見つかります。
宣伝・口コミのスタートダッシュを仕掛ける



レセプションは集客の最初の爆発点でもあります。
- 友人や知人に「SNSに投稿してね!」とお願いする
- 撮影スポットを用意して“映える写真”を残してもらう
- ハッシュタグをあらかじめ設定する(例:#〇〇カフェ準備中 #〇〇町の新店)



この日のお客さんが、あなたの最初の宣伝部隊になります。
レセプション当日の投稿や口コミが、
Google検索やMEOの初期表示に大きく影響するのです。



確かに、友達の投稿って信頼感あるし、つい気になるもんな。



人は広告よりも“人の声”に動かされます。
レセプションは、その最初の口コミを生む最高のチャンスです。
写真・動画を“資産”として残す



もう一つ忘れてはいけないのが、写真と動画の撮影です。
このタイミングで撮った素材は、
今後のSNS発信・ホームページ・メニュー表など、すべての宣伝に使えます。
- スマホで十分。できれば明るい時間帯に撮影。
- オープン前・調理中・接客中など、動きのある写真を残す。
- 看板・外観・メニューなども撮影しておく。



写真って“思い出”じゃなくて“営業素材”でもあるんだね。



まさに。
SNSでもブログでも、ストック型の発信をするには素材の貯金が欠かせません。
レセプション後にやるべきこと



イベントが終わったら、そのまま打ち上げで満足せずに、
必ずフィードバックを取ってください。
- 提供スピードや接客の感想を聞く
- 「料理の量はちょうど良かったか」「店内の動線はスムーズだったか」などを確認
- 良かった点・改善点をメモして即修正



そして、SNSで「レセプションが無事に終了しました!」と投稿。
感謝と同時に、次の本番を宣言することで、オープンへの期待値が高まります。



なるほど。レセプションって“終わり”じゃなくて“始まりの前の助走”なんだね。



レセプションは、感謝・検証・宣伝・記録のすべてを兼ねた開業の最終試験。
SNSで物語を発信し、地域に根を張り、店外に販路を広げ、
最後にレセプションでそれらを一つに繋ぐ。
ここで得た反応が、オープン後の“本当のスタートライン”になる。
まとめ



集客とは、SNSの発信から地域のつながり、リピーターづくりまでを一本の導線として設計すること。
開業とは人を集める技術ではなく、人との関係を育てる技術です。



準備は戦略であり、集客は構造です。
SNSもMEOもレセプションも、偶然ではなく設計の結果。
仕組みを作った人だけが、経営という長い物語を続けられる。



ここまで色々あったけど、やれることは全部やったはず…



これですべての準備が整いました。
次が最後の教えになります。