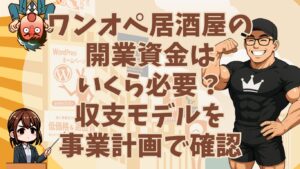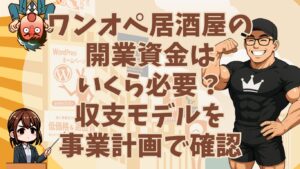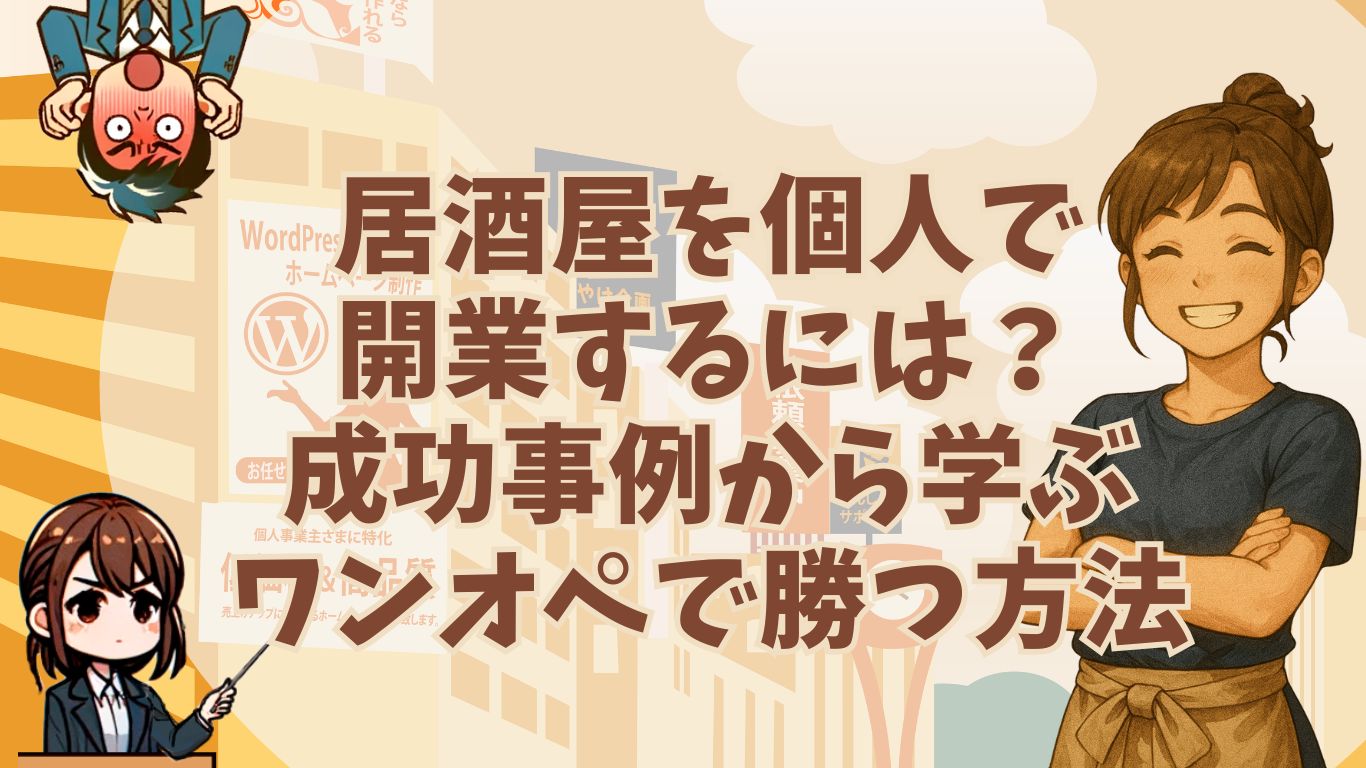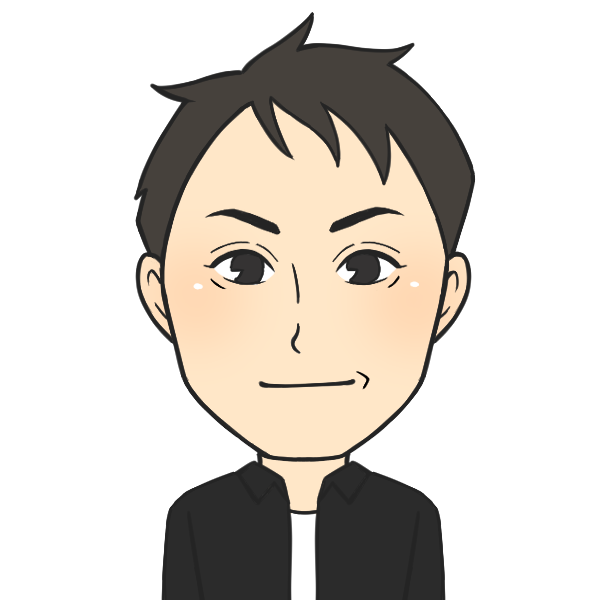甲斐承太郎
甲斐承太郎居酒屋ってさ、みんなで美味しい料理食べてお酒飲んで、あの空気感が好きなんだよね。
でも、僕みたいな個人が店を出すってやっぱり難しいのかな?
チェーン店だらけだし、人を雇うお金もないし……ワンオペで居酒屋なんて、現実的にありえるの?



そうですね。
たしかに大きな店舗や複数のスタッフを前提に考えると、個人で居酒屋を始めるのは難しく思えるかもしれません。
だけども――“個人にしかできない居酒屋”というのも、あるんですよ。
たとえば、10坪にも満たないような小さな空間で、店主が一人で切り盛りするお店。
小さいからこそ、目が行き届く。
一人だからこそ、こだわりが伝わる。
そんな居酒屋が、今ちょっとした注目を集めているんです。
- ワンオペで居酒屋を開業する現実的な方法と必要な準備
- 実際に成功しているワンオペ居酒屋の具体的なスタイルがわかる
- ワンオペでも無理なく回せるメニュー構成と導線の考え方が学べる



10坪未満の小さな居酒屋を一人で回すスタイルは、
少人数時代の“最適化された飲食ビジネスモデル”です。
むしろ、個人だからこそ勝てるやり方です。
小さな居酒屋のメリット・デメリット





なるほど…。でも小さい居酒屋って、やっぱり売上とか少なくなっちゃうんじゃない?
ちゃんとやっていけるのかなあ。



そこがポイントなんですよ。
確かに、10坪未満の小さな居酒屋には制約もあります。
だけど、“小さい”ことには明確な強みもあるんです。
小さな居酒屋・ワンオペ経営のメリット
- 固定費が低い
→ 家賃・人件費が抑えられるので、少ない売上でも黒字化しやすい。 - 運営がシンプル
→ 仕入れ・仕込み・営業・会計まですべて把握できる。トラブルが少ない。 - 自分の理想の店が作れる
→ コンセプト・メニュー・接客スタイルまで全て自分の裁量で決められる。 - お客との距離が近い
→ 常連との関係が深まりやすく、リピート率が高い経営が可能。 - 撤退・業態転換もしやすい
→ 初期投資が少ないから、万が一のときも被害が小さい。リスト



おお…なんか、小さいってマイナスじゃないんだね。
逆に強みになってるのが面白いな。



その通り。
けれど、もちろん注意点もあります。
小さな居酒屋・ワンオペ経営のデメリットとリスク
- 体調不良=営業停止
→ 代わりがいないため、1日の休業がそのまま損失に。 - 繁忙時に対応しきれないことも
→ 一度に複数の来客があると、提供や接客が遅れてしまうことも。 - 営業中にトラブルが起きると全部一人で対応
→ 電話対応・クレーム・洗い物・会計…全部自分。 - 長時間労働になりやすい
→ 開店準備から閉店、片付けまでを一人でこなすため、体力的負担は大きい。 - 精神的に孤独になりやすい
→ 困った時に相談相手がいないと、モチベーション維持が難しいことも。
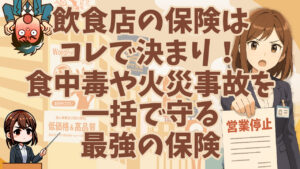
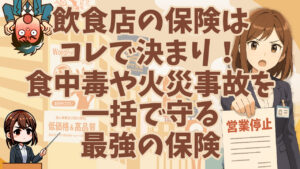
どんなスタイルで始められる?小さな居酒屋の業態アイデア



たしかに、ワンオペにもメリットがあるのは分かったけど…
どんな業態なら一人で無理なく回せるのかな?
普通の居酒屋って、揚げ物に焼き物に刺身に…って忙しそうだけど?



いいところに気づきましたね。
すべてのメニューを幅広く揃える“総合型居酒屋”は、たしかにワンオペでは厳しい。
だけど逆に、メニューのジャンルを絞った「特化型」や「家庭型」なら、
一人でもしっかりやっていけるんですよ。
それでは、代表的なスタイルを見ていきましょう。
アイデア①:焼鳥・おでんなどの「一品特化型」


- 少数の素材で回転率重視
- 炭火や煮込みなど、ライブ感のある提供が魅力
- カウンター型との相性抜群(串焼き・煮込み・燗酒)
例:札幌「とくさ」…おでんと季節野菜を中心に、女性店主が一人で営業
アイデア②:小料理と日本酒の「和風バルスタイル」


- 地酒×おばんざいなど、語れるメニューが強み
- 加熱せずに提供できる常備菜を中心に仕込んでおくと◎
- カップ酒や出汁割など、ワンポイントの工夫で話題化
例:東京「風見堂」…6.9坪・17席で自家製ソーセージや出汁割酒を提供し人気
アイデア③:カウンター6席の「ひとり飲み特化型」


- ターゲットは「一人飲み層」「0次会」など短時間利用客
- 滞在時間を短く回転率を上げる設計
- セットメニューや前払いスタイルも有効
キーワード:カウンター/ファーストドリンク/サク飲み/1時間で完結
アイデア④:「おばんざい系」家庭料理の店


- 常備菜を中心に仕込み、注文後は盛り付けだけ
- 接客と料理が融合した「おかえり系」コンセプト
- 高齢層や女性客に人気
キーワード:煮物・サラダ・揚げない・健康志向/惣菜とごはん
アイデア⑤:昼は定食/夜は居酒屋の「二毛作営業」


- 昼はランチで現金収入、夜は常連づくり
- ワンオペなら回転率より「安定した客層」を狙う形がベスト
- 定休日を組み合わせて体力調整も可能
例:晴レルヤ(西荻窪)…肉料理×蕎麦で昼夜二毛作



へぇー、いろんなスタイルがあるんだね。
なんか、自分でもできそうな気がしてきた!



キーワードは、「手数を減らして、価値を伝える」。
やることを絞って、“小さな強み”をつくることです。
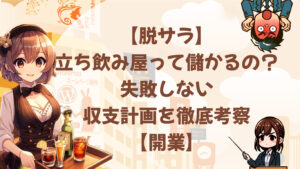
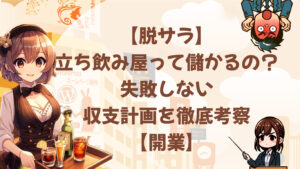
どのくらいの広さ・席数が適正?



そういえば、小さな居酒屋ってどのくらいの広さがあればできるの?
やっぱりカウンターだけの狭い店じゃないと、ワンオペは厳しいのかな?



いい質問ですね。
ワンオペで無理なくお店を回すなら、広すぎないことが大前提になります。
だいたいの目安で言うと…
ワンオペに最適な店舗規模の目安
| 規模 | 広さ | 席数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 最小モデル | 5〜7坪 | 5〜8席 | カウンターのみ。家賃・光熱費がとにかく安い。 |
| 標準モデル | 8〜12坪 | 8〜15席 | カウンター中心+小さなテーブル1〜2卓 |
| 広めモデル | 13〜15坪前後 | 15〜20席 | ワンオペ限界ギリギリ。ピーク対応に工夫が必要 |



特におすすめなのは、10坪前後(約33㎡)で10〜15席くらいの店です。
動線が短く、厨房からすべての客席を見渡せるレイアウトが理想。
カウンター主体で、注文・提供・会計がその場で完結する設計なら、一人でもスムーズに対応できます。



やっぱり厨房から目が届く範囲におさめるのがポイントなんだね。
トイレ掃除から洗い物まで、全部ひとりでやるって考えたら…大きすぎたら自滅しそう。



正解です。
ワンオペにおける失敗要因のひとつは「欲張って店を広くしすぎること」。
客席を増やしても、提供が遅れて満足度が下がれば逆効果。
成功例:中目黒「風見堂」の場合
- 広さ:約6.9坪
- 席数:17席(カウンター+壁際の立ち飲み)
- オープンキッチンで目が届く導線
- 月商250万円(坪月商35万円超)という高収益を実現



「この範囲なら自分ひとりで責任を持てる」っていうサイズ感を見極めるのがコツですね。
面積が狭くても、動きやすく整えられた店なら、一人でも十人力ですよ。
成功例②:西荻窪「晴レルヤ」の場合
- 広さ:約9坪
- 席数:12席(カウンター+テーブル数卓)
- メニューは「肉料理」と「蕎麦」に特化
- 回転率より“満足度”重視で常連化に成功
- 店主ひとりで仕込みから接客まで対応



このお店は、「ワンオペでもまわるように設計されたメニュー構成」が秀逸なんです。
昼は蕎麦ランチ、夜は肉料理とお酒という“二毛作営業”で、時間帯ごとに仕込み・調理の負担を分散。
さらに、オーダーが偏らないようメニュー数もコントロールされていて、お客の満足度と効率を両立しています。



面積も10坪以内。
提供スピードと厨房動線、どちらも“無理なく最大効率”に設計されています。
ワンオペでも高単価メニューと回転数のバランスを保てば、坪月商30万円超も現実的です。
成功例③:名古屋・千種「いざか家 ごんた」の場合
- 広さ:約14坪
- 席数:カウンター6席+テーブル12席=計18席
- 店主は元システムエンジニア。脱サラして独立
- 「焼き物+小鉢+ごはんもの」の三本柱でメニューを厳選
- デジタルツールを駆使し、限界ギリギリのワンオペ経営を成立させている



この店の面白いところは、「人を雇わずに、人並み以上に回す」という発想ですね。
厨房もホールも店主ひとり。けれど、ピーク時の混雑感はほとんどない。
その秘密は、デジタル化と設計の妙にあります。
- 焼き物はカウンター前のグリラーで常時火入れ → 注文から提供まで平均3分以内
- 小鉢は常備菜中心(5品×日替わり)→ 盛り付けだけで即提供
- ごはんものは3種(出汁茶漬け、焼きおにぎり、鶏そぼろ丼)に厳選
→ 同一材料で回せて仕込みもラク
- ホールと厨房の行き来が最短2歩以内
- 食器の返却口・水セルフ設置で歩数を減らす
- 店内のすべてが「目視可能」な視野設計
- 集客特化型ホームページで集客も自動化
- Googleマップに掲載することで発見される機会を増やし、ホームページへと誘導。
- さらに、季節限定メニューやお店のコンセプトを丁寧に伝えることで、ファン化を促進します。
- POSレジ(スマレジ)と連携した在庫・売上管理
- 売上データをもとに、在庫の動きをリアルタイムで把握。
- 翌日の仕入れまで自動で計画できるため、発注ミスや欠品を防ぎ、業務の効率化に貢献します。
- キャッシュレス決済端末で会計を自動化
- お釣りの受け渡しを省くことで、調理や提供の手を止めずに済み、衛生面の負担(手洗い等)も軽減。
- さらにPOSレジと連携させることで、レジ締め作業も大幅に時短化され、閉店後の業務効率が向上します。



すごっ…もはや一人とは思えない…!
それ全部、手作業じゃ絶対無理だよね。



ワンオペの限界は、“人”ではなく“仕組み”で越えるものです。
いまや、ITツールは第二のスタッフ。
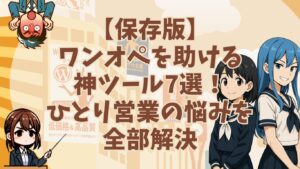
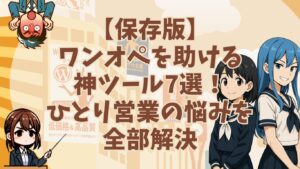
具体的にいくらかかる?開業費用の目安





ここまで見てくると、「自分にもできそう」って思えてきたけど…
やっぱり気になるのはお金の話なんだよね。
小さな居酒屋って、実際いくらぐらいで始められるの?



そこ、大事なポイントですね。
開業資金は立地や物件の状態によって大きく変わりますが、
「居抜き物件」か「スケルトン物件」かで、かなり差が出ます。
では、おおまかな目安を見てみましょう。
開業費用の目安(10坪モデル)
| 項目 | 居抜き物件の場合 | スケルトン物件の場合 |
|---|---|---|
| 物件取得費※ | 約150万 | 約200万〜300万 |
| 内外装工事費 | 約100万〜150万 | 約300万〜500万 |
| 厨房設備・什器 | 約100万 | 約200万〜300万 |
| 開業後の運転資金 | 約150万〜200万 | 約150万〜200万 |
| 合計 | 約500〜700万 | 約800〜1,200万 |



ワンオペでやるなら、10坪以下×居抜き物件が現実的な選択肢です。
たとえば札幌・すすきのでのモデルケースでは、約956万円で開業できた実例もあります。
初期費用を抑えつつも、内外装や厨房に必要な設備はきちんと整えた、堅実な開業スタイルです。



費用を抑えるコツは、次の3点。
・居抜き物件を探す(設備が残っている)
・メニュー数を絞り、厨房機器を最小限に
・家賃は「月商の10%以下」に収めること



なるほどなぁ。
やっぱり「店の広さ」と「初期投資」のバランスって超重要だね。



ええ。開業後に資金が足りなくて潰れてしまうお店も多いですから、
運転資金を含めた“総額”で考えるのが鉄則です。
メニューはどうする?ワンオペで回せる献立の考え方



やっぱりメニューも重要だよね。
でも、一人でやるなら、料理の数とか調理の手間も限られるよね?
どれくらいの品数とか、どんなジャンルが向いてるんだろう?



その通り。
ワンオペで成功しているお店には、「提供しやすい」ことを前提にしたメニュー構成があります。
キーワードは、「絞る」「仕込む」「回す」です。
| 観点 | 内容例 |
|---|---|
| 絞る | ジャンルを絞る(焼き物中心・おでん特化など)/品数は10〜15品以内が理想 |
| 仕込む | 営業前に仕込み完了できる常備菜・煮込み/注文後は盛り付けだけにする |
| 回す | 焼き・煮る・盛るなど工程を固定/同じ具材で複数メニューに転用できる設計にする |



たとえば「焼き鳥+小鉢+ごはんもの」のように、火口を1〜2に絞っても魅力的に見せる構成がポイントです。
料理にストーリーがあると、品数が少なくてもお客さんは満足します。
メニュー構成の具体例(10品以内)
| ジャンル | メニュー例 | 工夫ポイント |
|---|---|---|
| 焼きもの | 焼き鳥3種、焼き野菜2種 | 串打ち済の冷凍/炭火はライブ感◎ |
| 煮込み | 牛すじ煮込み、豆腐のだし煮 | まとめて仕込み/温めるだけ |
| 小鉢 | ポテサラ、ひじき、ピリ辛もやし | 盛り付けのみで即提供 |
| ごはんもの | 焼きおにぎり、ミニ出汁茶漬け | 鍋不要/味変で変化つける |
| デザート系 | 冷凍わらび餅、杏仁豆腐 | 解凍提供で洗い物も減らせる |



へぇ〜、これなら少ない数でも“ちゃんとした店感”が出るなぁ。
仕込みで勝負するって、逆にプロっぽい。



むしろ、ワンオペは“回せるかどうか”が生死を分けます。
注文が集中するときにどう耐えるか、そのためのメニュー絞り込みです。
実例:風見堂の工夫
- メニュー数は常時10品前後
- 仕込み中心の和風おつまみ+1品だけの看板料理(自家製ソーセージ)
- 注文のバラけを考え、同時提供ができるよう設計



特におすすめなのが、「おすすめ3品セット」や「店主おまかせ盛り」のような
「選ばせないメニュー」の活用です。これでオペレーション負荷をグッと下げられます。
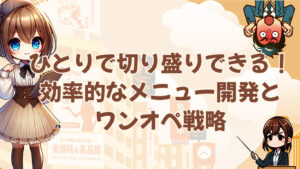
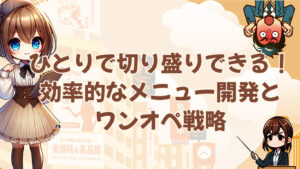
どんな許可・資格が必要になる?



ところで、居酒屋を開くってことはやっぱりなんか資格とか申請がいるよね?
個人だし、ひとりでやるなら手続きも大変そう…



そうですね、手続きは避けて通れません。
でも大丈夫です。
個人でワンオペの小さな居酒屋を始めるなら、必要な資格と許可は最小限に絞れます。
むしろ、何をやるかが明確なら、手続きもすぐ整理できます。
| 種類 | 内容 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 食品衛生責任者 | 調理や提供を行う飲食店に1名必要。1日講習で取得可 | 保健所 |
| 飲食店営業許可 | 飲食物を店内で提供するには必須。施設基準あり | 保健所 |
| 防火管理者 | 収容人数30人以上の店舗は必要。小規模なら不要なことが多い | 消防署 |
| 深夜酒類提供届出 | 深夜0時以降も営業するには届出が必要 | 警察署 |



とくに重要なのは「食品衛生責任者」と「飲食店営業許可」の2つ。
これがなければ保健所の営業許可は降りません。
施設(厨房・手洗い・給排水設備など)も保健所の基準を満たす必要があります。



事前に「営業予定地の保健所」に連絡して、
図面をもとに相談・確認をしておくと、トラブルは防げます。
※自治体によって細かい基準が違うので要注意です。
まとめ



今回は、「ワンオペ居酒屋って実際にできるのか?」というテーマで、
数字も現実も見据えたうえで、「ワンオペ」という選択肢には十分な現実味と可能性があることを、お伝えできたかと思います。



「ひとりでやるからこそ、無駄がない」
「ひとりでやるからこそ、お客様に伝わるものがある」
ワンオペは孤独ではなく、“最少人数で最大の価値を届ける”ための手段です。
重要なのは、「できる形に落とし込む」こと。



なるほど…
ワンオペでも、ちゃんと準備して考えれば、ひとりで勝負できるんだ!
でも「いくらかかるのか」「どれくらい稼げるのか」って…やっぱりちゃんと知っておきたいよね。
次は「開業資金と売上のリアル」を学んで、僕のお店の“数字”をイメージしてみたい!