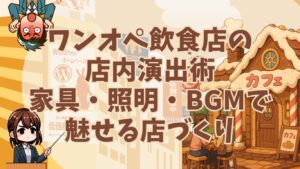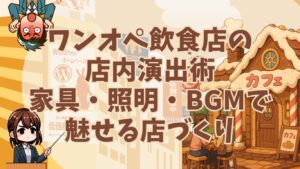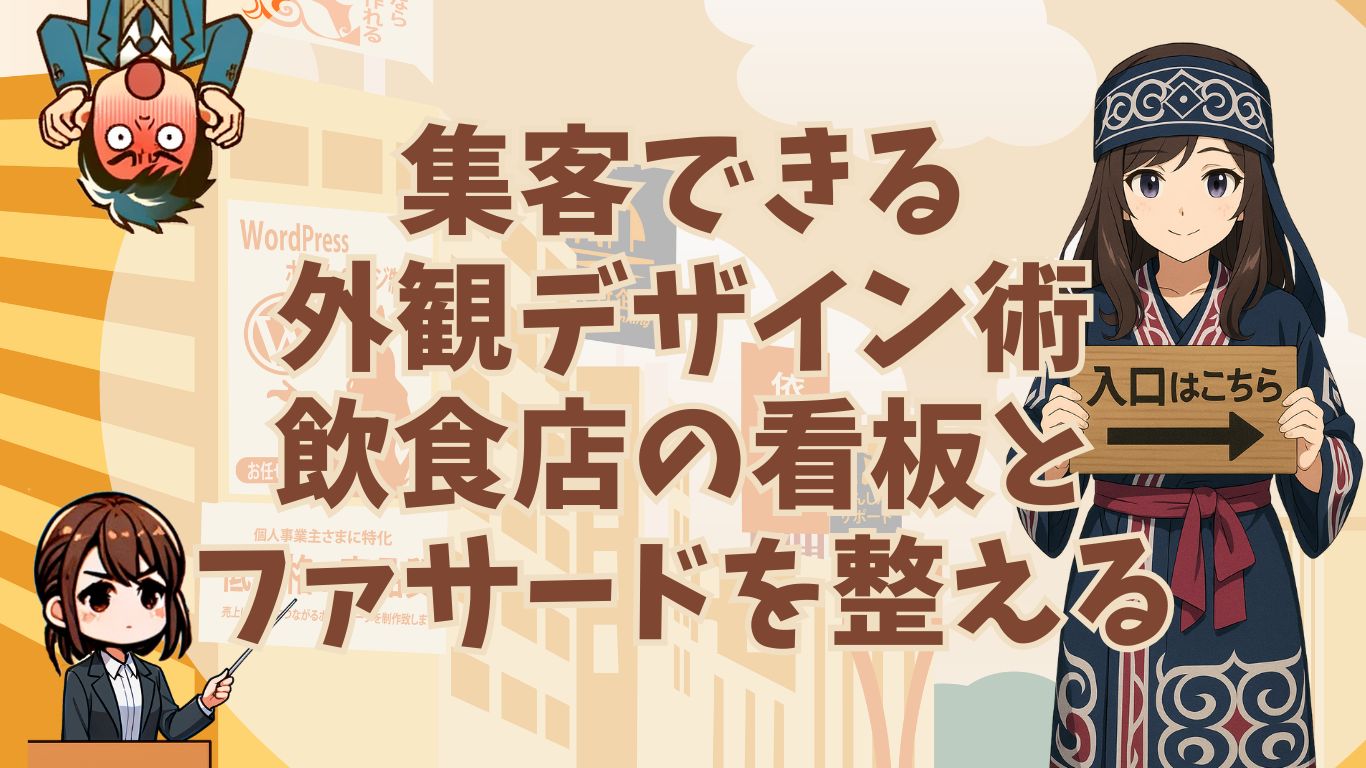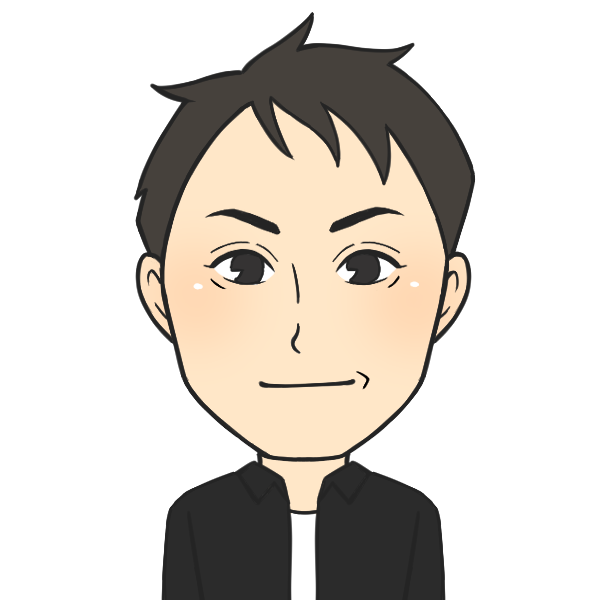甲斐承太郎
甲斐承太郎そろそろ店の外観も考えたいんだけど、やっぱり派手な看板にした方がいいかな?
赤とかネオンとかドーン!って感じで目立たせたくなるんだよな。



気持ちは分かりますが、外観は「目立つ」よりも「伝わる」が正解です。
看板とファサード(お店の正面部分)は、通りがかりの人に「どんなお店か」「入りやすいか」を3秒で判断させる場所です。
つまり、“広告”ではなく“入口そのもの”なんですよ。
- テナント店舗と路面店では「外装工事の自由度と費用」がまったく違う理由
- 外装工事の流れと、やっていいこと・ダメなことの境界線
- お客様の足を止める「看板とファサード」づくりの考え方



看板は「見える・読める・覚えられる」が鉄則。
そしてファサードは、「入りやすさ」と「世界観」のバランスで設計します。
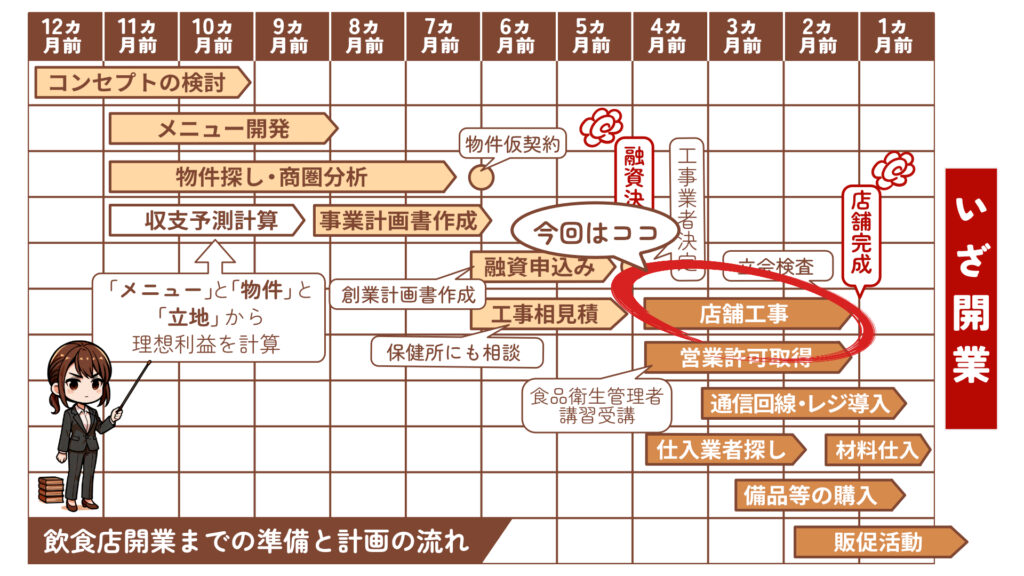
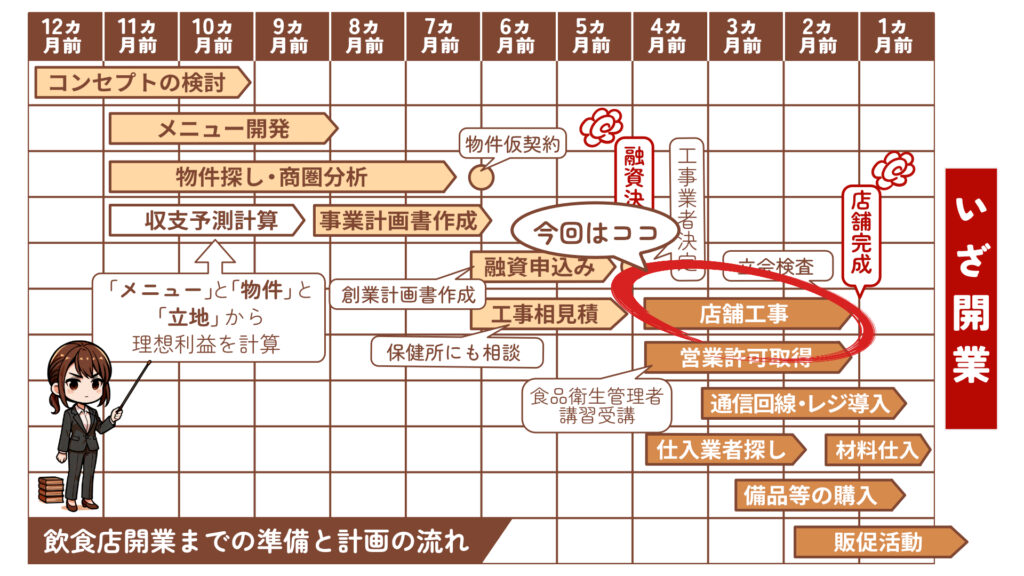
第1章|外装工事って誰に頼むの?内装と一緒にできるの?





そもそも外装工事ってどうすればいいの?
内装工事のときみたいにデザイナーを探すの?
それとも、内装業者がついでにやってくれたりするの?



いい質問ですね。
実は外装工事って、「内装とセットでやる場合」と、そうでない場合」があります。
店舗の種類や契約条件によって進め方がまるで違うんです。



特にワンオペ飲食店のような小規模店舗では、
ほとんどがテナントビルの一室を借りて営業します。
このタイプだと、建物の外壁や共用部には手を加えられないのが一般的です。



なるほど。
じゃあ「外装工事」っていっても、やれる範囲が限られてるってことか。



そうです。
実際のところ、外装工事には二つのパターンがあります。
外装工事の2つの進め方
| タイプ | 主な特徴 | 向いている店舗 |
|---|---|---|
| ① 内装業者が一括で行うタイプ | 設計・施工業者が内装と合わせて外装も担当。看板・入口・照明などまでまとめて発注できる。 | スケジュールを短縮したい店舗、時間がないオーナー向け |
| ② 分離発注タイプ(外装専門業者に依頼) | 看板・サイン・外壁仕上げなどを専門会社に個別で発注。コストを抑えやすく、デザインも柔軟。 | 予算を細かく調整したい、こだわりの看板を作りたいオーナー向け |



一般的には「内装+外装一括発注」が増えています。
ただ、外装専門業者に頼む方が費用を抑えられることもあるんですよ。



その場合、デザイナーが図面を描いて、外装業者が実際に施工するという流れになります。
ただし別発注だと、電気や配線の位置などを事前に調整しておかないとトラブルの原因になります。



え、そんなことまで考えなきゃいけないの?
やっぱり最初から内装と一緒に頼んだほうがラクそうだな。



スピードと安全を重視するなら一括発注。
コストとデザインの自由度を重視するなら分離発注。
この選択がまず最初の分かれ道になります。
第2章|テナントビルでの外装工事:できること・できないこと



ワンオペでお店やるなら、やっぱりテナントビルの一室ってことになるよね。
でもその場合、外装ってどこまでいじれるの?



そうですね。まず基本として、テナントビルでは外観全体を自由に工事することはできません。
建物の所有者や管理会社が外壁のデザイン・構造を管理しているため、
勝手に塗装したり看板を埋め込んだりはNGなんです。



テナント契約書の「原状回復義務」や「共用部禁止条項」によって、
外装の改修範囲が明確に制限されています。
つまり、手を入れられるのは専有部分の入口周りだけというのが一般的です。
テナントビル一室で実際にできる外装工事
| 工事項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 入口ドアまわりの装飾 | シート貼り・塗装・小型照明の追加 | 内装業者が対応可能な範囲 |
| ガラス面サイン | 店名ロゴ・営業時間シールなど | デザイン会社 or 看板業者 |
| 袖看板(突き出し) | 通行人向けサイン。許可が必要 | 管理会社の承諾必須 |
| 壁面プレート看板 | ビル指定サイズのプレートを設置 | デザインは制限あり |
| スポットライト照明 | 看板を照らす外照式照明 | 配線計画に注意 |
| ドア横ポスター枠設置 | メニューや日替わり告知など | 自立型・貼替式が便利 |



けっこう制限あるんだなぁ…。
でも、他の店でもよくドア横に光る看板出してるじゃん?
あれってどうしてるの?



あれは「袖看板」ですね。
実際にはビルオーナーに設置許可を取ったうえで、既存の金具や穴を使って設置していることが多いです。
新しく壁に穴をあけたりビスを打ち込むと、原状回復費を請求されるリスクがあります。



だからこそ、看板は軽量・取り外しやすい構造にするのが鉄則です。
アルミ複合板・カルプ文字・LED内照式など、後で外しても跡が残りにくい素材を選ぶオーナーが増えています。
外装工事の予算感(テナントビル一室)
| 項目 | 目安費用 | 備考 |
|---|---|---|
| プレート看板 | 5〜15万円 | 壁面に固定する小型タイプ |
| 袖看板(突き出し) | 10〜25万円 | 設置許可と配線工事含む |
| 窓サイン・ロゴ | 3〜10万円 | デザイン・カッティングシート費 |
| 外照式照明 | 5〜10万円 | スポットライト×数基 |
| エントランス装飾 | 10〜30万円 | 塗装・素材・装飾内容による |
| 合計目安 | 30〜70万円程度 | ※内装とは別見積もりになるケース多し |



思ったより現実的な金額なんだな。
これなら小規模でも“お店っぽい見た目”にはできそう。



ただし、ビル内店舗は見えにくい立地が多いです。
だから、外装工事よりも「看板の見せ方」や「照明の当て方」で差をつけるのが大切です。



そうですね。
ワンオペ店なら「照明+小さな看板+清潔感ある入口」が鉄板です。
シンプルでも丁寧に設計すれば、それだけで“入りやすい店構え”になります。



なるほど。
つまり、テナントビルでは「派手に変える」より「限られた範囲を磨く」って感じか。



その通りです。
外装工事の基本は「制約の中でどこまで表現できるか」。
そして、それをきちんと許可の範囲でやることが信頼につながります。
第3章|路面店・独立店舗の外装工事:お店の顔をつくる自由設計





じゃあ逆に、路面店だったらどこまで自由にできるの?
外壁も看板も、好きなように変えていいの?



はい、基本的に建物のオーナーが許可すれば、かなり自由にデザインできます。
路面店は外装が“お店の顔”そのもの。
看板・照明・ファサード(建物の正面)などを全部ひっくるめて、
ブランドの世界観を表現する場所になります。



ただし、自由度が高いということは、費用も上がるということです。
外装の塗装・サイン・照明のすべてを自分で発注するため、
テナントビルのように「ビル既定の看板に入れるだけ」とは違います。
路面店での外装工事の主な内容
| 工事項目 | 内容 | 目安費用 |
|---|---|---|
| 外壁仕上げ工事 | 塗装・板張り・タイル貼りなど外観全体を刷新 | 20〜30万円(10坪規模) |
| ファサード看板 | 店舗名を大きく掲げる主看板。電飾・立体文字なども | 20〜50万円 |
| 袖看板・スタンド看板 | 通行人に向けた誘導サイン | 10〜30万円 |
| 照明・ライトアップ | 看板・外壁を照らす照明設置 | 10〜20万円 |
| 装飾(植栽・庇・窓枠) | 入口周りのデザイン演出 | 5〜15万円 |
| 合計目安 | 50〜150万円程度 | デザイン性・素材で変動 |



なるほど…!
たしかに街を歩いてても、かっこいい店って外観からして違うよな。
でも100万円って、ワンオペ店にはちょっと重いなあ。



だから実際のオーナーは、「お金をかけるところを絞る」のが上手です。
たとえば以下のような工夫で、全体コストを半分以下に抑えることも可能です。
- 看板だけはプロに頼む(目を引くロゴや光の演出)
- 外壁はDIYで塗装(ペンキ+職人一日手間で大幅節約)
- 照明はネット購入+電気工事だけ依頼



へぇ〜、それなら現実的だね!外観でお客さんが入るかどうか決まるもんね。



まさにそこです。
路面店では外装が“広告”の役割を果たします。
夜間営業なら、照明の明るさひとつで印象が変わりますし、
昼間なら「通りすがりに写真を撮りたくなる外観」が最強の宣伝になります。
オーナーが実践する外装工夫のポイント
| ポイント | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 昼夜の見え方を意識 | 昼は明るいトーン、夜は照明で雰囲気を演出 | SNS映え・集客アップ |
| 店舗名を視認しやすく | ロゴ・文字サイズ・コントラストを強調 | 一瞬で「何屋かわかる」 |
| 入口の清潔感を維持 | ドア・床・植栽のメンテを定期的に | リピーターの安心感向上 |
| 地域景観に合わせる | 周囲の建物と調和する色や素材を選ぶ | 町並みに馴染みつつ個性を出す |



ちなみに、路面店でも景観条例や看板サイズ制限はあります。
特に観光地や商店街では、派手すぎるデザインが禁止されている場合も。
「デザイン会社+行政書士(屋外広告申請)」の連携が必要なこともありますのでご注意を…



ん?どこか別記事で同じような話を聞いたような聞いてないような…



前にもしてます。
ただ、上手にやれば“その街らしさ”を生かしたデザインで好印象を得られます。
路面店はまさに「あなたの世界観を表に出す舞台」なんです。



なるほどね〜。
テナントビルのときは「限られた範囲を磨く」、
路面店は「世界観を外に出す」。
…だんだんイメージ湧いてきた!



いい感覚です。
では次に、両者の違いを整理してみましょう。
あなたのお店がどちらのパターンに近いか、一目でわかりますよ。
番外編|工事不要で設置できる看板いろいろ



なんかさ、もっとこう……気軽に置ける看板ってないの?
壁に穴を開けたり、電気工事とかちょっとハードル高いんだけど。



もちろんあります。
ここまで紹介したのは外壁に取り付けるタイプでしたが、
「工事不要で設置できる看板」もたくさんありますよ。
テナントビルの共用部でも使えることが多いので、
小規模店舗やワンオペ店にはぴったりです。
| 看板タイプ | 特徴 | 費用目安 |
|---|---|---|
| タペストリー (布看板) | 壁やドア前に吊るすだけ。デザイン変更が簡単 主要メニューを掲示しよう | 5,000〜15,000円 |
| 手書きイーゼル看板 | チョークやマーカーで毎日メニュー更新できる 温かみを演出できる | 3,000〜10,000円 |
| スタンド看板 (自立型) | 電源不要の置き型サイン。通行人の歩く視線に合わせることで店前で存在感を出せる | 10,000〜30,000円 |
| のぼり旗 | 遠くからでも視認性抜群。通行人へのアイキャッチに激安店のイメージがあるのがネック | 2,000〜8,000円 |



オリジナル看板を制作してくれるネットショップもたくさんあって選ぶのが楽しいね。
これらがあるだけでなんかお店って感じがする…



はい。
特に「イーゼル看板」は一番簡単に“お店らしさ”を出せます。
チョークアートや手書きPOPで毎日のおすすめを出せば、
お客さんとの距離もぐっと近くなりますよ。



テナント店舗では“固定しない看板”を味方につけること。
撤去・移動が自由で、原状回復の心配も少ない。
しかも、毎日デザインを変えられる柔軟さがあります。
第4章|看板とファサードは“店の顔”──お客様の足を止めるデザインとは





ねえ所長、外装って結局どこまでいじるか悩むけど、
「看板とファサード」ってそんなに大事なの?



お店を一瞬で印象づけるのがこの部分なんですよ。
お客様は入る前に「なんとなく」お店の雰囲気を判断しています。
その“なんとなく”を形づくるのが、看板とファサードです。



統計的にも、初来店客の約6割は「外観を見て入店を決めた」と回答しています。
つまり、最初の5秒で“行ってみたい”を作れるかどうかが勝負です。
看板とファサードの役割
| 要素 | 目的 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 看板(サイン) | 店名・ジャンル・雰囲気を伝える | 遠視性・夜間照明・サイズ感 |
| ファサード | 店全体の「表情」を決める | 清潔感・素材統一・内装との連動 |
| 入口照明 | 夜間の視認性を上げる | 目線より高めに配置、温かみのある色味 |
| ウィンドウ演出 | 中の雰囲気を“チラ見せ” | 防犯と演出のバランス |



確かに、暗い入口とかよく見えない店ってちょっと入りづらいよな。



まさにそこです。
ファサードで一番大切なのは「入りやすさ」と「安心感」。
豪華さよりも、“明るくて清潔に見える”ことが最大の集客効果になります。



逆に、照明が強すぎたり、派手すぎるデザインは「安っぽく」見えることもあります。
特に女性客をターゲットにする店舗では、やさしい照度と素材感が好印象です。
| タイプ | 特徴 | 成功ポイント |
|---|---|---|
| ミニマル系(カフェ・ベーカリー) | 素材感と余白で魅せる | ウッド調+白看板+間接照明 |
| レトロ系(居酒屋・バル) | 温かみのある雰囲気 | 琺瑯看板+裸電球+暖簾 |
| ネオンサイン系(バー・夜業態) | 夜の通行人へ強く訴求 | LEDネオン+外照式ライト |
| ナチュラル系(定食・ランチ店) | 女性客・家族客向け | 植栽+ガラス開口+清潔感重視 |



なんか、業態ごとに“ハマる型”があるんだな。
たとえば、僕が居酒屋やるなら「レトロ系」かなぁ。



その場合、フォント選びも重要です。
明朝体よりも丸ゴシックや手書き風の文字が、温かみを出せます。



実際の看板デザインは「読む」より「感じる」ものなのです!
遠くから見ても何屋か伝わるように、色・文字・光の3兄弟を意識しましたらいいと思います!
ファサードを工事するときの注意点
| 注意点 | 理由 |
|---|---|
| ビル・自治体の規制確認 | 看板のサイズ・照明の明るさ・突き出し距離に制限がある |
| 原状回復を想定して設置 | 退去時に壁補修や撤去費が発生する可能性 |
| 電気配線の位置を事前に確定 | あとから照明追加すると内装工事に逆戻り |
| 素材の耐候性を考慮 | 風・雪・紫外線で劣化しやすい素材は避ける |



うーん、思ってたより奥が深い…。
でもやっぱり、看板ってお店の“名刺”みたいなもんだね。



その通り。
だから、内装デザインよりも先に“どんな顔で見せたいか”を決めることが重要です。



そのためなんですがね。
デザイナー任せにせず、オーナー自身の「世界観」を言語化しておくのが理想的なのです。
まとめ



さて、ここまでで「お店の外」をどう作るか、一通り見てきましたね。
外装工事って、じつは“見た目の勝負”じゃなくて“計画の勝負”なんです。
限られた条件の中でどこを見せ、どこにお金をかけるか。
この判断が、開業後の印象と集客を大きく左右します。



テナントなら「制約の中で魅せる工夫」。
路面店なら「自由と引き換えに発生する管理」。
どちらも正解ですが、目的をはっきりさせるのが大事です。
外観を立派にしても、中でオペレーションが回らなければお客はリピートしません。
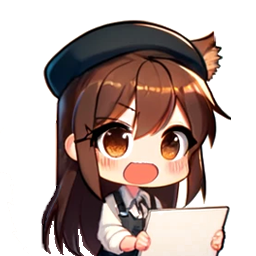
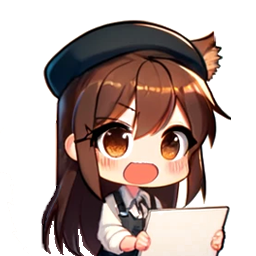
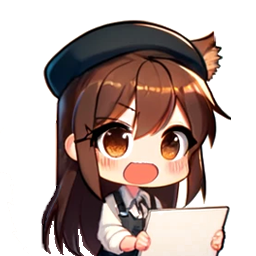
POSレジ、キャッシュレス決済、会計ソフト、セルフオーダー。
これらを上手に組み合わせれば、一人でもミスなく・速く・笑顔で回せる店がなります。



よし!ついにお店が完成したら内部の仕組みづくりだ!
僕の究極のワンオペ飲食店が完成する!!?
…あの子だれだっけ?