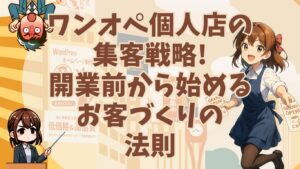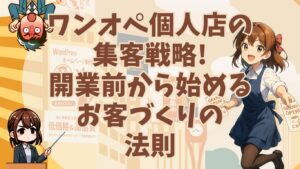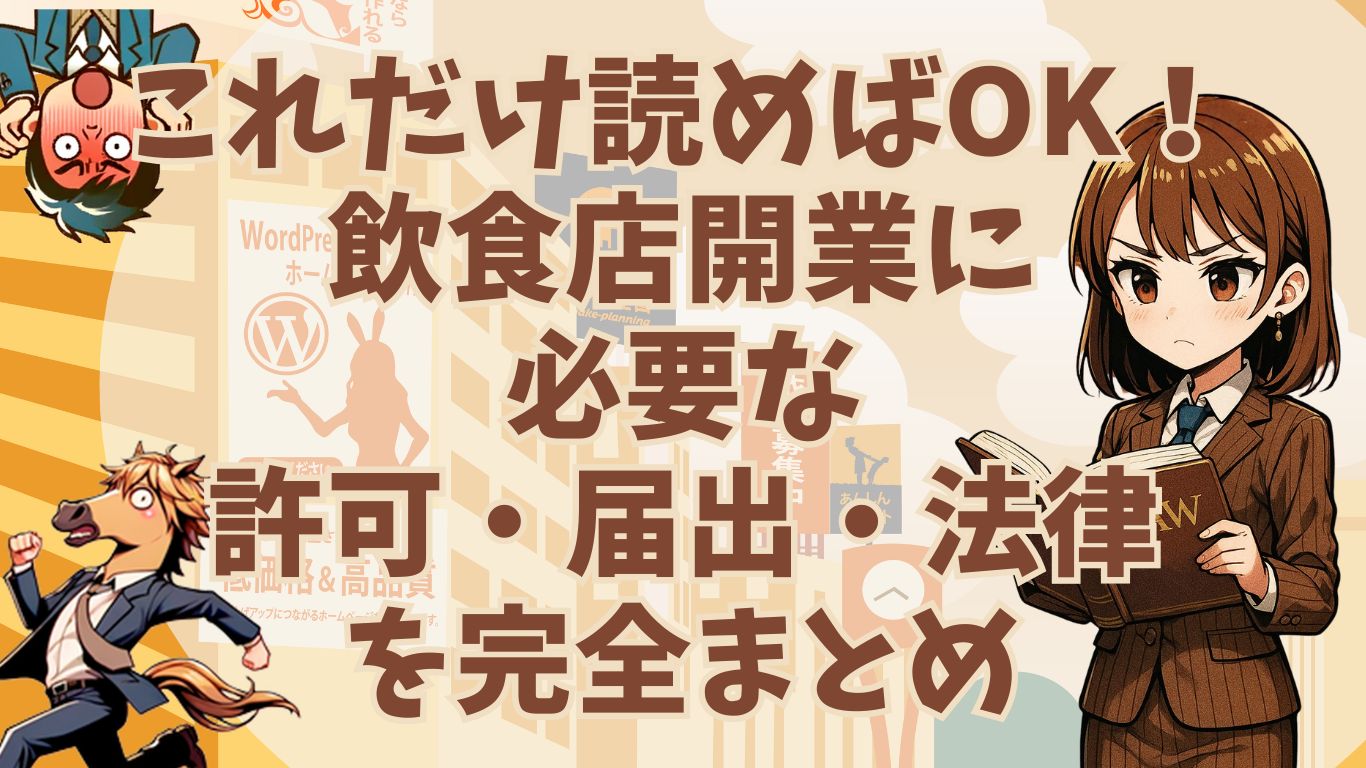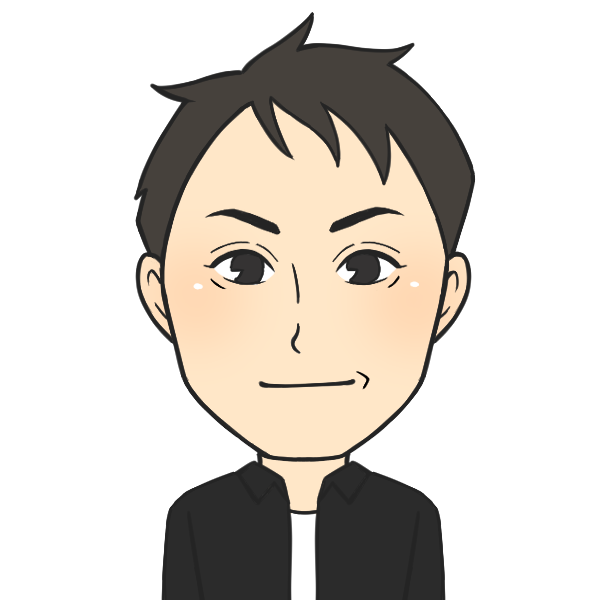甲斐承太郎
甲斐承太郎融資もおりて、テナントも契約して、いよいよ工事が始まったね……。
やっと少し落ち着けるのかな?



お疲れさまです、承太郎さん。
ここまで来たのは大きな一歩ですが――残念ながら、まだ“ひと山”残っています。
お店をオープンするには、営業の許可や各種届出が必要です。
これを終わらせないと、どんなに立派なお店でも営業はできません。
- 個人でお店を開業する際に必要な「許可」と「届出」の全体像がわかる
- 「誰に・いつ・どこに」届け出るのかの流れが理解できる
- 開業後も注意すべき法律(HACCP・景品表示法・労働関係法)まで一通り把握できる



営業を開始できるように、許可や届出をやる。
それが、今の段階でやるべきことです。
第0章|法律の基礎知識 ― 「許可」と「届出」の違いとは





僕みたいな一般人には、“許可”とか“法律”とか無縁でしょ?
別に知らなくてもいいよね?



たしかに、普段はあまり意識しないですよね。
でもね、開業した瞬間から、法律は“あなたの店の隣に座る同居人”になります。
……運転免許証をお持ちですね?



もちろん。車がないと仕事にならないし。



その免許証こそが、「許可」です。
本来、人は何を運転しようが、どこへ行くのも自由。
でも“車を動かす”という行為は危険だから、国が一度「禁止」にしている。
その禁止を解除する――それが「許可」です。



なるほど。自由だったはずの行為を、国が一度“ダメ”にして、それを“特別にOK”にしてるわけか。



そうです。
つまり、「許可」とは“自由の一時停止”を解除するための鍵なんです。
飲食店を開くことも同じ。
不特定多数の人間に食べ物を出す行為は、衛生上の理由で“原則禁止”。
その禁止を解除してもらうのが「飲食店営業許可」です。
生活の安全を守るための法律たち
| 行為 | 実は関係する主な法律 | 何のためのルールか(要点) | 主な管轄・窓口 |
|---|---|---|---|
| 車を運転する | 道路交通法 | 交通の安全・円滑の確保、免許制度の根拠 | 警察(運転免許は警察が所管) |
| 家を建てる・用途を変える(店舗化など) | 建築基準法(建築確認) | 構造・避難・耐火など基準適合の事前確認 | 建築主事/指定確認検査機関(自治体or民間) |
| ゴミを出す・事業系廃棄物を処理する | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) | 生活環境の保全・公衆衛生の向上(排出抑制・適正処理・マニフェスト等) | 市区町村(一般廃棄物の収集処理)/都道府県(産廃許可等) |
| 飲食店を営業する | 食品衛生法(営業許可) | 衛生基準の確保(施設基準・検査・営業許可) | 保健所(営業許可の担当) |
| 店内でお酒を提供する | 食品衛生法の飲食店営業許可(※酒類販売免許は不要) | 「提供」は飲食店営業の範囲。ボトル販売でなければ酒類販売免許は不要 | 保健所(営業許可) |
| 未開封の酒類を販売(テイクアウト/物販) | 酒税法に基づく酒類販売業免許 | 小売(ボトル等)には別途“販売免許”が必要 | 税務署(国税庁) |



こうして見ると、法律って「普段意識しないけど、生活を支えてるインフラ」みたいなもんだね。
ちゃんと整備されてるから、社会が秩序を保てる。
つまり、“知らなくても暮らせるけど、知らないと損する”やつか。



まさにその通り。
飲食店オーナーになった瞬間、あなたは“経営者”であり、
同時に“法律の当事者”になります。
法律の基礎知識
| 用語 | ざっくり言うと | 例 | ニュアンス |
|---|---|---|---|
| 許可 | 禁止されていた行為を「特別にやってよい」と認める | 飲食店営業許可、運転免許 | 「やってもいいよ」 |
| 届出 | 「やります」と報告するだけ(審査なし) | 開業届、深夜酒類提供飲食店営業届出 | 「言っておけばOK」 |
| 認可 | すでに成立した契約などに法的な力を与える | 電気代の値上げなど | 「行政が承認して初めて有効」 |
| 確認 | ルールに適合しているか事前にチェック | 建築確認申請 | 「事前にチェックを受ける」 |



つまり、「許可=特別な鍵」「届出=やる報告」くらいに覚えておけば十分です。



重要なのは、“許可をもらうまでは禁止されている”という意識です。
その感覚があるかどうかで、開業後のトラブル率が変わります。



じゃあ、工事中の店も、まだ“法律的にはただの部屋”ってこと?



正確です。
営業許可を取るまでは、厨房があっても、そこは「飲食店」ではありません。
開店までに必要な“許可・届出のストーリー”を、次章で整理していきましょう。
第1章|個人事業として必要な届出





営業許可が必要なのはわかったけど……他にやることあるの?
お店を作って、保健所の許可を取れば終わりじゃないの?



それがまだあるんですよ。
お店を“営業”する前に、まずはあなた自身の登録が必要です。



今回は多くの開業オーナーが選ぶ、
“個人事業主”としての届出を整理しましょう。
【個人事業主になるための基本届出】
| 書類名 | 提出先 | 提出期限 | 内容・ポイント |
|---|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 税務署 | 開業から1か月以内 | “事業主として登録”されるための届出。屋号(お店の名前)もここで記載。 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 税務署 | 開業から2か月以内 | 節税メリットのある青色申告を使うための申請。確定申告で最大65万円控除。 |
| 事業開始等申告書 | 市区町村 | 開業後すぐ | 住民税や事業税の算定に必要。出さないと税金計算がズレることも。 |



お店をスタートさせるために必要なのは、
税務署と市町村への届出です。
これが「事業を始めます」という最初の宣言になります。



この3つを出しておくと、「税金上も正式にお店を開いた人」として登録されます。
簡単に言えば、“法律上の自分の立ち上げ”です。
【屋号と商号】お店の「名前」にも種類がある



屋号?僕は別に屋台をやりたいわけじゃないんだけどな…



屋台の“屋”とは関係ありません。
屋号とは、個人事業主としての“お店の名前”のこと。
税務署に開業届を出すときに記入する“営業上の呼び名”です。



つまり、屋号はあなたが商売をするときに名乗る「看板名」。
「〇〇食堂」「△△カフェ」「こやけ企画」など、自由に付けられます。
【屋号・店舗名・商号の違い】
| 名称 | 使う人 | 法的扱い | 登録の有無 |
|---|---|---|---|
| 屋号 | 個人事業主 | 任意(自由) | 開業届に記載するだけでOK |
| 商号 | 法人・会社 | 法的に保護される名称 | 法務局で登記が必要 |
| 店舗名 | お客様に見せる店名 | 法的制限なし | 看板・SNS・広告で使用 |



屋号は“個人での営業名”なので、たとえば「脱サラ食堂」として登録しても、実際の看板には「ラーメン脱サラ」と出しても構いません。
でも、銀行口座を作るときや請求書を出すときには屋号が正式名称になります。
商号登記の話(将来の法人化を見据えるなら)



商号っていうのも聞いたことあるけど、屋号と何が違うの?



商号は“登記された正式な社名”のことです。
会社をつくるときには「株式会社〇〇食堂」のように必ず登記が必要になります。



個人事業主の屋号は登記義務がないので自由に名乗れますが、商号登記をすると次のようなメリットがあります。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 社会的信用が上がる | 法務局に登録されることで、事業実体を公的に証明できる |
| 屋号付き銀行口座が開設できる | 「〇〇食堂 代表 さとう はじめ」といった名義での口座開設が可能 |
| 屋号を法的に保護できる | 他人に同じ名前を使われにくくなる |
| 将来の法人化がスムーズ | 同じ商号で法人設立しやすくなる |



法律的に自由とはいえ、名前選びは慎重に。
ポイントは以下の3つです。
- 覚えやすく短くする:3〜4文字程度が理想。口コミで広がりやすい。
- 業態を入れる:「〇〇ラーメン」「△△カフェ」などで一目で業種が伝わる。
- 地域名を入れる:「札幌食堂」「旭川バル」など、検索・認知に強い。



なるほどね。屋号は自由だけど、商号にすれば信用力も上がるのか。



ええ。最初は屋号だけでも問題ありません。
でも、もし本格的にブランドを育てたいなら、商号登記も検討しておくと良いでしょう。
第3章|お店を営業するために必要な主な許可



そんなわけで開業届も出したし、これでもう“開業”って言っていいんだよね?



まだ半分です。
開業届は“あなた自身”を登録しただけ。
これからは“お店そのもの”を動かすための許可が必要になります。



つまり、事業主としては「人の届出」と「お店の許可」、この2段構えで一人前。
【営業許可の基本構造】
| 区分 | 管轄 | 目的 | 要点(HUB向けに簡潔) |
|---|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 保健所 | 食の安全確保 | 店内で調理・提供する業態の基本許可。厨房区画、手洗い設備、給湯、水回り等の基準に適合が必要。 後述の製造業許可と役割が異なる。 |
| 深夜酒類提供飲食店営業(届出) | 警察署(経由で公安委員会) | 深夜帯の治安・風紀維持 | 0時以降に「主として酒類を提供」して営業するバー等は許可ではなく届出制。 接待・遊興は禁止(やるなら1号等の許可が必要)。 構造・標識・年少者立入等のルールあり。 |
| 風営法の許可(接待・低照度・区画席) | 警察署(公安委員会の許可) | 接待行為や構造による風紀・安全管理 | 代表的に1号=接待を伴う飲食店(キャバクラ等)、2号=低照度飲食店(照度基準あり)、3号=区画席飲食店(パーテーション・個室の構造要件)など。該当すると許可制・営業時間制限等がかかる。グレーな「個室・暗い・接待っぽい」は図面を持って生活安全課へ事前相談が確実。 |
| 製造業許可(そうざい製造業・菓子製造業 など) | 保健所 | 包装・製造の衛生確保 | 弁当・総菜を継続的に製造販売する、菓子を製造する等は「飲食店営業」と別の製造業の“許可”区分。2021年改正で許可・届出・登録に整理され、そうざい/菓子は許可区分に属する。テイクアウトだけなら常に製造業許可は不要 |
| 酒類販売業免許 | 税務署(国税) | 酒類流通の適正化 | 未開栓ボトルの販売(店頭・EC)は免許が必要(小売、通信販売小売など)。店内提供(グラス売り)は対象外。 |
1.飲食店営業許可:すべてのスタート地点



“営業許可”ってつまり、これのこと?



そう。飲食を扱う以上、最初にここを通らないと始まりません。
厨房・手洗い・給水・排水などの構造が基準を満たす必要があります。



施工途中の図面を持って保健所に事前相談するのが鉄則。
完成後にNGが出ると、壁やシンクの作り直しになるケースもあります。
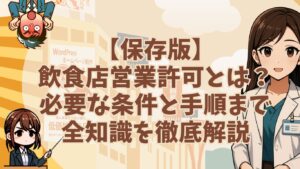
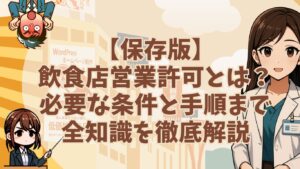
2.深夜営業をするなら「深夜酒類提供届出」



たとえば夜の1時くらいまでは営業したいけど、それも許可がいるの?



“許可”ではなく“届出”ですね。
0時以降にお酒を出すお店は、警察署に届出が必要です。
他にも条件があります。
照度(明るさ)は10ルクス以上、接待行為は禁止、
構造上の視認性(見通せる店内)も求められます。
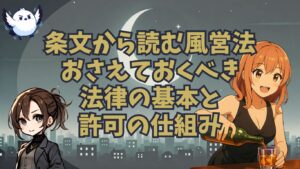
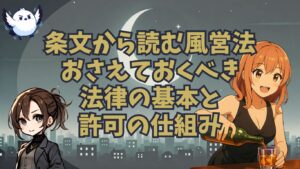
3.風営法の範囲に入る場合



風営法?接待?
接待って、どこからが“接待”になるの?



お客の隣に座って会話や遊戯で“もてなす”行為をすべて指します。
キャバクラやスナックのように、客と密接に接する接待をする場合は、
警察の風俗営業許可(1号営業)が必要になります。



一方で、個室や暗室など“構造”で該当するケースもあります。
区切られた鍵付き個室で飲食を提供すると、
「第3号営業(区画席飲食店)」に分類されることもあります。
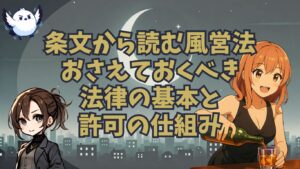
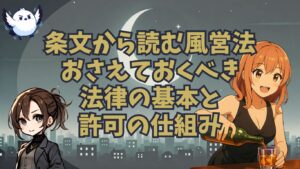
4.製造・販売を兼ねるなら“製造業許可”



将来的にECサイトで通信販売やお弁当販売もやりたいんだけど、同じ許可でいける?



それはそうざい製造業許可や菓子製造業許可の範囲です。
厨房で調理したものをテイクアウト販売する程度なら飲食店営業許可でOKですが、パック詰めして販売・卸す場合は製造業扱いになります。



「店内調理・その場で提供」と「まとめて製造・販売」は別物。
HACCP対応の設備基準も必要になります。


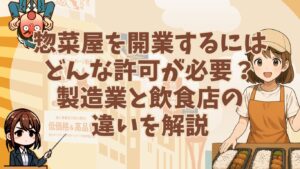
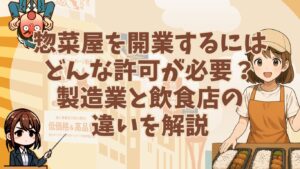
5.お酒を“売る”なら税務署の免許



うちのお店ではお酒の提供もする予定だけど…
もしかしたら酒類販売免許って必要じゃないの?



お店で開封、ビンとグラスを一緒に提供して店内で消費するなら飲食店営業許可で十分です。
しかし、開封していないお酒を販売するには、酒類販売業免許が必要です。
これは保健所ではなく税務署の管轄です。
| 区分 | 正式名称 | できること(ざっくり) |
|---|---|---|
| 小売 | 一般酒類小売業免許 | 店頭で一般消費者へ販売(未開封品)。 |
| 小売 | 通信販売酒類小売業免許 | EC・電話受注などの通信販売で一般消費者へ販売。 |
| 卸売 | 酒類卸売業免許(種別あり) | 事業者(小売店・飲食店など)向けに卸販売。種別:全酒類卸、ビール卸、洋酒卸、輸入酒類卸、店頭販売酒類卸ほか。 |



販売する種類(ビール・ワイン・日本酒など)によって審査内容も異なります。
“飲ませる”と“売る”は別のライセンス、と覚えておきましょう。
【まとめ】
| 覚える順番 | 内容 | 管轄 |
|---|---|---|
| ① 飲食店営業許可 | 調理・提供するための基本許可 | 保健所 |
| ② 深夜酒類提供届出 | 0時以降にお酒を出す場合 | 警察署 |
| ③ 風営法許可 | 接待行為・構造で該当する場合 | 警察署 |
| ④ 製造業許可 | 惣菜・菓子など製造販売する場合 | 保健所 |
| ⑤ 酒類販売業免許 | 開封していないお酒を販売する場合 | 税務署 |



お店を作るときは「どんな商品を、どんな時間に、どんな形で提供するか」で必要な許可が変わります。
迷ったら“どの法律に関係しているか”で整理するといいです。
食品衛生法、風営法、酒税法――名前が違えば、管轄も別。
第4章|施設に対して必要な許可と届出





保健所の人に許可についてはもう聞いたし、内装工事が始まったらもう安心でしょ?



まだです。
お店の“中身(営業内容)”の前に、“箱(建物)”そのものが法律に合っているかを確認しなければなりません。
これを怠ると、せっかくの工事が全部やり直しになることもあります。



順番を整理しておきましょう。
お店をつくるときに必要なのは、建築基準法 → 消防法 → 食品衛生法の流れです。
1.建築確認申請



“建築確認”って何なの?
出さなきゃダメなの?



実は…
ワンオペ飲食店のような10坪前後の小規模店舗なら、
ほとんどの場合、建築確認は不要です。
必要になるのは“建物全体の構造を変える”か、“大規模(100㎡超)”のときだけ。
| 建築確認が必要なケース | 建築確認が不要でOKなケース |
|---|---|
| 建物の用途を変える (例:倉庫→飲食店、事務所→カフェ) | 以前も飲食店だった居抜き物件をそのまま利用する |
| 改装部分が100㎡(約30坪)を超える | 10坪前後の小規模店舗で、改装面積が小さい |
| 柱・壁を撤去するなど構造を変更する | 内装リフォームのみ (カウンター・壁紙・照明の交換など) |
| 耐火区画や避難経路をいじる | 既存の構造を活かして使う(動線・区画を変えない) |
| 複数階建ての建物で1階を店舗化 | 平屋・単独店舗で営業する |
| 倉庫や事務所など、飲食用途以外からの転用 | 厨房やトイレなどの配置を変えない軽改装 |
| 新築・増改築を伴う工事 | 既存の飲食店舗の再利用(構造に手を加えない) |
2.消防署への届出・検査



これも、10坪以下の飲食店なら別に必要ない…



必要です。
飲食店は火気を扱うため、「消防法」の適用対象になります。
オープン前には防火対象物使用開始届出書を提出し、消防職員の現地検査を受けます。
| 届出名 | 誰(提出者) | いつまでに | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 防火対象物使用開始届出書 | 建物を使用しようとする者 (飲食店オーナー、または物件所有者) | 使用開始日の7日前まで。 | 所管の消防署 (建物所在地を管轄) |
| 防火対象物工事等計画届出書 | 工事を行う者 (飲食店オーナー+工事を行う側) | 工事着手の7日前まで。 | 所管の消防署 |
| 火を使用する設備等の設置届出書 | 設置を依頼する者 (建物所有者・飲食店オーナー等) | 設置予定の7日前まで (地域により) | 所管の消防署 |
| 消防用設備等設置届出書 | 設置後の所有者または使用者 | 設置後4日以内の場合あり (自治体による) | 所管の消防署 |



特に内装工事でレイアウトを変える場合、防火区画や避難動線が変わると再検査が必要になります。
工事の後に慌てるより、設計段階で消防に相談しておくのが早道です。
3.保健所の検査(営業許可前の現地確認)



最後は保健所だね。ここで営業許可をもらうんだよね?



はい。ただし、保健所の検査は建築・消防の確認が終わってからです。
シンクの数や給湯・排水など、衛生面の基準をすべて満たしているかが確認されます。
チェックリストの一例を挙げると――
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 手洗い・食器洗いのシンク分離 | 種類ごとに用途を区分 |
| 温水の供給 | お湯が出るか確認 |
| 害虫侵入防止 | 網戸・ドアクローザーの有無 |
| 清掃・保管スペース | 調理場の衛生動線 |
| 食品衛生責任者の資格証 | 有資格者が必ず常駐 |
第5章|開業後にも知っておきたい法律





よっしゃ!完全に理解した。
これで法律は完璧だな



おっと油断は禁物です。
お店がオープンしてからが、本当の“法律との付き合い”の始まりです。



営業許可は“スタートライン”。
ここからは“維持と管理”がテーマになります。
1.お店の“衛生管理”に関係する法律
食品衛生法(+HACCP)
- 食材の温度管理
- 手洗い・調理器具の洗浄消毒
- 冷蔵・冷凍庫の温度記録
- 従業員の健康チェック



これらを「記録して残す」ことが大切です。
「やっている」だけでは不十分で、「証拠として残す」がHACCPの考え方。
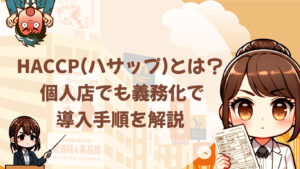
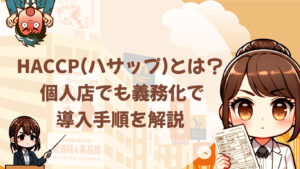
食品リサイクル法
- 廃油は専門業者へ引き渡し(マニフェスト保管)
- 食材ロスは極力減らす工夫を
- 定期的な廃棄伝票の保管が必要



ゴミであっても、処理の証拠が残る書類は大切な法的記録になります。
2.営業上で気を付けたい“落とし穴”法律
特定商取引法
個人情報保護法
- 顧客データの保存・管理ルールを明確化
- 委託業者(POS・クラウドサービス)と契約書を締結
- 情報漏洩が起きた場合は報告義務あり



データ管理も“お客様を守る衛生管理”と同じくらい重要です。
景品表示法



景品表示法!なんかよく聞くわ!でも飲食店に関係あるの?



例えば開店イベントで“くじ引き”とか“無料ドリンク券”を配るなどの宣伝活動が該当してしまう可能性があります。



実は、そこにもちゃんと法律の制限があるんです。
お客さんをだますような宣伝や、過剰な景品を配るのを防ぐために定められているのが景品表示法(けいひんひょうじほう)。
- 目的:誇張広告や過剰な景品で消費者を誤解させないためのルール
- 根拠:景品表示法第4条(優良誤認・有利誤認の禁止)
| 区分 | 内容 | NG例 |
|---|---|---|
| 優良誤認表示 | 実際より品質が優れていると誤解させる | 「日本一の味」「無添加100%(実際は一部添加物あり)」 |
| 有利誤認表示 | 実際より価格・条件が有利と誤解させる | 「今だけ半額!(常に同価格)」「他店より3割安い!(根拠なし)」 |
例えばこんな感じ
| 景品タイプ | 上限金額 | 例 |
|---|---|---|
| もれなく景品(総付景品) | 取引額1,000円未満→200円まで/1,000円以上→20%まで | 来店特典・ドリンク券など |
| 抽選など(懸賞景品) | 取引額5,000円未満→20倍まで/5,000円以上→10万円まで | くじ・SNSキャンペーン |
| 商店街など共同企画 | 30万円まで | 商店街スタンプラリーなど |



広告の自由を守りつつ、お客様の誤解を防ぐためのルールです。
「うちは誠実にやってます」が、いちばんのブランドです。
“日本一”より、“うちだからできる味”を言葉で伝えたほうが、ずっと説得力があります。
食品表示法
- 原材料名
- 消費期限・保存方法
- アレルギー表示
- 製造者名(または販売者名)
3.接客に関する法律(風営法)



え?風営法って夜のお店だけの話でしょ?



いえ、飲食店でも構造・照度・営業時間によって該当する場合があります。
知らずに営業していると“無許可営業”扱いになることもあるので注意が必要です。
| 区分 | 区分 | 主な内容 | 該当例 | 手続 |
|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 接待飲食等営業 | 接待行為を伴う | 歌声喫茶、高級料亭など | 許可制 |
| 第2号 | 低照度飲食店営業 | 客席照度が10ルクス以下 | ムーディーなカフェなど | 許可制 |
| 第3号 | 区画席飲食店営業 | 見通し困難かつ5㎡以下の個室で飲食提供 | 完全個室焼肉・鍵付き個室カフェなど | 許可制 |
| – | 深夜酒類提供飲食店営業 | 午前0時以降に酒類を提供(接待なし) | 居酒屋、立ち飲み屋など | 届出制 |



「うちは普通の居酒屋だから関係ない」と思っていても、
図面の構造や照明計画によっては、2号や3号に該当することがあります。
- 店内の照明を落とした落ち着いた雰囲気のカフェ(10ルクス以下)
- 他の客席から見通せない完全個室の飲食スペース(5㎡以下)
- アルコール提供をメインに提供する飲食店で0時を過ぎても酒類提供を続ける店舗



つまり、風営法は「夜の店」だけのものではありません。
個室・暗室・深夜営業・接待行為・特定遊興、この5つのうちどれかに触れたら要チェック。
まずは警察署(生活安全課)で図面相談しておきましょう。
4.従業員を雇うときに関係する法律



将来的に売上が安定して、オーナーの負担を減らすために従業員を雇うこともあるかもしれません。
そのときに慌てないよう、最低限の労務ルールは覚えておきましょう。
| 保険・制度名 | 目的・内容 | 加入義務があるケース | 届出・提出先 |
|---|---|---|---|
| 労災保険(労働者災害補償保険) | 業務中・通勤中のケガ・病気・死亡の補償 | 従業員を1人でも雇った時点で義務 | 労働基準監督署 |
| 雇用保険 | 失業・育児休業・介護休業などの生活保障 | 週20時間以上・31日以上雇用見込みのスタッフを雇う場合 | ハローワーク |
| 健康保険・厚生年金(社会保険) | 医療・年金の保障。正社員基準のスタッフが対象 | 常時2人以上の従業員を雇用、または法人事業主の場合 | 年金事務所 |
| 青色事業専従者給与届 | 家族に給料を払うときに経費として認めてもらう | 家族が事業に専念して働く場合(青色申告者のみ) | 税務署 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与を支払う事業所として税務署に登録 | 従業員や家族に給与を支払うとき | 税務署 |
| 源泉所得税の納期の特例申請 | 給与の源泉税を半年ごとにまとめて納付できる制度 | 従業員が常時10人未満 | 税務署 |



保険や届出は“人を雇った瞬間”に始まります。
ワンオペのうちは関係ないように見えても、最初のアルバイト採用時に一気に関係してきますよ。



つまり、「人を雇う=保険と税のセット」。
放置するとペナルティ対象になるので、ハローワーク・年金事務所・税務署の3か所はセットで動くのが鉄則です。
おまけ|個人事業主(オーナー本人)の保険と年金



なんか、従業員ってこんなに保険で守られてるんだね。
僕自身の保険はどうなっちゃうの?



オーナー本人は「会社に雇われていない」ので、自分で入る保険が基本です。
働き方が変わると、入る制度も変わるんですよ。
| 区分 | 内容 | 管轄 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 病気・ケガの治療費を補助する保険 | 市区町村 | 会社の健康保険を抜けたら自動的にこちら。所得に応じて保険料が決まる。 |
| 国民年金 | 将来の年金を受け取るための基礎制度 | 日本年金機構 | 会社員時代の厚生年金より少額だが、任意で上乗せ(国民年金基金・iDeCo)も可能。 |
| 国民年金基金/iDeCo | 老後資金を自分で積み立てる制度 | 国民年金基金連合会など | 掛金が全額所得控除になるので節税効果も大。 |
| 小規模企業共済 | 退職金の代わりになる共済制度 | 中小機構 | 廃業・引退時にまとまったお金を受け取れる。こちらも節税効果あり。 |
| 任意労災保険(特別加入) | 自営業者本人も労災補償を受けられる制度 | 労働基準監督署(労働保険事務組合経由) | 配達・厨房作業など危険業務なら検討の価値あり。 |
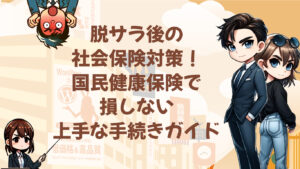
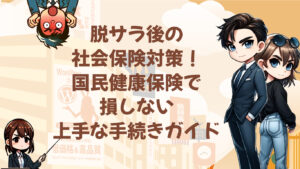


まとめ



ここまでで、“飲食店を始めるときに関係する法律”の全体像が見えましたね。
ポイントは、どの法律も「お店を縛るため」じゃなくて、お客様と自分を守るためにあるということです。
届出や許可、衛生管理や表示ルールも、ひとつひとつが信頼を積み重ねる行為なんです。



・開業前は「自分に関する届出」(開業届・屋号など)
・営業開始時は「お店に関する許可」(飲食店営業許可など)
・開業後は「運営に関する法令」(衛生・風営・労務など)
この3段階を整理すれば、何をいつやるか迷いません。
知らないまま始めるより、“知って始める”ほうが、結果的に自由に経営できます。



これでお店も完成間近!
営業許可を取ったらあとは扉を開くだけ!!
…開けたら誰もいなかったらどうしよう。ってことでこの記事