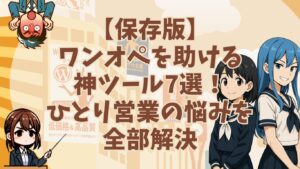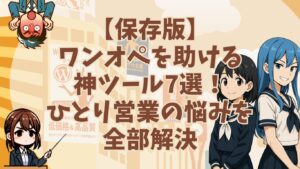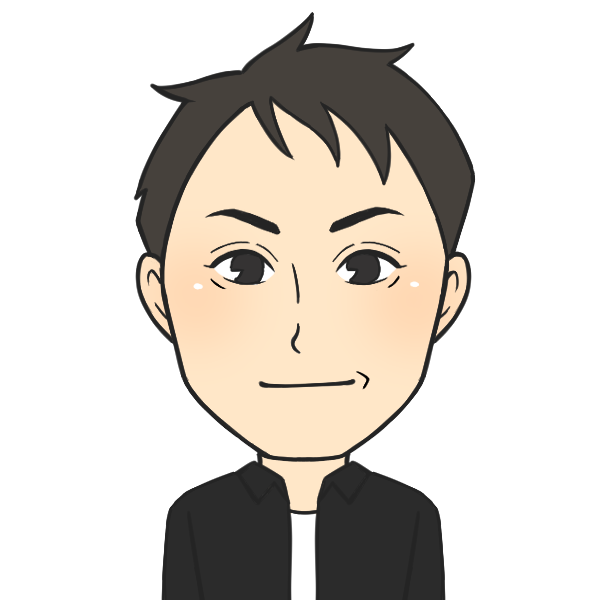甲斐承太郎
甲斐承太郎ついにお店が工事も終わって、完成したぞ!
さあ、ここから理想のお店を作り上げるんだ!
……あれ? テーブルだけでもいろんな高さや大きさがあるんだな。
どれを選べばいいの? どんなのが正解なんだ?



ふふ、いいところに気づきましたね。
実は、いつも何気なく利用しているお店でも、「居心地がいい」「おしゃれに見える」「落ち着く」と感じる理由はすべて“設計”にあります。
照明の明るさ、テーブルの高さ、椅子の座面の角度、食器の色――
これらはすべて“演出”として計算されているんですよ。
つまり、工事が終わっても“お店づくり”はまだ終わっていません。
ここからは、見た目と使いやすさを融合させる最終仕上げのステージです。
- 家具・照明・BGMなど、店内演出の基本構成が理解できる
- テーブルやイス、照明の高さや配置で売上・回転率を変える方法がわかる
- 清潔感を保つ「クレンリネス設計」で、長く愛される店舗づくりができる



店内演出とは「感覚の設計」。
家具・照明・音・清潔感――すべてが連動して、
「このお店、なんか落ち着く」と思わせる空間を作り出します。
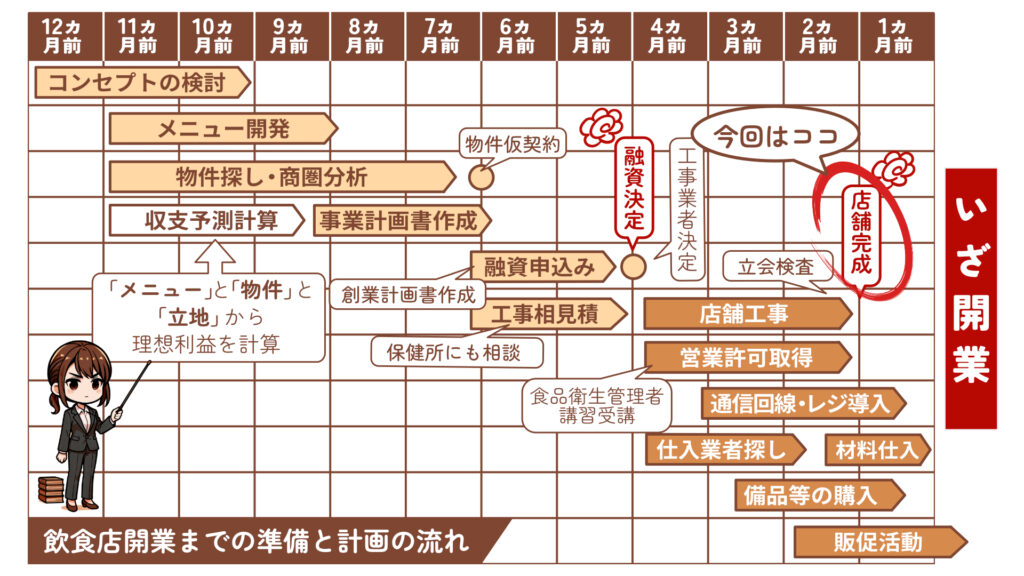
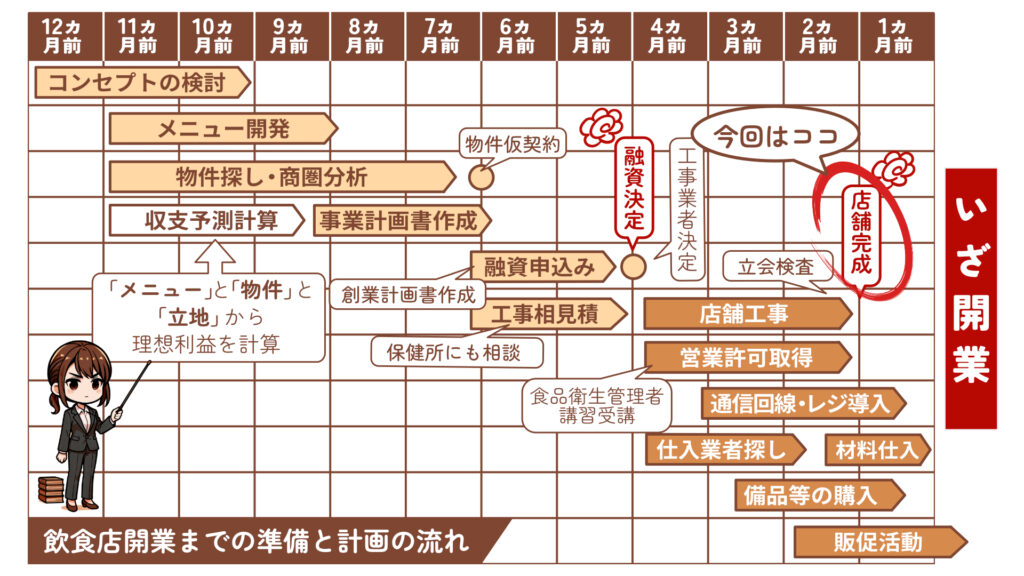
第1章|業態で全然違う厨房設備の選び方





さて、図面も出来上がったから購入する厨房機器を決めないとね!
って、あれ?いざ道具を揃えようとすると、種類が多すぎてわからないぞ…。
冷蔵庫だけでも業務用・家庭用・縦型・コールドテーブルって、どれを選べばいいんだ?



その悩みは当然です。
厨房設備は“お店の業態”によって必要なものがまるで違います。
ラーメン店なら大型のガスレンジと製麺機、カフェならエスプレッソマシン、居酒屋ならフライヤーと冷蔵ストッカー――。
つまり、「何を出すか」=「どんな設備が必要か」なんです。



厨房設備は「商品動線」に合わせて選びましょう。
仕入れ → 保存 → 調理 → 盛付け → 提供、この流れを止めない配置こそ、ワンオペ店の効率を決めるカギです。
厨房設備の主な種類と役割
| 区分 | 主な機器 | 役割・ポイント |
|---|---|---|
| 加熱機器 | ガスレンジ・フライヤー・グリドル | 主力メニューに合わせて火力を選ぶ。電気 or ガスはランニングコストで判断。 |
| 冷却機器 | 冷蔵庫・冷凍庫・コールドテーブル | 仕込み量と回転率を基準に容量を選定。背の高い縦型より、作業台兼用型が便利。 |
| 洗浄・衛生機器 | シンク・食洗機・手洗器 | 保健所の基準を満たす数を確保。特に手洗器は独立設置が必須。 |
| 換気・排気設備 | フード・ダクト・換気扇 | 油煙・臭い対策に必須。ワンオペ厨房では空気の流れも作業性に直結。 |
| その他 | 作業台・棚・ストッカー | 作業スペースは“1人分の動線”を意識して確保。収納を上手に設計。 |



こうして見ると、必要なものって意外に多いな…。
でも、予算とのバランスを考えると全部は揃えられないかも。



その通り。
最初から完璧を目指すより、「最低限+成長の余地」で考えるのが現実的です。
特にワンオペ店では、冷蔵庫やシンクの配置を工夫すれば
高価な機器を増やさなくても十分回せる場合があります。



つまり、機器を増やす前に“配置の最適化”が最優先ということ。
図面段階で決めるべきポイントを整理しましょう。
厨房設計で決めておくべきポイント
| 項目 | 内容 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 給排水位置 | シンク・食洗機の設置場所 | 延長工事が必要か。傾斜や詰まりに注意。 |
| ガス容量 | 加熱機器の同時使用量 | 使用予定機器の合計出力を業者と確認。 |
| 電源容量 | 電気機器・照明の消費量 | ブレーカーの容量不足に注意。 |
| 換気計画 | フード位置・吸排気バランス | 油煙と臭気の排出方向を確認。 |
第2章|テーブルとイスで価値の提供を管理
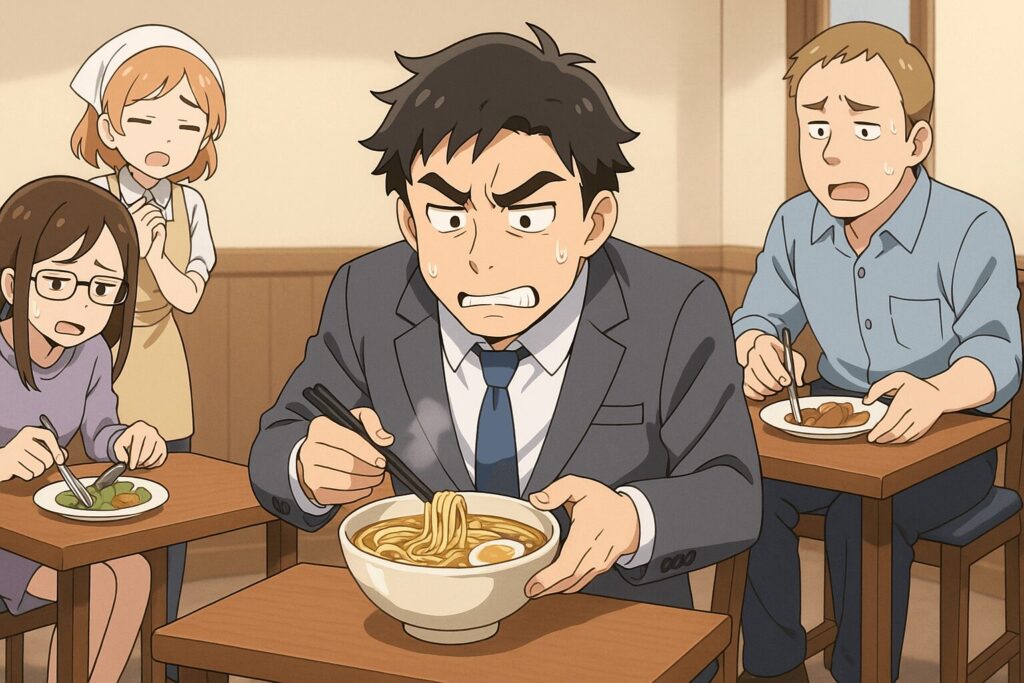
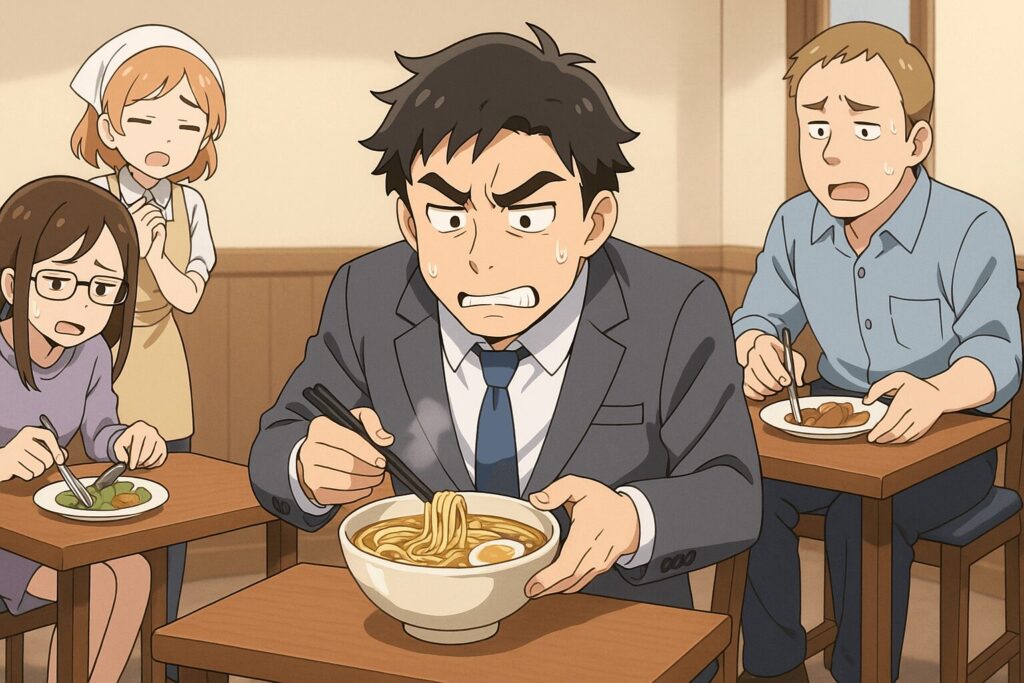



やっとお店が完成したけど、テーブルの高さとか椅子の種類ってどうやって決めればいいんだ?
見た目のバランスだけで選ぶと失敗するのかな?



そうですね。家具の高さやバランスは、お客様の滞在時間や回転率、リピート率にも影響します。
単なるデザインではなく、“業態に合わせた高さの設計”が大切です。
テーブルと椅子の基本バランス



飲食店では「テーブルの高さ−椅子の座面高=25〜30cm」が基本バランス。
この差が狭すぎると食事がしづらく、広すぎると落ち着かない印象になります。
| 業態 | テーブル高(床〜天板) | 椅子の座面高(床〜座面) | 高さの差 | 特徴・用途 |
|---|---|---|---|---|
| 一般的な飲食店・カフェ | 700〜730mm | 400〜450mm | 約250〜300mm | 食事中心。長時間座っても疲れにくい |
| バー・スナック | 500〜600mm | 360〜400mm | 約150〜200mm | ドリンク中心。くつろぎ重視 |
| カウンター席(食事メイン) | 950〜1000mm(カウンター) | 650〜700mm | 約250〜300mm | 立ち座りしやすく、会話しやすい高さ |
| 掘りごたつ席 | 700mm前後(床〜天板) | − | 約300mm(座面差) | 足を下ろせる構造で食事しやすい |
| ソファ席(料理提供) | 600mm前後 | 350mm前後 | 約200〜250mm | 食事対応。カフェやレストランに多い |
| ソファ席(ドリンク中心) | 350〜400mm | 350mm前後 | 約150〜200mm | ゆったりとした滞在型空間に最適 |
- ラーメン店や焼肉店:器が高いので、椅子を3cmほど高く設定すると食べやすい。
- カフェ・タピオカ店など:ドリンク中心なら、椅子を少し低くすると落ち着きが出る。
- バー業態:あえて高めのカウンターとスツールを使い、会話のしやすさを演出する。
席種を増やすときのポイント



業態別に最適化しつつも、高さの統一感を保つことが大切です。
高さを揃えると、席をくっつけたり離したりして柔軟なレイアウト変更が可能になります。
| 座席タイプ | 高さ統一のメリット | 注意点 |
|---|---|---|
| テーブル席 | 団体対応しやすい | テーブル脚の安定性を優先 |
| カウンター席 | 作業動線を維持 | 客席側と厨房の目線を意識 |
| ソファ席 | 滞在時間をコントロール | 座面の沈み込みを考慮する |
- カウンターを優先:厨房から提供・回収がしやすく、ワンオペ運営に最適。
- 2人掛けテーブル中心に:組み合わせ次第で少人数・団体どちらにも対応可能。
- ベンチシートを片側に設置:壁側スペースを有効活用でき、席稼働率が上がる。
- 安定感のあるテーブル:ぐらつき防止で顧客のストレスを軽減。
- 音がしない椅子:金属脚の擦れ音は不快印象を与えるため要注意。
- 素材の統一感:木・スチール・ファブリックなど、店舗コンセプトに合わせて統一。



つまり、“見た目のデザイン”よりも“動作のしやすさ”を優先するのが正解。
高さの誤差3cmでも印象が変わるのは、人間工学的にも実証されています。



はい。家具の寸法を「居心地」と「回転率」の両面から設計するのが、
ワンオペ飲食店の成功を支える店舗デザインの基礎なんです。
テーブルの形状で変わる印象と回転率



同じテーブルでも、「形」だけでお客様の滞在時間やお店の印象が変わります。
ワンオペ飲食店では、レイアウト効率と雰囲気づくりのバランスが重要です。
| 形状 | 特徴 | メリット | デメリット | 向いている業態 |
|---|---|---|---|---|
| スクエア型(四角形) | 最も一般的なタイプ。2人掛け・4人掛けを組み合わせやすい。 | ・スペース効率が高い ・テーブル同士を連結しやすい ・動線が取りやすい | ・角があるため圧迫感が出やすい ・対角線上の人と目が合いにくい | 居酒屋、定食屋、カフェ、ファストフードなど |
| ラウンド型(円形) | 柔らかい印象を与え、会話がしやすい形。 | ・親しみやすい雰囲気 ・目線が中心に集まり会話が弾む ・角がないため安全 | ・スペース効率が悪い ・複数台設置が難しい | バー、喫茶店、家族層向けレストランなど |
| 楕円・変形型 | 柔らかさと動線効率を両立。 | ・空間にリズムを与えやすい ・個性を出しやすい | ・既製品が少なくコスト高 | デザイン性重視のカフェやバル |



つまり、「おしゃれな形を選ぶ」じゃなくて、“どう使いたいか”から逆算するのが正解です。
スクエア型は回転率を、ラウンド型は会話や雰囲気を重視するお店に向いています。
ワンオペ店におすすめの形状バランス



なるほどな〜。じゃあ、うちの10坪ワンオペ飲食店ではどっちがいいんだ?



ワンオペの場合は、スクエア型を中心に一部ラウンド型を組み合わせる構成がおすすめです。
これにより、回転率・雰囲気・動線の三立てが実現できます。
- メイン席:2人掛けスクエア型 × 3〜4台(結合可能タイプ)
- 壁際:ベンチシート+スクエア型(動線を確保)
- 入り口付近や単客向け:小型のラウンドテーブル(柔らかい印象を演出)



補足ですが、ラウンド型は空間を広く見せる効果もあるため、狭い店ほどアクセントに一つ入れると“抜け”が生まれます。
視覚的なゆとりを作る設計テクニックですね。
結論:テーブルは「形+高さ」で設計する



つまり、テーブル選びは“デザイン”ではなく“戦略”です。
高さは業態に合わせて、形はお客様の心理と動線に合わせて決めましょう。
形・高さ・配置を計算しておけば、内装費を抑えながらも「プロっぽい空間」に仕上がります。
イスの種類と印象の違い
| 種類 | 特徴 | 与える印象 |
|---|---|---|
| 木製チェア | 温かみ・安定感 | ナチュラル・安心感のある店 |
| スチールチェア | 無骨・直線的 | モダン・スタイリッシュな印象 |
| ハイチェア(カウンター) | 背筋が伸びる姿勢 | 会話重視・テンポ良い空間 |
| ソファ席・ベンチシート | ゆったり・滞在型 | リラックス重視・高単価向き |



イスは「お客様の姿勢」をコントロールする道具でもあります。
姿勢が前のめりになれば短時間利用、背もたれに沈めば長時間滞在。
つまり、イスの角度が回転率を決めるとも言えます。



確かに、立ち飲みの時って自然とテンポが早くなるもんな。



テーブルやイスなどは大きなインテリアの演出を助けます。
テーブルだけでも、丸いのか、四角いのか、何人掛けなのか、材質は木材なのかガラスなのか、木材だけにしてもワンプライの節目が美しい素材なのかも高級感を演出するに大事な要素となります。
第3章|食器・カトラリーは“静かな演出家”





厨房機器の設置完了、テーブルとイスが用意できたら次は…
食器ってどうやって選べばいいの?
あと何枚くらい必要なの?



料理そのものを引き立てるのが“食器演出”。
色味・素材・反射光をコントロールすれば、料理写真の完成度も上がります。
見た目の統一はブランド力そのもの。
ワンオペ店でも、皿やカトラリーの統一だけで「ここのお店、整ってる」と感じてもらえます。
| アイテム | 意味・効果 | ポイント |
|---|---|---|
| 皿・ボウル類 | 料理の印象を決める額縁 | 同系色で統一感を、和洋折衷は避ける |
| グラス・カップ | 温度・触感で味を補強 | 厚みと素材感がブランド印象に直結 |
| カトラリー | 清潔感・世界観の象徴 | 安っぽい素材は“印象の格下げ” |
食器の揃え方の基本



営業中は洗い物が常に回転しています。
「一巡分+予備」がないと、忙しい時ほど皿が足りないという事態になります。
とくにワンオペ店では、洗浄のタイミングをずらせないので“2倍ルール”が基本です。
| 項目 | 基準 | 理由・ポイント |
|---|---|---|
| 食器の数量 | 客席数 × 2倍 | 洗浄が間に合わない時でも営業を止めないため |
| グラス・カップ | 1日来店見込み+予備10〜20% | 割れやすいため補充分を常に確保 |
| 用意のタイミング | 開店1ヶ月前までに | メニューに合わせた形・サイズ選定が必要 |
| 耐久性 | 業務用仕様を選ぶ | 落としても割れにくく、買い足しが容易 |
グラスとカップの考え方



グラスって、水とかジュースとかお酒とか、種類で全部分けたほうがいいの?



はい。提供内容に合わせて最低限のカテゴリを揃えておくのが基本です。
| 種類 | 用途 | 基準数(10席の場合) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 水用グラス | 食事時の水・お茶 | 20個(座席×2) | 口径が広くスタッキング可能なタイプ |
| ジュース用グラス | ソフトドリンク提供用 | 15個 | タンブラー兼用でもOK |
| アルコール用グラス | ビール・焼酎など | 20個 | メインドリンクなら最優先で多めに |
| コーヒーカップ | 食後ドリンク用 | 10〜15個 | ソーサー付きで演出にも効果的 |
| ティーカップ | カフェ・喫茶系 | 10個 | カップ単体でも使えるデザインを選ぶ |
お酒を扱う店は「グラス在庫」が命



立ち呑み屋や居酒屋のようにお酒メインの業態では、グラス数が回転率を左右します。
とくにタンブラーは一晩で複数回転するため、座席数の2〜3倍は必須です。
| グラスの種類 | 推奨数量 | 用途・特徴 |
|---|---|---|
| タンブラーグラス | 座席数×2〜3倍 | 水・ハイボール・焼酎など万能 |
| ビアグラス | 座席数×2倍 | 泡立ち・冷却効率を意識 |
| ロックグラス | 座席数×2倍 | 焼酎・ウイスキー系で定番 |
| ワイングラス・カクテルグラス | 座席数分 | 演出用。高価なものは限定使用でOK |



お酒の提供回数が多いと、洗浄サイクルが追いつかなくなります。
グラスが足りずに注文を断るのはもったいない。
あらかじめ“使用頻度の高いグラス”を多めに確保しましょう。
食器は業務用じゃないとダメ?



でもさ、業務用の食器って味気なくない?
おしゃれな雑貨屋で買った方が映えるんじゃない?



確かに見た目は大事です。
ただし、飲食店の現場では「揃い続けること」も品質の一部。
業務用食器には次のような特徴があります。
| 比較項目 | 業務用食器 | 一般家庭用食器 |
|---|---|---|
| 継続性 | 同じ型番を長期供給(3〜10年) | シーズンごとに入れ替え・廃盤あり |
| 強度 | 厚手で欠けにくい | デザイン重視で薄い傾向 |
| 補充性 | 業者経由で1枚単位購入可 | 店頭やネットでは在庫限り |
| コスト | 初期費用はやや高め | 安価だが入れ替え頻度が高い |



つまり、「3年後も同じ皿が買えるか」がプロの基準。
家庭用の陶器を混ぜるなら、統一感が崩れても成立するコンセプト
(例:アンティーク喫茶)に限定すべきです。



業務用専門店ではデザイン性の高いものも増えています。
“使い勝手と世界観”の両立ができるのが、現代の業務用食器の魅力ですよ。



家具も食器も、デザインだけじゃなく意味があるんだな。
よし、次は照明とかBGMも含めて“雰囲気づくり”を勉強してみよう!



それがまさに次のステップです。
空間を支える“光と音の設計”――それが「空間演出」です。
第4章|色・照明・BGM・ディスプレイで空間を演出する


基本のテーマカラーを決めよう。



空間演出を考える場合はまず、テーマカラーを考えましょう
色は2色くらいが目安になります。色をたくさん使いすぎると煩くなってしまいますのでご注意ください。
飲食店にオススメのテーマカラー
- 赤などの暖色系:
気分を盛り上げて食欲を増進させます。料理との相性も良く定番のテーマカラーです。 - 青などの寒色系:
落ち着いた雰囲気を演出できます。静かなBARや高級感のあるお店と相性が良いです。 - 白・黒のモノトーン調:
フォーマルな印象を与えて、大人な雰囲気を演出できます。結婚式の二次会などに利用されます。 - ビビットな原色:
明るい元気な雰囲気になります。若者を中心としたファストフード店などにオススメ - ベージュなどの自然系:
モノトーンよりもさらに年上の年齢層や主婦などに好まれる落ち着いた雰囲気で住宅街に出店する場合などに相性が良いです。



木材を使ってベージュ系に統一したり、コンクリート打ちっぱなしのモノトーン調なBARとか素材によってもテーマカラーを引き出すことができます。



壁材にトタンやブリキを多様したり古いモノをあつめてレトロな雰囲気を演出しているお店も有るよね!
照明の色と明るさが決める「お店の時間」
| 種類 | 色温度の目安 | 効果・印象 | 向いている業態 |
|---|---|---|---|
| 昼白色(5000K前後) | 明るく清潔・活動的 | 回転率を高めたい昼営業 | ランチ中心のカフェ・食堂 |
| 電球色(2700〜3500K) | 暖かく落ち着く | 滞在時間を延ばしたい夜営業 | バー・居酒屋・ダイニング |
| 調光照明 | 時間帯で変化可能 | 昼夜で雰囲気を切り替えられる | カフェ&バー・2部制店舗 |



明るさは「心理距離」を縮めます。
明るい空間はフレンドリーに、暗めの空間はプライベートに感じられる。
時間帯や客層に合わせて“照明のストーリー”を作りましょう。



つまり、昼は明るくて元気、夜は少し暗くして落ち着かせる、ってことか。



その通りです。
光は「売上を左右する無言の営業マン」。
電気代をケチるより、光の配置を工夫したほうが効果的です。
BGMは「お客様のテンポ」を決める
| 音楽テンポ | BPM目安 | 客の行動 | 向いている業態 |
|---|---|---|---|
| 早いテンポ(120〜140) | 活発・短時間滞在 | 回転率重視の店 | ラーメン・立ち飲み・ファスト系 |
| 中テンポ(90〜110) | 心地よい滞在 | バランス型 | 居酒屋・カフェ |
| 遅いテンポ(60〜80) | ゆったり滞在・高単価 | 滞在型店舗 | バー・ラウンジ |



人の行動リズムはBGMのテンポに同期します。
BGMのテンポが早ければ会話も短く、食事もテンポアップ。
つまり、BGMで回転率をコントロールできるんです。



へぇ!音楽って“気分”だけじゃなくて、経営にも関わるんだな。



さらに、音量と方向も重要です。
スピーカーを客席の上に向けるより、壁に反射させると自然に包み込む音になります。
静かな店ほど、音の“配置”が効きます。
インテリアの演出:ディスプレイにもこだわりを



コンセプトを軸に店舗の空間のバランスをとるのにディスプレイはとても重要です。
客席まで案内される通路にある巨大なワインセラーやBARのずらっと並んどグラスレール、焼き肉屋などは解体前の肉の塊などお客さんの期待を盛り上げお店のコンセプトを伝えるのに役立ちます。
ディスプレイの基本4原則
- 目立たせる:ディスプレイはお客様の注目を集めるために、壁面など視線が自然と集まる場所に配置します。小物は散らばせるのではなく、目立つように集中的に配置し、大きなインパクトを与える工夫をします。
- 暖色ベースで配色:活動的な印象を与える赤などの暖色は、客席回転を高めるのに有効です。赤色は消化を促し、時間の経過を早く感じさせるため、飲食店のディスプレイには暖色を基調に使うと良いでしょう。
- 清潔に保つ:清潔さは飲食店の信頼性に直結します。ディスプレイは掃除しやすく、ほこりが付きにくい材質を選び、定期的な清掃や取り替えが容易なものにします。
- 定期的に変化させる:同じディスプレイが長く続くと新鮮味が失われ、客の注目を引かなくなります。特に頻繁に来店する常連客が多い店では、季節ごと、あるいはもっと頻繁にディスプレイを変更して店の雰囲気を新しく保ちます。
ディスプレイ・小物で「世界観」を固定する
| 項目 | 役割 | 工夫のポイント |
|---|---|---|
| 壁面ディスプレイ | 店の世界観を見せる | 照明で影を演出し、立体感を出す |
| メニュー掲示 | ブランドの一部 | 手書き or デジタルで印象が変わる |
| 小物・植物・装飾 | 空間の“呼吸” | 同系色でまとめて雑多感を防ぐ |
BGM・照明・香りで視覚以外の空間演出



店の演出は味覚、視覚、嗅覚、聴覚、触覚の5感に働きかける店作りが必要です。
料理でも五感を刺激することができますが、ワンランク上の演出により感動体験を大きなものにすることが出来ます。



人間の五感になにも感じさせることができなければ感動を生むことも出来ず、常連客を作り出すこともお客さまから愛されるお店を作ることも不可能になります。



演出効果ってこんなにたくさん意味があるんだね!



照明の色と明るさでお店の雰囲気は大きく変わります。
照明を暗くすると風営法の許可が必要になる場合がありますので低照度にする場合はご注意ください。



装飾は“語らない接客”です。
お客様が無意識に「ここ、好きだな」と感じるのは、
統一されたテーマと余白の取り方が上手なお店。



なるほど、センスじゃなくて構成なんだな。
俺も自分の店の「物語」を飾ってみようかな。



いい発想です。
ディスプレイは“飾る”ではなく“語る”。
そのお店が何を大事にしているかを静かに伝える役目です。
演出効果まとめ
- 照明
- 照度:明るいと人間は活発的になり暗いとリラックスできます。
- 光源:電球は暖色ベースで料理も美味しそうに見えます。蛍光灯はキッチンに向いていて色や文字がハッキリ見えます。
- 直接:間接照明:直接照明は普通の照明です。間接照明は壁に反射させて光を柔らかくする効果があります。
- BGM
- 音響設備はこだわりがあれば天井につるすタイプが良いでしょう。音の広がりが良いです。
- 音楽のジャンル:ジャズ=お酒を中心にしたお店、クラシック=ゆっくりくつろげるカフェ、流行りの曲=若者向けや庶民的な定食屋など
- 香り
- オープンキッチンやテーブルの上で仕上げのスパイスを削るなどの演出は香りと印象を深く刻み込むのに大きな効果あります。生ゴミなど悪臭が客席までいかないように注意も必要です。



ここまでで「設備・家具・空間演出」が揃いました。
ですが、忘れてはいけない最後のテーマがあります。
どんなに美しい空間も、“清潔”でなければすべて台無しです。
次の章では、“美しい空間を保つ技術”――クレンリネスについて話します。
第5章|演出の最後は「清潔感」で決まる!クレンリネス設計



うーん…おしゃれに作ったはずの店なのに、なんかすぐ生活感が出ちゃうな。
ホコリや油汚れが目立つっていうか…これって掃除の仕方が悪いのか?



いいえ、それは設計段階での“クレンリネス設計不足”です。
おしゃれな店ほど、入り組んだ照明や装飾が多く、
実は掃除しづらい構造になっていることが多いんですよ。



デザイン=掃除のしやすさです。
「汚れを溜めない構造」にしておくことで、
開業後の清掃コストと労力を大幅に減らせます。
クレンリネス設計で気をつけるポイント
| 設計箇所 | よくある問題 | 改善ポイント |
|---|---|---|
| 床 | タイル目地に汚れが溜まる | 目地の少ない素材を選ぶ(塩ビタイル・長尺シート) |
| 壁・天井 | クロスや木目調の凹凸にホコリ | 拭き掃除できる耐水素材に |
| 照明 | ペンダントライト上部に油埃 | 埋め込み型や清掃しやすいカバータイプ |
| 厨房機器 | 隙間に油・水が溜まる | 壁付け・脚付きで下を掃除できる設計に |
| テーブル・イス | 脚の数が多く掃除が面倒 | 片側ベンチ・固定脚で省力化 |



“掃除しやすいデザイン”は、結果的に美しさを長持ちさせます。
毎日30分の掃除が10分で終われば、その分お客様対応に回せますからね。



確かに、オープンしてすぐは気にならないけど、
数ヶ月経つと“見えない汚れ”ってめっちゃ気になるんだよな。



人間の五感は鋭いものです。
少しの油臭・ほこり・手垢でも「なんか居心地悪いな」と感じる。
つまり、清潔感こそ最強のリピーター対策なんです。
ワンオペ店におすすめの“省力清掃アイデア”
| 分野 | 工夫 | 効果 |
|---|---|---|
| 床掃除 | ワイパー+使い捨てドライシート | モップより時短、髪や埃も即除去 |
| テーブル | アルコールクロス常備 | 準備中・片付け中どちらも時短対応 |
| 厨房 | 業務用アルカリ洗剤+水スプレー | 油汚れを溜めない「1日1分ルール」 |
| エアコン・換気扇 | 定期的に分解清掃 | におい・効率・電気代対策の三拍子 |



クレンリネスを「習慣化」できれば、
店の雰囲気は半年後・一年後でも新品同様に保てます。
“磨かれたお店”は、“信頼されるお店”。
だからこそ、清掃を「経営の一部」として考える必要があります。
まとめ



以上が店舗づくりに必要な構想になります。
小さないお店を開店する場合は使える面積が狭いので設置できる機器も最低限になってしまいますので、この構成の段階から吟味することが重要になります。



内装のテーマカラーやBGM、照明や香りなどでお店のコンセプトをひきたてることができます。
お店の重要なポイントは非日常を感じてもらうことです。
現在の飲食店のライバルはコンビニです。
お腹を満たすだけならコンビニのほうが安くて便利ですが、レジャー感で勝負することであなたのお店に価値を感じてお客さんが来店してくれることにつながるでしょう。



ぼくが実現したいお店の理想はいろんな人が気軽におとずれてワイワイとコミュニケーションを楽しむことができるお店。
ボクのお店にしかできない付加価値みつけていくよ!