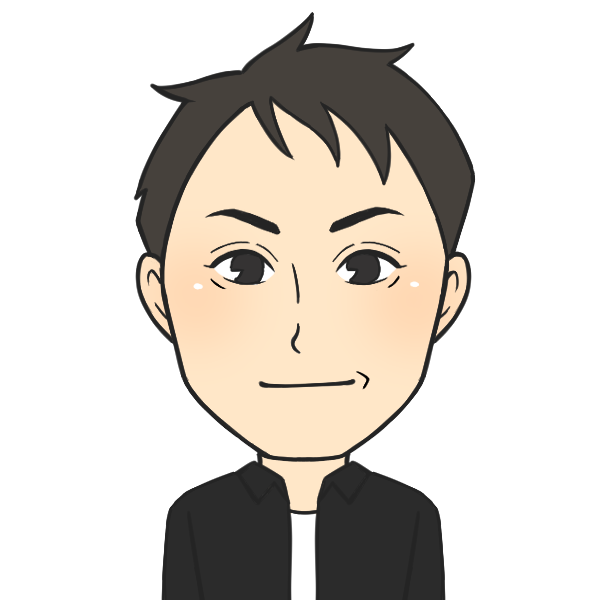甲斐承太郎
甲斐承太郎なんか起業セミナーとかでよく耳にする商工会議所ってなに?
ここに加入するとどんなメリットがあるの?
てか、ボクは会議なんて嫌いだから商工会に入ろうかな?



経営の厳しさ、予算の制約、そして何より「加入する価値が本当にあるのか」という疑問は、個人経営者ならではの切実な悩みですよね。
この記事を通じて、商工会議所が個人飲食店にとってどれほど有益かを具体的にご説明します。
- 商工会議所の提供する具体的なサポート内容を理解できる。
- 加入費用とサービスの価値を比較検討する助けとなる。
- 他の個人飲食店オーナーの成功例を知ることができる。



商工会議所は、事業の成長と安定を支援する多種多様なリソースを提供します。
具体的には、資金調達の支援、法律や税務の専門家による無料または割引の相談、地域内でのネットワーキング機会の提供などがあります。
これらは特に資金やリソースが限られている個人飲食店にとって、事業拡大や持続可能な経営に不可欠です。
そもそも商工会議所とは?
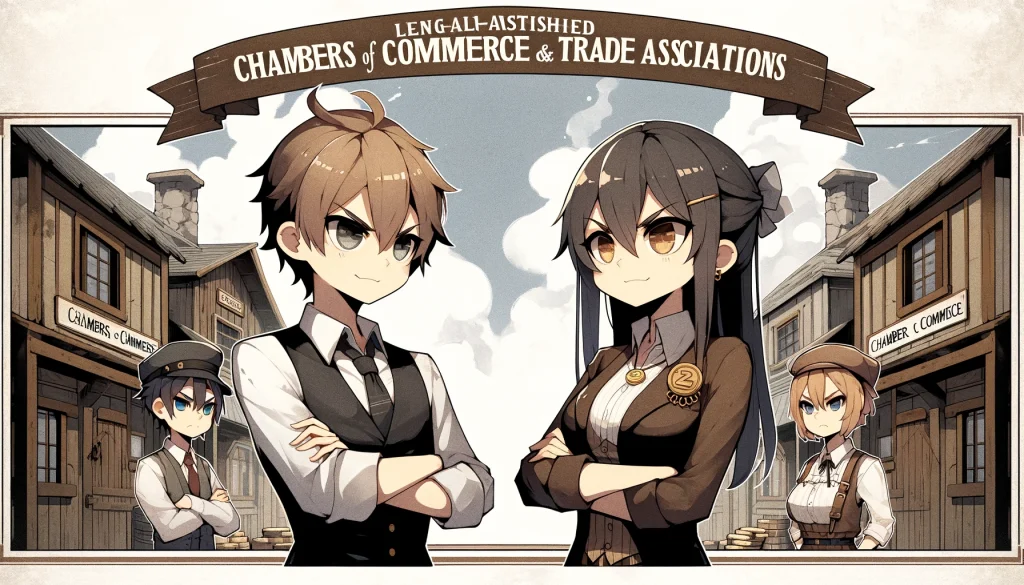
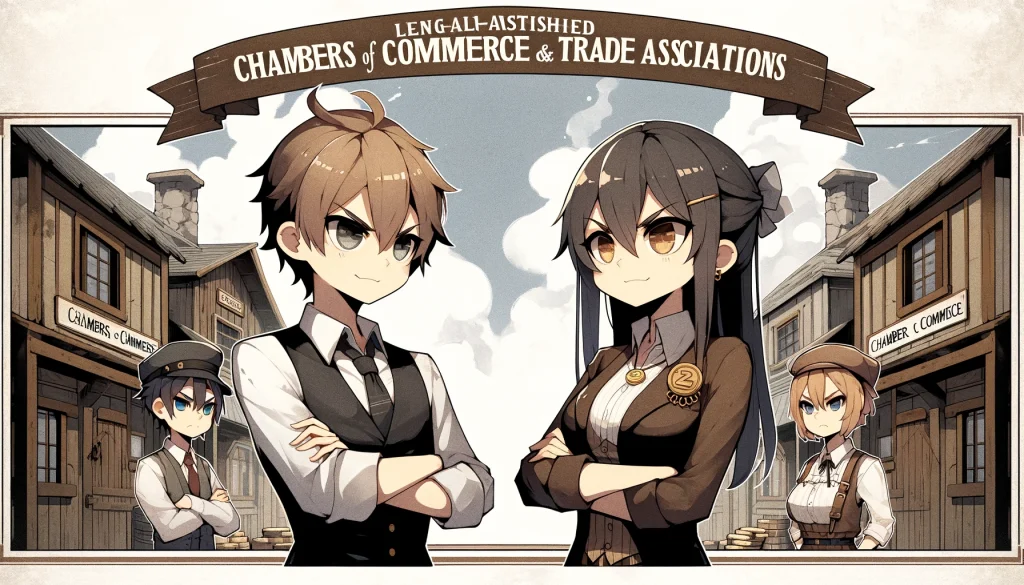



そんなわけで商工会議所ってナニモノなの?



先に言っておくと、『商工会議所』と『商工会』は別物です。



ええ!会議がアルかナイかじゃないの?



商工会議所と商工会の主な違いを比較表にまとめました
| 項目 | 商工会議所 | 商工会 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 商工会議所法 | 商工会法 |
| 管轄官庁 | 経済産業省 経済産業政策局 | 経済産業省 中小企業庁 |
| 対象地域 | 市の区域 | 町村の区域 |
| 会員構成 | 小規模事業者:約8割 | 小規模事業者:9割超 |
| 主な事業内容 | 中小企業支援+国際活動 | 小規模事業者の経営改善普及に重点 |
| 設立要件 | 特定商工業者の過半数の同意 | 地区内商工業者の2分の1以上が会員 |
| 意思決定機関 | 議員総会:選挙された議員による (会員数30~150人) | 総会:全会員構成 (会員200人超で総代会設置可) |
| 議決権 | 会員:部会で1人1票、選挙権は会費口数に応じ最大50票 | 1会員1票 |



商工会議所または商工会のどちらかを選択することができます。
どちらの組織も事業の成功をサポートするための貴重なリソースを提供していますので、事業の目的や目標に合った組織を選ぶことが重要です。



商工会議所と商工会を合わせて『商工会等』と呼びます。
商工会等は、地域の企業や店舗の成長を支援するための非営利の公的な団体です。
日本全国にあり、地域の経済活動を活性化させることを目的います。
商工会等の主な活動
- 政策提言活動:地域の声を国や自治体に届ける。
- 会員交流事業:ネットワーキングや情報交換の場を提供。
- 検定事業:簿記検定などスキルアップの支援。
- 国際化支援:海外進出を目指す事業者へのサポート。
- 共済事業:低コストの保険でリスク管理を強化。
加入するメリットとデメリット





結局、ボクみたいな小規模で一人でやっていく個人事業主は商工会等には加入すべきなの?



もちろん、上手に活用することで多くのメリットを享受することができます。
以下にメリットとデメリットを比較します。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 資金面 | 無担保・無保証で融資が受けられる「マル経融資」、補助金・助成金のサポートあり | 年会費が必要 (例:札幌商工会議所で18,000円〜) |
| 専門家の支援 | 税務、法律、労務などの専門的なアドバイスを低コストで利用可能 | 一部のサービスが事業規模や業種に合わない場合がある |
| ネットワーク構築 | 地域内の他の事業者との交流イベントやセミナーで新たな顧客やパートナーと出会える | イベントやミーティングへの参加が時間的な負担になる場合がある |
| 信頼性 | 会員であることで地域や顧客からの信頼性が向上 | 地域イベントや協賛活動など、追加の負担がある場合がある |
| スキルアップ | セミナーや研修を割引価格で受講可能 | – |
| 保険・共済 | 小規模企業共済や生命共済で低コストのリスク管理が可能 | – |
| 政治的な側面 | – | 一部の活動が自身の価値観や事業方針と一致しない可能性がある |



地域イベントに強制参加だったり、政治活動もさせられるの?



確かに商工会等は地域活動への積極的参加を求めることが多く、時にはそれが負担に感じることもあります。
地元のお祭りやイベントへの協賛金を求められたり、頻繁な飲み会への参加など、経営者としては時間とコストの面で考慮する必要があります。



それに、特定の議員との癒着や政治的な動きが見えることも懸念材料の一つです。
これらの活動が全ての会員にとって有益であるとは限らず、自分の事業方針や個人的な価値観と異なる場合、加入のメリットを十分に考える必要があります。
商工会等に加入することで受けられる7つサービス





加入したらどんなサービスを受けられるの?



①経営相談、②独自の融資制度、③補助金・助成金、④専門家派遣制度(エキスパートバンク)、⑤研修やセミナーの開催、⑥合同会社説明会、⑦共済制度の7つのサービスを紹介します。
①経営相談



経営上の悩みや課題に対して専門的なアドバイスを提供します。
これには創業・起業支援、デジタル化支援、記帳指導、税務相談、融資相談、経営改善支援、企業再生支援、事業継承支援、知的財産相談などが含まれます。



具体的な例でいえば、「札幌市創業支援等事業計画」があります。
詳細については下記で解説しています。
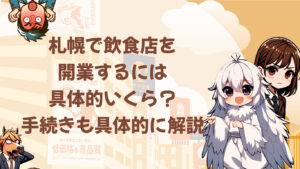
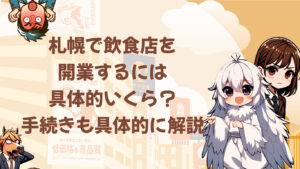
②独自の融資制度



商工会等には『マル経融資』という独自の融資制度があります。
マル経融資は商工会等の推薦があれば、日本政策金融公庫から無担保、無保証人で最大2000万円まで融資を受けることができます。
これは1973年に小規模事業者の資金調達を支援するために設けられた制度で、特に経営指導を受けている事業者が対象です



また、マル経融資にはいくつかのバリエーションがあって、通常のもの以外にも新型コロナウイルス対策としての特別なマル経融資や、危機対応型マル経融資など、時期や状況に応じた支援が可能です。



すごいね。
でも、どうやって申し込むの?



まずは商工会等で6ヶ月以上の経営指導を受けることが基本要件です。
その後、商工会等に融資の推薦を依頼して、日本政策金融公庫に申し込みます。審査を経て融資が決定し、資金が提供される流れになります。
ちなみに、商工会等のメンバーでなくても申し込みは可能ですが、会員であればその他のサポートも受けやすくなりますよ。
③補助金・助成金



商工会等では多種多様な補助金や助成金が用意されています。
例えば、「小規模事業者持続化補助金」があって、これは創業者が最大50万円の補助を受けることができる制度です。
この補助金は、特に新しい商品開発や市場拡大を目指す事業者にとって大きな助けになるでしょう。
ただ、補助金を受けるには、しっかりとした事業計画と実行力が求められるから、準備が重要です。



どうやったら補助金がもらえるの!?



まずは、事業計画書や創業計画書をしっかりと作成することが大切です。
それが承認されれば、補助金が交付されるわけだけど、使用後は事務局に対して報告書を提出する必要があります。
また、補助金を使って何をしたのか、具体的な成果もしっかりと示すなど要件が多くあります。
詳しくは別記事でまとめてあります。
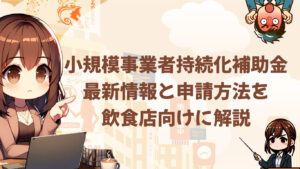
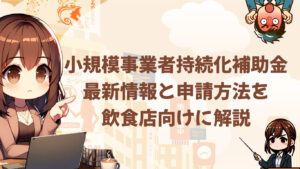
④専門家派遣制度(エキスパートバンク)



専門家を現場に派遣してくれる「エキスパートバンク」制度というものがあります。
マンツーマンで、ITや生産管理など、多岐にわたる専門分野での相談に対応しています。
派遣される専門家は、各分野で豊富な経験と知識を持っているので、具体的な問題解決に非常に役立つでしょう。



いいね!それ!!
どうやって申し込めばいいの?



まずは商工会等に連絡して、利用申込みを行います。
そこから本所の経営指導員がヒアリングをして、あなたのニーズに合った専門家との派遣調整を行ってくれます。
派遣は最大3回まで無料ですし、秘密厳守で対応してくれるので安心して相談できます。
相談内容が複雑で、さらに支援が必要な場合は、有償での個別対応も可能です。
⑤研修やセミナーの開催



実は商工会等では、さまざまなビジネススキル向上のための研修やセミナーを開催しています。
例えば、マーケティングや財務管理、デジタルツールの活用方法など、多岐にわたるテーマで開催されてます。
しかも、会員であれば割引価格で参加できるから、コストパフォーマンスも非常に高く、各セミナーは現役の専門家が講師として直接教えてくれるから、具体的で実践的な知識が身につくきます。



なんかよく簿記検定の研修とかやってるよね!
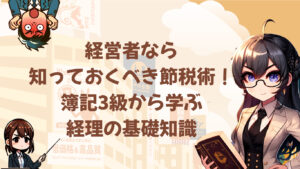
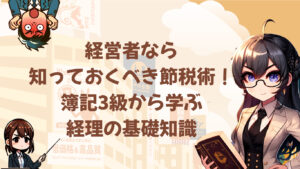
⑥合同会社説明会



合同説明会(合説)は、多くの企業が一堂に会し、様々な業界や職種の情報を提供するイベントです。
主に求職者や学生が参加し、企業の人事担当者から直接話を聞くことができるため、職業選択の幅を広げるのに非常に有効です。



僕の場合は転職は希望してないから関係ないかな
⑦共済制度



個人事業主になったら加入必須の保険制度が
「小規模企業共済制度」や「生命共済制度」です。
低コストで、事故や病気などによるリスクをカバーできます。
特に「生命共済制度」は、24時間全世界での保障があり、小規模な事業者でも気軽に加入できるんです。



たとえば、病気や事故で入院した場合の日額給付金や、もしものときの死亡保障があります。これに加えて、先進医療費用保険金補償特約を付帯することも可能です。



そして「小規模企業共済制度」は、事業を辞めたり、役員が退職したりした際に、生活の安定を支える退職金的な役割を果たします。これがあれば、未来の不安からも少し解放されます
- 目的: 個人事業主や小規模企業経営者の退職金準備のための制度。
- 掛金: 毎月の掛金は1,000円から最大70,000円まで自由に設定可能。
- 掛金の調整: 掛金は増額や減額が可能(ただし減額時には一定の要件が必要)。
- 税制優遇: 支払った掛金は全額所得控除の対象となる。
- 共済金の支払い: 事業をやめたり、退職した場合に共済金が支払われる。一括受取の場合は「退職所得」扱い、分割受取の場合は「公的年金の雑所得扱い」となる。
- 対象者: 事業主、役員、従業員が対象。商工会議所のスケールメリットを利用して低コストで提供。
- 保障内容: 病気や事故による死亡および入院など、業務上・業務外を問わず24時間保障。
- 加入条件: 医師の診察が不要で、告知に基づき加入が可能。
- 特約の付帯: 5口以上加入することで、「先進医療費用保険金補償特約」を付帯することができる。
- 剰余金の配当: 毎年収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金として支払われる。



それは心強いね。申し込みはどうしたらいいの?



商工会等に直接連絡をして、共済制度の申込みを行います。
手続きはとてもシンプルで、商工会議所のスタッフが丁寧にサポートしてくれます。



ほかの保険についてはこちらの記事でも解説しています。


まとめ



今回は商工会議所と商工会を合わせて商工会等について見てきました。
商工会等に加入することで経営相談から補助金、専門家の派遣まで、多岐にわたるサポートが受けられます。
さらに小規模事業者向けの融資制度や、経営に役立つセミナーにも参加できます。それに、病気や事故に備える共済制度も充実しています



商工会議所は地域のビジネスコミュニティとのネットワークを築く絶好の場です。
他の事業主との情報交換だけでなく、新しいビジネスチャンスを見つけることも可能です。
ここのポイントが良い方向か悪い方向かに左右されるポイントであるのには注意が必要ですが、それでも商工会議所に相談すれば、事業に最適なプランを一緒に考えてくれます。
ビジネスを強化する大きな一歩になるはずです。



個人事業主は個人だからこその孤独感や拭えない不安感はつきまとうけど、相談できる相手がいることはやっぱり心の拠り所になるよね。
最初のうちは顧問料と思って加入して一生懸命走ってみるのも悪くないかもね!